工房集の作家たち・特別編:knock art 10
昨年10月から先週まで9回にわたってお送りしてきた「工房集の作家たち」シリーズ。今回はその特別編として、工房の作家たちも多数参加し、12月4日から8日まで埼玉県立近代美術館で開催際された第10回埼玉県…
art museum of roadside art 大道芸術館、オープン! |
|
|
|
先週の編集後記でひっそりお知らせしたとおり、東京墨田区の花街・向島に「museum of roadside art 大道芸術館」が10月11日、公式オープンした。 |
|
昭和の純喫茶、昭和の歌謡曲、昭和のラブホテル…… |
|
[museum of roadside art 大道芸術館 誌上ツアー] |
|
大道芸術館(以下MORA)は元料亭だった3階建ての建物全館を使っている。料亭時代そのままの木戸をがらがらと開けると、お出迎えするのが鳥羽の秘宝館入口にあった女体入りカプセルだ。 |
|
|
|
1階向かって左側の奥に進むと、貸し切り用のカラオケルームがある。とはいえ今どきの通信カラオケではなく、長く収集してきた昭和のレーザーカラオケ、およそ1500曲の映像で歌っていただける特別な「音楽室」だ。デザインのテーマはデコトラ! 運転席に使われる「金華山」と呼ばれる高級生地を贅沢に使っている。 |
|
|
|
レーザーカラオケは3分間の人生劇場だった |
|
分別あるはずのオトナから分別を奪い去るカラオケの魅力、それはなにより歌詞の魅力なのだと思う。「別れる前に、お金をちょうだい。そのほうがあなただって、さっぱりするでしょ」なんて美川憲一の心境におのれを重ね合わせられるようになるのは、やっぱりこれから人生下り坂と悟る中年期にさしかかってからのことだろう。 |
|
|
|
20世紀後半は音楽が革命的な転回を遂げた時代だった。エレキギターという、だれでも簡単に巨大な音を出せる機械を得たロック・ミュージックが、それまでの音楽家という専門職を土台から揺るがせた。”楽器が演奏できなくてはならない”という大前提をヒップホップのターンテーブルが、”歌がうまくてはならない”という大前提をラップが破壊し、そして”歌は専門家が歌って聴かせるもの”という基本常識を見事にひっくり返したのが、カラオケという魔法の箱だった。 |
|
|
|
映像・音声ともに圧縮のかからないデータを記録できることから、画質も音質も現在のDVDより優れたレーザーディスクは、日本ビクターの開発したVHD方式との競争に、圧倒的な不利をはねかえして勝利をおさめ(採用メーカー数ではレーザーディスクがパイオニア1社だったのに、VHD陣営は13社だった)、映画ソフトとカラオケ・ソフトの両方で全国に普及していった。 |
|
カラオケルームのガラステーブルをけなげに支えるのは、オリエント工業製のラブドール。珍しい「泣き顔」だ。奥の壁面には天才蝋人形師・松崎覚さんによる艶やかな蝋人形が覗き窓のような小部屋で微笑んでいる。 |
|
|
|
東京杉並区の住宅街に、深い木立に隠れる洋館。松崎覚さんの「蝋プロ」を初めて訪ねたのは、帰りのタクシーの中で運転手さんから「なんかニューヨークで飛行機がビルに突っ込んだみたいですよ」と教えてくれた日なので、いまでも忘れられない。洋館の室内にはピカソやチェ・ゲバラやジョン・レノンが暗がりに佇み、グランドピアノの上では昭和天皇の頭部がメガネ越しにこちらを見ていた。 |
|
|
|
マダム・タッソーに代表されるような一般的な蝋人形は、粘土の原型から石膏型をつくり、そこに蝋を流し込んで固めた人体に彩色していくが、松崎さんは極力彩色を避け、さまざまな種類、色合いの蝋を自在に組み合わせながら、蝋の肌が語りかけるような蝋人形をつくる。たとえば手の全体をつくり、そこに濃い色の蝋でつくった血管を乗せ、さらに半透明の蝋の皮膚を乗せて微妙な透け具合を表現する、というふうに。 |
|
|
|
そして壁面を飾るのは「ブラック・ベルベット・ペインティング」と呼ばれる、かつてアメリカを中心にポピュラーだったお土産用の絵画。画用紙やキャンバスの代わりに、通常黒いベルベット地に描かれた手描き作品である。戦後アメリカで普及し、キッチュな土産物の代名詞となった。特に人気だったのが「ベルベット・エルヴィス」と呼ばれたエルヴィス・プレスリーやジョン・ウェイン、ネイティヴアメリカン、オオカミ、イエス・キリストなどとともに、1960~70年代にはこうしたエキゾチックなニュアンスを漂わせるヌード・ベルベットもよく描かれていた。それはTIKIに代表されるエキゾチカ・ブームの一端と見ることもできる。 |
|
|
|
カラオケルームの入口まわりは小さめの作品で飾られている。 |
|
|
|
《美川憲一》小川卓一 |
|
港からすぐに商店街、その先は高台に向かって張りつくように住宅街が広がる尾道。その階段迷路のような街並みの一角に「ふりむき館(やかた)」があった。地元の人間だけに知られながら、日々増殖してきたプライベート・ギャラリー。その主が小川卓一さん。 |
|
|
|
《ノーマ・ジーン・ベーカー》ピエトロ-L-キクタ |
|
ピエトロ-L-キクタ画伯は路上生活者=ホームレスの画家。ふだんは横浜駅西口ダイヤモンド地下街に下るエスカレーター前で「ビッグイシュー」を売って生活費としているという。美術評論家・宮田徹也さんの尽力で、2011年と2012年にホームグラウンドの横浜で個展も開催している。 |
|
|
|
香港の陶器人形 |
|
まだ英領だったころの香港、裏通りのジャンク骨董ショップを漁っていたら、美女に耳かきされて至福の表情のじいさんに将来の自分を見た気がした。値段も手ごろだったので東京に持ち帰った陶器人形。極細の耳かきがよく、いままで折れずにいてくれた。 |
|
|
|
吉岡里奈 |
|
描くもの、書くもののイメージと、本人の見かけがかけ離れているというのはよくあること。僕もそう言われることが多いが、2016年に『女たちの夜』というZINEのような作品集を、作者である吉岡里奈そのひとから手渡されて、「え、これ描いたんですか?」と、かなりとまどったのを覚えている。目の前に広げられたお色気熟女(とオヤジ)がプンプン振りまく昭和の匂いと、目の前にいる女の子の見かけが、どうしてもうまく合わさらなかったからだ。そんな吉岡さんの作品がMORAには2点、展示されている。 |
|
|
|
だからいまでも絵の対象として描きたいのは、ぜったい女なんです。男には興味なし。おじさんは描きますけど、それはエビフライのパセリみたいな添え物。若い男にはさらに興味ないし、ぜんぜん描けないです。だって女は顔だけで3日くらいかかったりするけど、おじさんは2時間ぐらいで描いちゃうから。 |
|
|
|
バンコクの犬 |
|
バンコクのショッピングセンターをぶらぶらしていたら、肖像画屋が並んでる一角に出た。古い写真を持っていくと立派な油絵に描き起こしてもらえる、日本でも昔はよくあった商売だ。狭苦しい店の壁に、おじいさんやおばあさんの顔や、どうでもいい風景を描いた油絵がびっしり掛けてある。その下ではイーゼルをずらりと並べて、若い画家たちが小さな写真を脇に置いて一心に絵筆を振るう。その雰囲気が好きで、このへんをよく散歩していた。 |
|
|
|
肖像画屋のお姉さんと話していて、いちばんおもしろかったのは値段の決め方だった。ダヴィンチでもモネでもダリでも、作家の名前は値段にいっさい関係ない。値段を決める要素はただふたつ、サイズと……絵具の色数(!)。まあ、これに絵柄の複雑さが加味されもするのだが(ロスコとかモンドリアンとか安いはず)、もともと抽象画は人気がないそうなので、ほとんどの場合、値段はサイズと色数だけで決められる。これこそ絵画(の値付け)の原点だと思ったりして。 |
|
|
|
《無題》柊一華 2019年 |
|
柊一華(ひいらぎ・いちか)はSMクラブを経営する女王様として働きながら、10年近く前から写真を撮るようになった。愛用するカメラはHOLGA。中判のブローニーフィルムを使用するトイカメラファンにはおなじみの、いいかげんなつくりで、現像するまで結果がわからなくて、その写りの悪さと緊張感がたまらない、そういう楽しさにあふれたカメラだ。 |
|
|
|
父親が亡くなって遺品整理をしていたときに、古いオリンパスのOM-1が出てきて、「使えるのかなと思ってフィルムを買ってきて、子どもとか適当に撮ってみたらすごくいい感じで、それで楽しくなって趣味で撮るようになったんです」。 |
|
|
|
《Hang-Kreung》ナリモン・パドサムラーン(Naruemon Padsamran)2009年 |
|
パドサムラーンは1981年生まれのタイ人アーティスト。モーラム/ルクトゥーンといった、タイの民謡や演歌・歌謡曲をフィーチャーした野外ショーを経営する家に生まれた。中学生のころから看板やコンサートの背景画を描き始め、それが高じてマハーサーラカーム大学美術学部に進学。卒業論文制作のため、彼女の芸術的インスピレーションの原点である野外歌謡曲ショーで使われた看板を解体・再構成し、タイの民謡の踊り手たちのフォームやポーズをかたどった立体作品をつくりはじめた。この作品は地獄寺の撮影に夢中になって、バンコクにアパートを借りて通っていたころ、ふと立ち寄ったギャラリーで出会ったもの。 |
|
|
|
『女子・小人プロレスリング大試合と20世紀のスリラー大魔術』ポスター |
|
福島県本宮市に1914年創業、2022年に108年を迎えた本宮映画劇場。街並みの奥に分け入っていくと、いきなりあらわれる褪せたピンク色の巨大木造建造物が、1963(昭和38)年に閉館した当時の姿をそのまま残している。それは館主・田村修司さんの半世紀にわたる孤独な闘いがもたらした奇跡の戦果でもあった。閉館以来、館主だった田村さんはまったく再開の見込みもないまま、旧式な映写機をメンテナンスしつづけ、館内を掃き清めつづけ、たったひとり、いつでも映画を映せる状態に劇場を保ちつづけてきたのだから。町民からの無関心や嘲笑揶揄に耐えながら。 |
|
|
|
ここまでで1階から2階へ上がる階段の途中まで。来週は続けて2階のバーエリア「茶と酒 わかめ」にお連れする! |
|
|
|
都築響一コレクション |

昨年10月から先週まで9回にわたってお送りしてきた「工房集の作家たち」シリーズ。今回はその特別編として、工房の作家たちも多数参加し、12月4日から8日まで埼玉県立近代美術館で開催際された第10回埼玉県…

今回ドクメンタでは、設置場所や制作プロセス等自分自身初めて経験することが多く、またそれに伴う不安も大きかったので現地でのそんなダイレクトな人々の反応は心に染むものがあった。多くの観光客でごった返してい…

バレンタインデーの日、 会社では、女性同士が話し合い、男性スタッフにチョコを配ります。 チョコ選びが得意な人が、有名パティシエから、老舗の洋菓子店、和菓子店とどんどん提案してきます。 最後は、多…
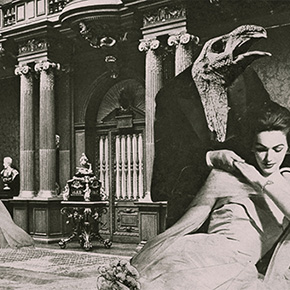
高知県立美術館で『岡上淑子コラージュ展――はるかな旅』が開催中だ。この展覧会を待っていたひとは少なくないと思う。今年90歳になった岡上さんの初の大規模回顧展である本展は、国内所蔵のコラージュ80点、写…

千葉県市原市、と言われてピンとくるひとはどれくらいいるだろうか。ジェフユナイテッド? ぞうの国? 鉄ちゃんなら可愛らしい小湊鐵道を思い出すかもしれない。房総半島のほぼ中央に位置する市原市は、市制施行5…

ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。
本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。
旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。

稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。
1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!

プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。
これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。

書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい
電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。

伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!
かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。
ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。

――ラブホの夢は夜ひらく
新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。
円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!

――秘宝よ永遠に
1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。
すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。
1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!

70枚のTシャツと、70とおりの物語。
あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。

編集に「術」なんてない。
珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。
多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。
編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。
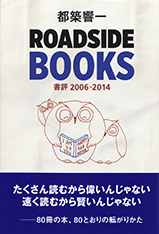
こころがかゆいときに読んでください
「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。
このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。

あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。
たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。

いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。
咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。

2012年、東京右傾化宣言!
この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!
576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!