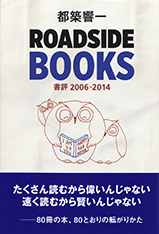- TOP
- バックナンバー
BACKNUMBERS
バックナンバー
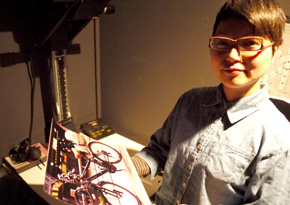
photography
「大阪式」に生きるということ
いまからもう10年以上前のこと、大阪の小さな写真専門学校でトークに招かれ、そこは写真館の跡継ぎ養成みたいな地味な学校だった。学生寮があるというので、「寮の中を撮影させてくれるなら」という交換条件で引き受けたトークを終えたあと、生徒たちの緊張感のないポートフォリオを見せられて、そのなかでひとりだけ、きわだってヘンテコで輝いていたのが梅佳代だった。

photography
佐藤信太郎 『東京 I 天空樹 Risen in the East』
『東京 I 天空樹』には2008年12月、まだ更地だった段階から、2011年8月、すっかり完成した姿が隅田川の花火と並んで見えた夜まで、52景のスカイツリーが記録されている。そこに、ありがちな「真下から仰ぎ見るスカイツリーの威容」なんてカットは1枚もない。あるときは近くから、あるときはすごく遠くから撮影されているのは、「風景の中のスカイツリー」だ。

photography
石川真生『港町エレジー』
ここにあるのは『日の丸を視る目』のような明確な社会派メッセージではなく、おのれの肉体にすべてをかけて生きる男たちの圧倒的な存在感に、目を見張る女性写真家のまなざしです。撮影されたのはいまから20年以上前ということになりますが、これが50年前でも、いまでもたぶん変わらないであろう、フリチンの生き様。モノクロームの画面から匂い立つような、男臭さ。

photography
刺青村長!
四ッ谷3丁目のギャラリー・シュハリで今月28日から開催されるのが、片山恵悟さんの『刺青村長』。「刺青村長、変態村の住人たちの、歌と踊りのしつこい饗宴!」というキャッチコピーもイカレてますが、写真もすごい・・見ておわかりのとおり。片山さんは本業が雑誌編集者。それも『実話マッドマックス』『劇画マッドマックス』両誌の編集長という、なかなかスリリングな誌面の責任編集を長く続けているので、その人脈と度胸とエネルギーは大したもの。東京の、いちばんディープなアンダーグラウンド・シーンに案内してくれます。
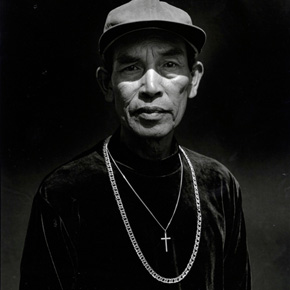
photography
地霊:多田裕美子と山谷の男たち
仕事にあぶれた男たちが道ばたにうずくまる山谷の通りを、まるで山谷っぽくない、若い女の子がカメラを提げて歩いて行く。後ろに続くのは重そうなカメラバッグや三脚や、背景布を担いだ、いかにも山谷の男たち。ちょっと変わった一行は、山谷の中心である玉姫公園に到着すると、慣れた手つきで黒い背景布を広げ、カメラをセットし、植え込みの一角に板を立てる。その板にはこんな文句が書かれていた――

photography
うれし恥ずかし駅前彫刻
ある日、友人から届いた封書には「都築くんならこういうの好きかと思って・・」というメッセージとともに、小さな手づくり雑誌が2冊入っていた。『駅前彫刻』と『駅前彫刻2』と題されたそれは、名前のとおり駅前や公園や道端に、だれにも気にされないままひっそりたたずむ、ブロンズや石の彫刻作品を撮影した写真集だった。

photography
大阪式とベルギー式
四ッ谷3丁目のギャラリー・シュハリで開催中の『大阪式 コノハナ/24区』。以前にこのメルマガでも紹介した、大阪出身の写真家・谷本恵さんの、4回目となる『大阪式』です(以前の記事は1月18日号参照)。今回は天王寺エリアを離れ、これまたディープな大阪湾に面した此花区に遠征。いつものように、なんとも言えないリアル・ナニワ・スタイルをキャッチしていて、見てるだけで大阪下町世界にワープさせられる気分です。添えられたテキストも、渋い人情味満点で、ホロリとなりますよ~。

photography
サードライフにようこそ
古くからの友人でノーバート・ショルナーという写真家/映像作家がいます。ドイツ出身、1989年にロンドンにやってきて、当時最先端だった『FACE』や『i-D』誌で、いきなり活躍しはじめました。僕が知り合ったのもそのちょっと後ぐらいですが、ヴォーグをはじめとする世界中のハイファッション誌で、シャネルにプラダ、マックイーンまでトップデザイナーのファッションを撮影するような超売れっ子でありながら、いつも画面にはちょいブラックで悪戯っぽいテイストが見え隠れしていて、すごく好きなフォトグラファーでした。

photography
アメリカの『ねじ式』
以前このメルマガで『ヤング・ポートフォリオ』という企画展を紹介した清里フォトアートミュージアムで、いま『Flash! Flash! Flash! エジャートン博士、O.ウィンストン・リンク、ERICの写真』という、なかなか変化球の展覧会が開催中だ(12月24日まで)。この3人の名前だけでピンと来るひとはかなりの写真通だろう。ハロルド・エジャートン博士は、ストロボの発明者として有名。撮影に25年間を費やしたという「ミルククラウン」や、リンゴを突き抜ける弾丸の写真は、いちどは見たことあるひとも多いはずだ。

photography
記憶の島
川崎の生田緑地にある岡本太郎美術館で、いま『記憶の島――岡本太郎と宮本常一が撮った日本』という展覧会が開催中です(10月8日まで)。宮本常一(みやもと・つねいち)は偉大な民俗学者であり、僕のこころの師匠でもあるというか・・『土佐源氏』のような物語を、死ぬまでにひとつでいいから書いてみたいというのが夢でもあり。宮本常一は1907(明治40)年、岡本太郎は1911(明治44)年生まれ。ふたりは同時代人でもありました。そして岡本が華々しく活躍しながら、美術業界からは常に一歩引いた目で見られてきたように、宮本もまた民俗学の本流であった柳田国男派から長らく、徹底的に冷ややかな目で見られてきた、アウトサイダー的な存在でもありました。

photography
鳥取の店構え
こないだ鳥取の図書館で、鳥取市内の繁華街の写真を探していたときのこと。地元史の棚で、ペーパーバックの地味な写真集が目にとまった。『池本喜巳写真集 近世店屋考』――なにげなく手にとってパラパラしてみたら、それは鳥取県内の昔ながらの商店をモノクロームで撮影した記録だった。床屋、米屋、金物屋、時計屋、荒物屋、酒屋、駄菓子屋・・・大型カメラでじっくりきっちり、構図を固めて写し取られた空間と人物たち。1983年から2005年というから、20年間以上にわたって収集された鳥取の商店は、どれも数十年の歴史を経てきたものばかりだ。それは昭和そのものにも見えるし、いまでも地方の旧道を走っていると、カーブを曲がった先にひょっと現れそうでもある。

photography
海女の群像
写真って、どう撮るかよりも、撮らせてもらえるまでにどう持っていくかの勝負なのかも、と思うことがよくある。親しくなって、いい顔をしてもらうとかじゃない。カメラを持った他人がその場にいることが、だれの気にもならなくなって、気配を消せるところまで持っていけたら、それはもう撮影の大半を終えたも同然、ということがよくある。このほど10年ぶりに再刊されたという『海女の群像』という写真集を見た。撮影者の岩瀬禎之さんは1904(明治37)年生まれ。すでに2001(平成13)年に97歳で亡くなられているが、千葉・御宿の地で江戸時代から続く地酒「岩の井」蔵元として酒造りに励みながら、長く地元の海女たちを写真に収めてきた。

photography
センター街のロードムービー
印画紙の上にあらわれ消える男女たち。それはいまから数年前、日本でいちばんスリリングな夜があった時代の渋谷センター街に、生きていた男の子と女の子たちだ。焦点の合った主人公と、その向こうのぼやけた街並み。鮮やかで、しかもしっとりしたカラー(それはウォン・カーウェイの撮影監督だったクリストファー・ドイルや、ベンダースやジム・ジャームッシュのロビー・ミューラーのような色彩感覚)。1枚1枚のプリントに閉じ込められた、なんとも言えない、あの時代の空気感。そしてこの素晴らしい写真を撮った鈴木信彦さんは、プロの写真家ではなく、仕事をしながら週末渋谷に通うだけのアマチュア・カメラマンなのだという・・。

photography
痛車賛歌――坂口トモユキのデジタル細密画
「いたしゃ」と言われて「イタ車」を連想するのか、「痛車」を連想するのか、君はどちらのタイプだろうか。痛車とは、ご存じ車体にアニメやゲームのキャラのイラストを貼りつけた、ヲタク活動の一環。以前は週末の秋葉原名物だったりしたが、最近では全国各地の街角で見かけることが少なくない。その痛車の名作群を2009年から撮影しつづけている、坂口トモユキさんの写真集『痛車Z』が12月6日に発売され、併せて中野ブロードウェイ内のギャラリーで写真展も今月末から開かれる。坂口トモユキさんは1969年生まれの写真家。東京近郊の住宅地を深夜に撮影して回った『HOME』を2008年に発表する。僕が坂口さんの名前を知ったのも、その年の木村伊兵衛賞審査会場で写真集を見たときだった。

photography
ブローニュの森の貴婦人たち――中田柾志の写真世界1
深い緑の森の夜、フラッシュに浮かび上がる挑発的な女。ビニールの花のごとく地面を覆う使用済みのコンドーム・・・。パリ、ブローニュの森にあらわれる娼婦たちの生態である。パリ市街の西側に広がるブローニュの森。凱旋門賞のロンシャン競馬場や、全仏オープンのロランギャロスも含むこの広大な森林公園が、昔から娼婦や男娼の巣窟としても有名だったことを知るひとも少なくないだろう。そういえばあの佐川一政が、死姦し食べ残した遺体を捨てようとしたのも、この森のなかだった。陽と陰がひとつの場所に、こんなふうに混在するのがまた、いかにもパリらしいというか。

photography
連載:スナックショット 13 長野2(平田順一)
寒中お見舞い申し上げます、どうも平田です。今年もぐっと胸にくるような街角、時空を超越したような酒場を求めて歩き回りますので、よろしくお付き合い願います。今回のスナックショットは長野県北信地方、15年前冬季オリンピックの舞台となった長野県の北部です。長野県は首都圏から割と近いわりに気候・風土が関東平野と異なるので、夏は避暑、冬はスキーやスノーボードで活況を呈しており、そのどちらにも縁がない自分も足繁く訪れている。

photography
阿片とオヤジと制服たち――中田柾志の写真世界2
先週に続いてお送りする写真家・中田柾志のストレンジ・ドキュメンタリー・ワールド。今週はラオス、キューバ、タイの3ヶ所でまとめられたシリーズをご紹介しよう。アルバイトで生活費を稼ぎながら、テーマを熟考しては旅に出る生活を繰り返してきた、43歳の知られざる写真家。そのエネルギッシュな視覚の冒険をお楽しみいただきたい。 なお、本稿は先週書いたように前後編にわけてお送りするはずだったが、あまりにも紹介したい作品が多いので! 次週もまた別のシリーズをお見せする予定、お楽しみに。

photography
隣人。―― 北朝鮮への旅
去年末、北朝鮮を撮影した写真集が出版された。タイトルは『隣人。――38度線の北』。撮影したのは初沢亜利(はつざわ・あり)という日本人のカメラマンだ。北朝鮮の写真と言われただけで、思い浮かぶイメージはいろいろあると思う。でもこの本の中にはボロボロの孤児も、こちらをにらみつける兵士も、胸をそらした金ファミリーの姿もない。 そもそも隠し撮りではなく、真っ正面から撮影されたイメージは、遊園地でデートする若いカップルであったり、卓球に興じる少年であったり、ファストフード店で働く女性や、海水浴場でバーベキューを楽しんだり、波間に寄り添う中年夫婦だったりする。言ってみればごくふつうの国の、ごくふつうの日常があるだけで、でもそれが他のあらゆる国でなく、「北朝鮮」という特別な国家のなかで撮影されたというだけで、この本は特別な重みをたたえている。

photography
可愛くて、やがて恐ろしき堕落部屋
今週あたり全国の書店に行き渡っているだろう、話題の写真集がある。先行販売している一部書店やネットでは、すでにかなり盛り上がっているその一冊は『堕落部屋』という。デビューしたてのアイドルだったり、アーティストの卵だったり、アルバイトだったりニートだったり・・・さまざまな境遇に暮らす、すごく可愛らしい女の子たちの、あんまり可愛らしくない部屋を50も集めた、キュートともホラーとも言える写真集だ。実はこの本、僕がオビを書かせてもらっている。ほかの文筆業の方々はどうなのかわからないが、僕にとって他人の本のオビを書くというのは、けっこうプレッシャーのかかる仕事で、ごく親しいひとの本以外はなるべく受けたくない。だから自分の本のオビも、かならず自分で書く。でも、この川本史織という若い写真家の作品集は、ゲラを見せてもらった時点で、なんとかキャッチーなオビを書いてあげたい、という気持ちになった。

photography
共犯者をさがして ―― 中田柾志の写真世界3
2週にわたってお送りしてきた中田柾志のビザール・ドキュメンタリー。最後になる今週は、2006年から現在まで続行中のプロジェクト「モデルします」をご紹介する。素人女性が応募してくるモデル募集サイトで探した女性たちを、中田さんはすでに数十名撮影してきた。その写真プリントと、応募してきた彼女たちの自己評価というか、自己アピールをセットにした作品群。プロのモデルのように美形でもなければ、スタイルも並みか、並み以下。そんな女の子たちが、自分を撮影モデルとして、会ったこともない人間にみずから売り込むという、それ自体がきわめて異常なシチュエーション。

photography
サーカスが街にいたころ
昨年12月5日配信号の『捨てる神と拾う神――森田一朗すてかんコレクション』をご記憶だろうか。それは昭和の時代の、無名の作者たちによる優れたストリート・デザインだったが、コレクションの主である森田一朗さんは、市井の人間を長く撮りつづけてきたドキュメンタリー・フォトグラファーである。品川区にある森田さんのご自宅には、ほんの少し前に過ぎ去ってしまった時代の日本人と、その生活の記憶が、膨大なネガとプリントになって保存されている。これから数回にわたって、その貴重なストックの一端を見せていただこうと思う。まず今週、来週はサーカスのお話から。

photography
サーカスが街にいたころ 2
先週に続いてお送りするドキュメンタリー・フォトグラファー、森田一朗さんのサーカス・コレクション。ご自宅に眠る膨大なコレクションから、先週紹介できなかったぶんを、森田さんご自身が『藝能東西』誌に寄稿した文章とあわせてご覧いただく。春になるとサーカスが街にやってきていた時代があった。モノクロームの画面から滲み出る、興奮と哀愁と自由の空気を胸いっぱいに吸い込んでいただきたい。

photography
刺青の陰影 1
先月から今月にかけて、052~053号で紹介した森田一朗・写真コレクション『サーカスが街にいたころ』。今週と来週はその続編として、森田さんの刺青写真コレクションをお見せする。森田さんが刺青を撮りはじめたのは1960年代。サーカスについて回り始めるより前のことだった――。“僕はね、ひとにどんどん近づいてって、話を聞くのが好きなんですよ。それであるとき、風呂屋に行って、隣にいたひとをぱっと見たら、素晴らし彫りものをしていてね。それで思わず「これ、水滸伝じゃないですか」って聞いたんです。『張順の浪切り』っていう図柄だったんだけど、本人はそれを知らなかったのね。それで「あんた詳しいな」ってことになって、仲良くなって家に遊びに行かせてもらったりしてたんです。

photography
刺青の陰影 2
052~053号で紹介した森田一朗・写真コレクション『サーカスが街にいたころ』。その続編として先週に引き続き、森田さんの刺青写真コレクションをお見せする。1966(昭和41)年に発表された写真集『刺青』(図譜新社刊、英語解説ドナルド・リチー)に掲載された写真群と、江戸下町の粋を体現するような、刺青愛好家の聞き書きをあわせてお楽しみいただきたい。今回ご紹介するのは、浮世絵摺師の北島ひで松さん。浅草生まれの浅草育ちで、日本一の浮世絵摺師と言われた人物だ。森田一朗さんは、北島ひで松さんのことをこんなふうに紹介している――

photography
海辺にて――デレク・ジャーマンへの旅
来週月曜(11日)まで、そのタカシマヤ美術画廊で開催されているのが『高橋恭司 “ブルーブルー” ―デレク・ジャーマンの庭―』という写真展だ。亡くなったのが1994年だから、もうすぐ没後20年になるデレク・ジャーマン。「映画監督・舞台デザイナー・作家・園芸家」などとウィキには書かれているが、みなさんにとってデレク・ジャーマンとは、どんな存在だったのだろう。最初から最後まで画面が青一色だった、あまりに異色な遺作『ブルー』を思い出すひともいるだろうし、かつて日本でも彼の庭園を紹介する本の翻訳版が出たことから、おしゃれな園芸家として知っているひともいるだろう。

photography
つくりもののまこと――『日本映画 スチル写真の美学』展によせて
「ハリスさんも死んだ、鶴さんも死んだ、今度はわたしの番なんだ・・」と絶唱するのはご存知『お吉物語』だが、先月末でシネパトスが死んで、5月末でテアトルシネマが死んで、銀座の映画館もどうなっちゃうんだろう・・・涙。そのテアトルシネマから首都高の下をくぐってすぐ、京橋のフィルムセンター(東京国立近代美術館フィルムセンター)は、銀座エリアに残された数少ない映画ファンの聖地である。過去の名作や埋もれた作品の上映はもちろん、展覧会もなかなかおもしろいフィルムセンター。先月末まで開催していた『西部劇(ウェスタン)の世界 ポスターで見る映画史 Part1』も楽しかったが、今月16日からは『映画より映画的! 日本映画 スチル写真の美学』と題された非常に珍しい、そして個人的に思い入れの深い展覧会がスタートする――。

photography
拳闘家と写真家――ふたりのファイターによせて
梅小路公園には去年、京都水族館がオープン。これまで京都市民には場末扱いされてきた下京区への、ひとの流れの変化を呼び起こしているが、先週土曜日にはこの京都水族館のすぐおとなりに、小さなギャラリーがひっそりオープンした。『trace』という名の、三角屋根の古い倉庫を改造したギャラリーは、写真家であり美術作家でもある山口和也が開いたもの。そのこけら落とし企画として5月12日までのほぼ1ヶ月間、山口さんが6年間にわたって撮影し続けてきたプロボクサー小松則幸の写真展を開催している。

photography
つくりもののまこと――伝説のスチルマン井本俊康さんに聞く
これまでほとんどまったく脚光を浴びることのなかったスチルマンをフィーチャーした、貴重な機会となる今回の展覧会。『Frozen Beauties 日本映画黄金時代のスティル・フォトグラフィ』(2000年、Asupect刊)に掲載した、僕のロビーカード・コレクションも展示されているが、今週は全盛期の日活で活躍したスチルマン・井本俊康(いもと・としやす)さんのお話を伺ってみよう。東京品川区の静かな住宅街に奥様とふたりで暮らす井本さんは、日活時代に石原裕次郎の作品だけで33本、吉永小百合を24本、会社を離れてフリーになり、引退するまで実に380本もの映画スチルを手がけた、伝説のカメラマンである――。

photography
梅佳代展オープン!
先週土曜日から初台の東京オペラシティ・アートギャラリーで始まった『UMEKAYO 梅佳代展』。すでにチェックしたというひともいるでしょう。これまでの彼女の展覧会の中でも最大規模の、そして現代日本のポップ・カルチャーにおける写真表現の最前線をあらわにする、絶対注目の大規模展覧会です――こんなこと言うと、生真面目なアート・フォトグラフィ信奉者に怒られそうですが。梅佳代についてはもう説明の必要がないと思うので、ここでは書きません。1981年に石川県で生まれ、2002年に大阪の日本写真映像専門学校を卒業。2006年に初写真集『うめめ』を発表して一躍注目を集め、翌年には木村伊兵衛写真賞を受賞(このときは僕が審査員でした)。それからの活躍はご存知のとおりです。

photography
一夜漬けの死体――川本健司の「よっぱらい天国」
新宿でも、渋谷でも池袋でもどこでもいい。東京の夜の街を初めて歩く外国人がいきなり度肝を抜かれるもの――それは道端に倒れている人間たちだ。あっちにもこっちにも、街路樹の根本にもビルの入口にも、ぐったりとからだを横たえて動かないひとたちがいる。それは人体というより、薄暗がりのなかの小さな障害物だ。ニューヨークだってロンドンだってパリだって、バンコクだってマニラだって道に倒れている人間はいっぱいいるが、東京の場合はそれがスーツ姿のサラリーマンだったり、ミニスカートの女子だったりする。で、事情を知らない外国人は「東京はなんてタフな場所だ!」と驚いたり、「死んでるんじゃないの?」とオロオロしたりするのだが、「いや、酔っぱらってるだけだよ」と聞かされて二度びっくり。「財布やカバンを盗られないのか!」「レイプされないのか!」と、こんどは「東京って、なんて安全な場所なんだ」と感心したりする。
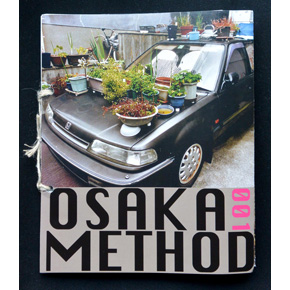
photography
ガラパゴス・シティ、大阪
昔は憧れて京都に住んでみたこともあるけれど、いまは仕事に行くにも、遊びで行くにも、京都より大阪のほうが百倍好きだったりする。一見、なんの変哲もない、なんの風情もない大阪の街を歩いていて、突然に出くわす人々や風景。そこには同じ日本でありながら、明らかに東京とも、京都とも、ほかのどこともちがう、大阪っぽいとしか言いようのないノリというか、グルーヴというか、そういう異質な空気感が確実にある。だから僕にとっての大阪のイメージは、ここだけがどこか別な方向への進化を辿っているとしか思えない、ガラパゴス的な印象の場所でもある。そういう大阪の空気をすごくうまく捉えている、若い写真家が谷本恵さんだ。
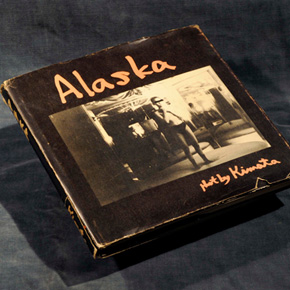
photography
笑う流れ者――アンダーグラウンド・フォトグラファー木股忠明の世界
仙台、新宿ゴールデン街、神奈川県綱島・・・同時多発的に小さな写真展が、ひっそりと開かれている。『笑う流れ者木股忠明の思いで』――ひっそりすぎて、そんな展覧会があることすら知らないひとがほとんどだろうし、木股忠明という写真家の名前も、よほど詳しいひとでないと聞いたことがないだろう。写真に詳しいひとですらなく、アンダーグラウンド・ミュージック・ワールドによほど詳しいひとでないかぎり。1970年代末期から80年代にかけて、日本の音楽業界がインディーズ・ブームというものに(ニューウェーブと呼ばれるようにもなったが)浮き立っていたころ、それとは一線を画した場所で、ずーっと小さくて暗い片隅で、ふつふつとうごめくエネルギーがあった。

photography
駅という名の広場があった――新宿駅と上野駅の写真集をめぐって
1969年、僕は中学生だった。テレビでは東大安田講堂の攻防戦がニュースで流れ、海の向こうではウッドストックに数十万人の若者が集い、19歳の永山則夫が米軍基地から盗んだピストルで4人を殺し、アームストロング船長たちが月面を散歩し、映画館には『真夜中のカウボーイ』や『イージーライダー』を観る列ができて、パチンコ屋からは『夜明けのスキャット』や『ブルー・ライト・ヨコハマ』や『人形の家』が流れていた年。そして1969年は駅が「広場」であることをやめ、「通路」になってしまった年でもあった。1969年の半年間ほど、毎週土曜夜の新宿駅西口地下は、数千人に及ぶ若者たちが集まって、身動きがとれないほどだった。ギターを抱えてフォークソングを歌う者たち。ヘルメットに拡声器で反戦と大学解体を叫ぶ者たち。ジグザグデモをくりかえす者たち。そこはまさに、毎週末に出現する祝祭空間であり、緊張と怒りに満ちた磁場でもあった。

photography
GABOMIという名の「そのまま」写真
長崎、広島、高松・・・路面電車の走っている街とは、たいてい気が合う。先々週のメルマガで紹介した、女木島の『女根』を取材に行ったときのこと。島から高松港に帰ってきて、市内をぶらぶらしてみようと、高松の路面電車「ことでん」の駅に歩いて行ったら、切符売り場の壁に異様なポスターが貼ってあった。仏生山温泉というらしい、檜造りの気持ちよさそうな大浴場に、ことでんの運転手さん、車掌さんたちが制服を着て、制帽もかぶって、白い手袋はめて、裸足で、風呂に浸かって遊んでいる。服をびしょびしょにして、湯けむりのなかで、気持ちよさそうに。

photography
写狂仙人の教え――福田満穂コレクション
先週木曜日には渋谷のギャラリー「アツコ・バルー」、そして日曜に山口湯田温泉からDOMMUNE「女将劇場生配信」で、偶然にも続けて山口県の知られざるアーティストの紹介をすることができた。渋谷で展示中の画家・田上允克、萩の仲村寿幸など、すでに本メルマガでインタビューを掲載したアーティストたちと並んで、特に反応が強かったのが、山口市在住のアマチュア・フォトグラファー福田満穂さん。あくまでストレートでありながら、どこかファニー、しかもビザール。見れば見るほど不思議な作風は、笑いの裏にひそむ乱調の美を感じさせてやまない。

photography
路上の神様 ――石倉徳弘のポートレイト・フォトグラフィ
たとえばダイアン・アーバスがフリーキーな被写体を通して、フリーキーな自分自身を撮影していたように、鬼海弘雄が浅草の人間模様のなかに自分のかけらを見つけようとしているように、優れたポートレイトは被写体を通して撮影者を浮かび上がらせずにおかない。そうでなければ、ポートレイトはただの顔かたちのサンプル集になってしまう。不思議なポートレイトのシリーズを見る機会があった。写っているのは似合わないスーツや改造制服に身を固めた少年だったり、見るからにオヤジでしかない女装家だったり、売れてなさそうなミュージシャンだったり、変な入れ墨の変な外人だったり、ホームレスだったり。

photography
優雅なファッションが最高の復讐である――ダニエル・タマーニとコンゴのサプール
イタリア人の写真家であるダニエル・タマーニは、もともと美術史を専攻していたが、数年前から写真の世界に身を投じ、当時住んでいたロンドンや、パリのアフリカ人コミュニティにとりわけ興味をもつようになった。2006年、もとはフランスが宗主国だったコンゴ共和国を旅した彼は、首都ブラザヴィルで、異様なまでにスタイリッシュに着飾った男たちと出会う。それはフランス語で「サプール(sapeur)」と呼ばれる、ヨーロッパ的なダンディズムを中央アフリカの地で体現した、ダニエルにとってまったく未知のグループだった。

photography
新連載! 隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 01(ケイタタ)
日下慶太さんという若い大阪人と会えたのは、偶然見たブログがきっかけだった。ちょうど大阪出張があったので、すぐに連絡を取って通天閣下で待ち合わせ。新世界市場というシャッター商店街にある、彼と友人たちのアジトでおしゃべりしているうちに、こんな連載を始めてもらうことになった。 彼のブログには、こんな自己紹介が載っている――大阪生まれ 大阪在住。 ロシアでスパイ容疑で拘束、アフガニスタンでタリバーンと自転車を二人乗りなど、世界をフラフラとしながら広告代理店に入社。コピーライターとして 勤務する傍ら、写真家、執筆家、セルフ祭顧問として活動をしている。

photography
隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 02(ケイタタ)
おっ、打ち切りにならずにすんだぜ『隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス』。これで読み切りじゃなくて正々堂々「連載」と言えるやん。第2回はつい先日が敬老の日だったということで老人特集でお送りします。

photography
隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 03 寝てる人 初秋編(ケイタタ)
今回は「寝てる人 初秋編」。このテーマ、実は連載のきっかけとなったものなのである。今夏に行なわれたFREEDOMMUNEに行った私は、自身のブログ「隙ある風景」で明け方に踊り疲れてあちこちで寝ている人の写真をアップしたところ(https://keitata.blogspot.jp/2013/07/blog-post_3409.html)、同じくFREEDOMMUNEに出演していた都築氏の目にとまることとなり「一度会いませんか」とTwitterにメッセージが来たのであった。「寝てる人」は都築さんのリクエストでもあった。さあ、満を持してお送りしよう。「寝てる人 初秋編」。コレクションは大量にあるので、初秋に撮ったものに限ってセレクトした。

photography
『張り込み日記』
「事実は小説より奇なり」という、言い古された格言の英語は「Truth is stranger than fiction」だが、ときとしてそれが「事実のほうがフィクションよりストレンジ」というより、「事実のほうがフィクションよりフィクシャス=フィクションっぽい」という意味ではないかと、思いたくなってしまうことがある。とりわけ、超一級のドキュメンタリー写真を眼にしたときには。『張り込み日記』という作品集は中年と若手、ふたりの男たちが街を歩きまわる写真で、すべてのページが構成されている。このふたりは刑事なのだ。

photography
鳥取発・昭和行き――池本喜巳、ふたつの写真展
1944年に鳥取市で生まれた池本さんは、大阪の写真学校で学んだあと、帰郷して写真の仕事に従事するかたわら、故・植田正治のアシスタントを20年間にわたって勤めてきた。今年が生誕100年となる植田正治の、写真家としての素顔をもっともよく知る人物のひとりでもある。この10月下旬から11月初めにかけて東京で、池本喜巳さんによるふたつの小さな写真展が開催される。ひとつは自身のシリーズ『そでふれあうも』(@元赤坂Niiyama's Gallery)、もうひとつは植田正治のポートレートを集めた『素顔の植田正治』(@下目黒Gallery Cosmos)。

photography
閉じかけた世界のなかへ
だれかがFacebookでシェアしてくれた1枚の画像があまりに美しかったので、写真集を探してAmazonには見つからなかったけれど、写真家本人のサイトで直販しているのを見つけ、すぐに注文のメールを書いてPayPalで代金を送金。そのまま出張に出かけ、数日後に帰宅したらもう、カリフォルニアから大きな包みが玄関に届いていた。『ECHOLILIA』(エコリリア)というその大判の写真集は、サンフランシスコ在住の写真家ティモシー・アーチボールドが、自閉症である息子イライジャーと向きあい、写真という手段でその閉ざされたこころとつながりあおうと試みた、果敢な挑戦と、ほとんどスピリチュアルな表現の記録である。

photography
隙ある風景 ロードサイダーズ・リミックス 05 ファッション(ケイタタ)
前回は「読書の秋・食欲の秋」がテーマでしたが、おっと何かを忘れていたじゃないか、そうだ、ファッションの秋だ、ということで今回は「ファッション」をテーマにお送りしよう。

photography
隙ある風景 ROADSIDERS' remix 06 寝てる人 晩秋編(ケイタタ)
今週は『寝てる人 晩秋編』。10月2日配信のvol.085にて『寝てる人 初秋篇』を書いたのだが、今回は『晩秋編』である。寝てる人の写真がたくさんありすぎて「秋1つ」では収まり切らないボリュームだったのである。正直に言おう、ネタ切れが怖いので2つに分けておきたかったという事情もないことはなかった。まあ能書きはこれぐらいにして『隙ある風景 晩秋編』。49枚寝ている人だけ。見ている間にあなたも眠ってしまうはず。

photography
ODO YAKUZA TOKYO――アントン・クスターズの歌舞伎町アンダーワールド
自費出版だというその写真集の噂を聞いたのは、2012年の初めごろだったと思う。Amazonなどの通販サイトには出まわらず、本人のウェブサイトから直接注文するしかないと知り、ベルギーの振込先にPayPalで送金、数週間後に届いたのが『ODO YAKUZA TOKYO』という大判の写真集だった。「ODO」とは「王道」のこと。そして「YAKUZA」と「TOKYO」はもちろん・・・これはベルギー人の若き写真家アントン・クスターズが新宿歌舞伎町で活動する、ある組の日常を撮影した写真集なのだ。「YAKUZA」という、とりわけ外国人にとってはもっともミステリアスな日本文化の一側面に深く寄り添いながら、あくまで客観的にその姿を捉えることに成功した、きわめて稀な作品である。

photography
隙ある風景 ROADSIDERS' remix 07 サラリーマン(ケイタタ)
今回のテーマは「サラリーマン」。日常の仕事の中で、そして、通勤途中でサラリーマンを見るたびに、サラリーマンというのはどこか違う生物のように感じてきました。それは街中でホームレスの人々を見たときに自分とは違う種族の人間だと思うような感覚と近いもの。今日はその隙あるサラリーマンの姿を写真と言葉で表現していきたいと思います。

photography
隙ある風景 ROADSIDERS' remix 08 2013年を振り返って(ケイタタ)
いよいよ年の瀬となりました。今年9月より始まった『隙ある風景』もみなさんのおかげで無事年を越せそうです。今回は、今年最後の記事ということで2013年を「隙」とともに振り返って行こうと思います。

photography
挟む女
いつまでたっても好きになれないセレブな街・広尾の通りに面して、新しくできた小さなギャラリー。ショウアン(Gallery Show-an)というその場所は、ガラスドアを開けるとなぜか、ぎょっとするほど大きなカリントウや、おいしそうなあんず大福を並べた和菓子屋で、壁の向こうがギャラリー空間。そのギャラリーで昨年末の6日間だけ、大福を買いに来たセレブ奥様が卒倒しそうな展覧会が開かれた。『ハサマレル男達』は、文字どおり「挟まれた男たち」。肌もあらわな太ももに顔をギューッと挟まれて、ぐちゃっと変形したところをアップで撮られた、もだえ顔の写真展なのだ。

photography
暴走の原点――『スペクター1974―1978』
ピンパブさすらいびとの比嘉健二さんは、暴走族文化を語る上で外すことのできないキーパースンでもある。『ナックルズ』をはじめとする若者系実話誌を生み出し、それ以前に僕も毎号欠かさず愛読していたレディース雑誌『ティーンズロード』の生みの親でもあった。その比嘉さんが10年以上の時間をかけて、昨年10月にようやく世に出した写真集がある。一般書店にはほとんど並んでいないので、知る人は少ないかもしれない。箱入り・上製本でずっしり重いその写真集は、『スペクター1974―1978』と名づけられている。言うまでもなく、日本暴走族文化の原点ともいうべき伝説のグループ「スペクター」を捉えた、奇跡的な写真集だ。

photography
隙ある風景 ROADSIDERS' remix 10 ノマド(ケイタタ)
今回のテーマは「ノマド」。そう、いま流行のノマドスタイルです。オフィスという場所に縛られずnomad=遊牧民のように自由に働く様をぜひご覧ください。

photography
はだかの領分――大崎映晋写真展
東京日本橋の裏通りに、書画用の特殊な和紙・大濱紙(おおはまし)を製造販売する小さな店『かみ屋』がある。その地下にあるギャラリー『KAMIYA ART』でひっそり開催されているのが『美しき海女――大崎映晋写真展』だ。大崎映晋(おおさき・えいしん)という名前に、どれくらいのひとがピンと来るだろうか。大崎さんは「水中写真家・水中考古学者・海女文化研究家」という肩書を持つ、日本における水中写真のパイオニア。1920(大正9)年生まれというから現在93歳という年齢で、いまも元気に活動を続けている。そして今回の写真展は、大崎さんがその生涯をかけて記録してきた海女たちの、いまではもう見ることのできない、裸の肌で海に生きてきた姿である。

photography
夜をスキャンせよ
レコード棚の前、ベッドの上、仕事場のMacに向かって・・・さまざまな場所で寛ぐ、よく見ると目だけが真っ白のひとびと。いや、よく見なくてもいきなり白目に目が行ってしまうのは、「目は口ほどに物を言う」からなのだろうか。そういえば前に会った歌舞伎町のデジタル写真館のオーナーは、ホストを撮るうえで最大のポイントは「目ぢから」だと言ってたっけ。そういう職業写真作法に対する、これは皮肉たっぷりのツッコミなのか・・・などと妄想をふくらませてしまうのが、1月15日配信号の後記で紹介した沼田学の写真展『界面をなぞる2』だった(~1月22日まで@新宿眼科画廊)。

photography
『そこへゆけ』――ストリートスケープのねじれ
2013年10月9日配信号で紹介した渡部雄吉の『張り込み日記』は、去年紹介したうちで、もっとも反響の大きかった写真集のひとつだった。発行元となったROSHIN BOOKSは斉藤篤という写真好きの青年によって、「この本を世に出したいために」設立されたマイクロ・パブリッシャーだったが、幸いにも『張り込み日記』は噂が噂を呼んで程なく完売――悔し涙にくれたひとも多いかと思うが、この4月1日に第2版が発売されるそう! 急いで予約すべし。そのROSHIN BOOKSが満を持して2月に発表したばかりの2冊めのプロジェクトが『そこへゆけ』。『張り込み日記』の渡部雄吉は大正生まれ、1993年に亡くなっている歴史上の写真家だが、『そこへゆけ』の作者・佐久間元(さくま・げん)はまだ34歳という若手。これが初の写真集という、意表を突いた展開である。

photography
私をデートにつれてって――櫻井龍太と陽性のエロ
オフ会当日に櫻井くんを紹介されたとき、説明されたのが「この子、オッパイ写真家やから」。なんでも友達や恋人のオッパイをいろんな場所で撮影したシリーズが秀逸だそうで、それは見たいじゃないですか! というわけでケイタタさんは急いで写真展を企画、僕はメルマガでインタビューさせてもらった。1983年生まれ、5月29日で31歳になるという櫻井龍太は、「10代のころから女性の裸を撮りつづけてきた」という、筋金入りのヌード・フォトグラファーだった。

photography
移動祝祭車 ――沈昭良の『SINGERS & STAGES』
台湾の写真家・沈昭良(シェン・ジャオリャン)の『STAGE』シリーズを最初に見たのは、2006年新宿のPLACE Mギャラリーだったと思う。1968年台南市生まれ、新聞社で働いたあとフリーの写真家となり、日本工学院で学んだ経歴もあって日本語は完璧。そして本人いわく「時代遅れのドキュメンタリー・フォトグラファー」である沈昭良は、台湾各地の庶民の暮らしに密着した写真を長いあいだ撮りつづけてきた。冠婚葬祭や催し物の場所で、荷台が開けばステージに変身する、「ステージ・トラック」を舞台として繰り広げられる移動ショー劇団。それを台湾では「台湾綜芸団(タイワニーズ・キャバレー)」と呼ぶそうだが、2010年ニコンサロンでの展覧会に続いて、2011年末に出版された彼の写真集『STAGE』については、本メルマガの2012年5月23日号(020)でも紹介している。

photography
情色情――タイワニーズ・エロチカ
沈昭良に続いて、今週はもうひとつ台湾から写真の話題をお伝えしたい。台北に親しんでいる旅行者なら、華山1914文創園区という場所をご存知だろうか。「台北の秋葉原」と呼ばれる光華商圏のそばにある華山1914文創園区は、もともと1914(大正3)年、日本の台湾統治時代に建設された清酒工場「芳醸社」が、戦後台湾の専売公社として清酒、梅酒の製造を行ってきたあと、1987年に閉鎖。長らく廃墟化していたところに、アーティストや演劇人たちが注目するようになって、活動場所として活用されるようになった。

photography
抗体――アントワーヌ・ダガタ
最初に見た瞬間――多くのひとがそう思うだろうが――これってカメラで描いたフランシス・ベーコンじゃないか!と僕も思った。ブレというのは写真家にとっていつも魅力的な要素だが、これだけシャープにブレをエネルギーの表現につなげている写真家って、いまいるだろうか。いま渋谷で開催されている『アントワーヌ・ダガタ 抗体(Anticorps)』は、今年もっとも重要な写真展のひとつになるはずだが、それにしてはメディアの無関心さが目立つ。

photography
カーブサイドの誘惑
「なかなかない珍しいもの」よりも、「ありすぎて見えないもの」や「ありふれてバカにされているもの」に目を向けていきたいという思いが高まったのは、いまから十数年前のことで、それはやはり珍日本紀行で日本の田舎を何年間も走り回った影響だったのかもしれないが、その思いが募って出版にこぎつけたのが『ストリート・デザイン・ファイル』という、全20巻のデザイン・ブックだった。20巻の中にはラブホテル、大阪万博、暴走族の単車、デコトラ、メキシコのプロレス仮面、中国の文革グッズなど、世界各地でバカにされていた日常のデザインが詰め込まれていたが、そのなかでもひときわ、現地のインテリに徹頭徹尾バカにされていて、個人的には大好きな一冊に仕上がったのが『The German Soul 小人の国』という、ドイツの庶民に絶大な人気を持つ焼物の小人たち――白雪姫と七人の小人の、あの森の小人――を探し歩いた写真集だった。

photography
5000人の花嫁花婿――統一教会・合同結婚式写真集
「統一教会」という言葉に、みなさんはどんなイメージを想起するだろう。原理研究会、霊感商法、マインドコントロール・・・いかがわしい新宗教の代表的存在、という受け止め方がほとんどではないか。1992年に桜田淳子が合同結婚式に参加したことから、一時はかなりマスコミを賑わわせたが、このところほとんど目にすることはなかった。おととし2012年には教祖の文鮮明が亡くなっているのだが、それもたいして報道されずに終わった気がする。そのいっぽうで最近、書店には並ばないかたちで2冊の「統一教会写真集」が、実は東京の出版社から発行されているのをご存知だろうか。ひとつは2012年9月15日に執り行われた文鮮明の葬儀の模様を収めた『慟哭』(写真:酒井透、大洋図書刊、2013年)であり、今回紹介するもう一冊がこの7月に出版されたばかりの『WORLD WIDE WEDDING』。こちらは今年2月に挙行された合同結婚式の模様を、ふたりのカメラマンが捉えたA4版上製本の豪華写真集だ。

photography
新宿砂漠
渡辺眸(わたなべ・ひとみ)という写真家をご存知だろうか。1942年東京生まれ。70年代からインド、ネパールへの度重なる旅を記録した、数冊の写真集で知られるようになったベテラン・フォトジャーナリストだが、ちょっとちがうジャンルで脚光を浴びたのが2007年に新潮社から発売された『東大全共闘1968-1969』だった。あの安田講堂がバリケード封鎖されていたとき、たまたま友達の彼が東大全共闘代表の山本義隆だったことで、着替えを届けに行く彼女についていき、そのままバリケード内に籠城。外側からの報道写真ではなくバリケードの中から、闘争の内側からの唯一の記録が、渡辺さんによって撮影されることになった。その渡辺眸さんが当時撮影した、こちらは新宿の街頭の記録『1968新宿』がこのほど発売(街から舎刊)、いま新宿ニコンサロンで展覧会を開催中だ(8日まで、このあと大阪に巡回)。

photography
モノクロームの伝説
日本海に面した鳥取県の小さな町・赤崎(現・琴浦町)。8月20日配信号の編集後記で、海に面して約2万の墓が並ぶ花見潟墓地の幻想的なお盆の風景を紹介したばかり。その赤崎を訪れた目的が、今年4月末に開館した『塩谷定好写真記念館』だった。鳥取で写真、となると自動的に植田正治の名前が出てくる。植田正治はすでに米子近くの伯耆町に立派な美術館があり、訪れたことのあるひとも多いだろう。一般にはあまり馴染みのない名前かもしれないが、塩谷定好(しおたに・ていこう)は「植田正治の先輩」として山陰の写真界では古くから知られてきた、伝説のアマチュア写真家である。

photography
浅草サンバカーニバル 2014 前編
いまから2年前、2012年6月13日配信号で「山谷に生きる男たち」のポートレートを見せてくれた、多田裕美子という写真家がいる。浅草生まれの浅草育ち、いまも浅草で暮らし、働き、毎晩飲んでる多田さんも、やっぱりサンバカーニバルにはほとんど興味がなかったそうだが、なんと今年オフィシャル・カメラマンを依頼されて、「どうだった?」と聞いてみたら、「それが、予想外におもしろくて!」と興奮気味。そこで今週と来週、内側から見た浅草サンバカーニバルをリポートしてもらうことにした。毎年、完全にワンパターンの報道でしか僕らが知ることのなかった浅草サンバカーニバル。露出度マックスのお姉ちゃんたちが踊りまくるだけ、という一般常識をはるかに超えて、「本場ブラジル」のコピーにとどまらない、独自の進化をいまや遂げつつあることに僕も、みなさんの多くも驚くはずだ。

photography
浅草サンバカーニバル 2014 後編
先週に続いてお送りする、内側から覗いた浅草サンバ物語。先週の写真で、ブラジルとはまたちがう独自の進化(深化)を遂げつつある、浅草サンバの熱量を感じ取っていただけたろうか。今週はそんな浅草サンバを生み出した立役者のひとり、いかにも浅草的な生き様を教えてくれるオトコ、モロハシさんをご紹介する。

photography
ポルノ映画館の片隅で——エンヴァー・ハーシュのレーパーバーン
今年6月18日配信号で、『カーブサイドの誘惑』と題した記事をお送りした。それはバンコクの路上で見つけた、壊れてパイプだけになった椅子とか、ビールケースに棒を挿しただけの「駐車禁止」サインとか、「美」や「伝統」のカケラもない、しかしある種の美しさにあふれたオブジェのコレクションだった。それを撮ったのがハンブルク在住のエンヴァー・ハーシュという写真家だ。1969年ハンブルク生まれ、イギリスのアートスクールで学んだあと、ずっとハンブルクを拠点に活動を続けている、生粋のハンブルクっ子であるエンヴァーは、学生のころからもちろんレーパーバーンに出入りしていて、「クラブとかライブハウスとか、ビール飲んだりとか・・・とにかくよく来てたよ」。

photography
浅草スモーキン・ブギ
先月末から2回にわたって「浅草サンバカーニバル」をリポートしてくれた、浅草のオフィシャル・フォトグラファー多田裕美子さん。本場リオとはまたちがう、ガラパゴス的進化を遂げつつあるカーニバルの実態に、びっくりしたひとも多いのでは。その多田さんが、「タバコを吸うひと」をテーマに撮りためた写真展を、やっぱり浅草で開くことになった。僕の住んでいる東京千代田区では、もう路上でタバコを吸っただけで罰せられるようになったくらい、いまや喫煙者は社会の害悪あつかいだ。そう考えるとタバコを吸うひとたちもまた、いつか消えゆくマイノリティなのかもしれない。タバコの煙のように・・・。

photography
金子山の風景
大手出版社が軒並み出展する東京国際ブックフェアが年々先細りで、自費出版・ジンが中心の東京アートブックフェアが年々拡大中という、わかりやすい変化のただ中にある日本の出版界。僕のところにも毎月いろいろな自費出版のお知らせが来て、うれしくもあり焦りもしという状態だ。今週は対照的な、でもどちらも熱い2冊の手作り写真集を紹介する。まずお見せするのは「金子山」という、いちど聞いたら忘れられないヘンな名前の写真家が発表した『喰寝』——これで「くっちゃね」と読ませる。サイズは文庫版、しかし548ページ! 厚さ5センチ近くという、僕の文庫よりヘヴィで(笑)、しかもオールカラー。初版500部で、価格3500円・・・売り切れても赤字なのでは? 完全に収支計算間違ってる気がする。

photography
浴槽というモノリス
ご承知のとおり僕はよくトークをやるけれど、それはなにも人前で話すのが好きとかではなくて(ほんとに!)、トークの場でいろんなひとと知り合えるから。終わったあとに「うちのそばにもこんな場所がある、こんなひとがいる」と教えてくれたり、「こんな絵を描いてるんです、写真を撮ってるんです」と作品を見せてもらえることがたくさんあり、それはネットよりもずっと貴重な情報やアドバイスになってくれる。牧ヒデアキという写真家とも、そうやって知り合った。牧さんは1971年生まれ。三河湾に面した愛知県西尾市で、建築設計の仕事をしながら、ずっと写真を撮っている。あるトークのあとで分厚いアルバムを見せてもらったのだが、そこには路傍に打ち捨てられたポリやステンレスの浴槽ばかりが写っていた。

photography
リリックとしてのポートレート——石川竜一写真展のために
絵や写真を見てくれ、と訪ねてきてくれるひとはずいぶんいる。いい、悪いなんて決められないし、大したアドバイスもできない。「がんばって続けてください」ぐらいしか言えることはないけれど、ただひとつ確かなのは「ものすごくたくさん持ってくるひとに、おもしろくないのはない」という経験則だ。ある日、沖縄から来たという青年が戸口に立っていた。すらっとした長身、端正な顔立ち。赤い革ジャンにシベリアに行くみたいな帽子を被って、露出計付きのいかついハッセルブラッドを首から下げて、ものすごく大きなリュックを背負っている。招き入れると席につくまもなく、テーブルにどさどさと分厚いポートフォリオを積み上げて、「見てください」とつぶやき、あとは黙ってこっちをじっと見ていた。

photography
陽性のエロティシズム・フォトグラフィ
11月のパリといえば、「パリ写真月間」の季節でもある。ひと月でおよそ100もの写真関連展示が開かれるというが、とりわけ毎年グランパレで開催される『パリ・フォト』(今年は11月13〜16日)の期間には、世界中から写真関係者、キュレイター、ギャラリストが集う。その週にあわせて多くの展覧会が集中するが、ルーブル地下のカルーセル・デュ・ルーブルで開かれた「フォトフィーヴァー・パリ 2014」に出展した作家のひとりが、フレデリック・フォントノワ。1963年パリに生まれ、いまもパリで制作を続ける、写真とビデオにまたがる映像作家である。少し前から作品を紹介する機会を待っていたのだが、オルセーの『サド』展と奇妙にリンクする部分もあり、今回続けて、飛幡祐規さんにインタビューをお願いして掲載することにした。

photography
東京のマルコビッチの穴
不思議な写真を見た。息づまる、というより、ほんとうに息が詰まるような狭苦しい空間が、ずっと先まで伸びていて、それはどこに続くのか、それともどこにも着かないのか・・・。見るものすべてを閉所恐怖症に追い込むような、それでいて難解なSF映画のように異様な美しさが滲み出るそれは、ビルの内部を走るダクトの内部を撮影したものだという。木原悠介は1977(昭和52)年生まれ、36歳の新しい写真家だ。中野区新井薬師の、潰れた写真屋を改造した「スタジオ35分」という小さなギャラリーで、今年8月末から9月初めの9日間だけ開かれた『DUST FOCUS』が、人生初めての個展だった。

photography
夜のコンクリート・ジャングル
公園の遊具にこころ惹かれるオトナはけっこういる。「タコ公園」とか「クジラ公園」とか、遊具の名前で通称される公園も少なくない。平日の午後、あるいは深夜に酔って帰る道すがら、ふと目にする、ひと気のない公園にうずくまるコンクリートの巨大な物体。かすかな哀愁と不気味さを漂わせながら、ただそこにあるなにか。それをずっと撮り続けているのが木藤富士夫(きとう・ふじお)だ。木藤さんの写真を最初に見たのは、けっこう前だったと思うが、それは絶滅危惧種となりつつあるデパートなどの屋上遊園地を撮影したシリーズだった。小さな自費出版の写真集に収められたそれらは、よくある廃墟写真とはちがって、まだ営業中なのにもかかわらず、ごく近い将来の廃園を予感させるような諦観が漂っていた。単なる昭和ノスタルジーとはひと味違う、明るいディストピアのようなニュアンスが画面に滲んでいた。

photography
からだとからだと写真の関係
(前略)偏狭なこころの病気がこの国の一部をむしばみつつあるいっぽうで、いまアート・ワールドでは若い中国人アーティストたちの勢いが止まらない。現代美術の最前線でもそうだし、写真の世界でもそれは同じだ。以前にもちょっと触れた東京のアートブック・フェアで、刺青にボディピアスばりばりの女性がひとりで座っているブースがあった。聞けば台湾からの参加だという彼女が、ずらりと並べたアート・ジンのなかで、これはすごいですよと教えてくれたのが、『SON AND BITCH』と題された箱入りの写真集だった。中を開いてみると、日本のアートっぽい写真どころではないハードコアなポートレートが満載。そして作者の任航(Ren Hang=レン・ハン)はここ数年、世界各地のグループ展でその作品をよく目にする、注目の若手写真家なのだった。
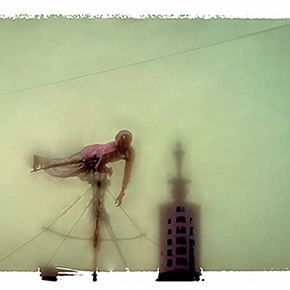
photography
曲芸のタブロー——芦沢武仁の辺境写真紀行 01
自主運営ギャラリーは東京では、僕の遊び場である四谷3丁目〜新宿2丁目あたりに密集しているので、よく足を運ぶけれど、このメルマガを始めるようになってから、意外な発見があるのは、むしろメーカー・ギャラリーのほうが多かったりもする。富士山、高山植物、蒸気機関車、子供、祭り・・・あいかわらずのカメラおやじネタも多いが、ときに目を見張る高純度の作品が隠れていたりもする。年配の常連客ばかりに独占させておくには惜しすぎる、貴重な出会いが待っていたりもする。今年の9月3日号では渡辺眸の写真展『1968 新宿』を紹介したが、同じ新宿ニコンサロンでこの9月末から10月中旬にかけて開かれたのが芦沢武仁(あしざわ・たけひと)による『曲芸のタブロー』だった。

photography
家の記憶——芦沢武仁の辺境写真紀行 02(写真・文:芦沢武仁)
世界の辺境を旅する写真家・芦沢武仁の短期集中連載・第2話。先々週のインドの旅芸人たちのルポルタージュに続き、今週はルーマニア・マラムレシュの暮らしをご紹介する。ウクライナと国境を接するルーマニア北部のトランシルヴァニア地方マラムレシュは、世界遺産に登録された木造聖堂群で知られる、豊かな伝統に支えられた美しいエリア。時間の止まったような村々を訪ね歩くうちに、人々の暮らしに魅せられた芦沢さんは、2009年から11年まで3度にわたってマラムレシュを訪れることになった・・・。

photography
写ルンです革命
先月紹介して好評を得た、木原悠介によるダクト内部写真。あれがすべて「写ルンです」で撮影されたことを、ご記憶だろうか。1986年に富士フィルムが発売した「写ルンです」は、誕生からもうすぐ30年。デジカメ、携帯全盛期の現在でも富士をはじめ、いくつかのメーカーから「レンズ付きフィルム」として販売されている。いまから30年後のデジカメがどうなってるかなんて、想像できるだろうか。USBもSDカードもそのころにはとうに消滅して、常に新しい媒体に移し続けないかぎり、30年前(つまり現在)の写真は見ることすらできないはずだ。レンズ付きフィルムはまた、世界でいちばんタフなカメラでもある。電池も充電も必要としない。モーターのような駆動系も電子回路も組み込まれていないから、どんな場所でもとにかくシャッターを押せば「写ルンです」。

photography
昭和の終わりの新宿で
せっかく南新宿のことを書いたので、新宿の話題をもうひとつ。去年3月19日号で、『新宿が生きていたころ——昭和40年代新宿写真展』という展覧会の紹介記事を掲載した。新宿歴史博物館で開かれたこの写真展は、新宿がたぶんいちばんエネルギッシュだった時代を、豊富な写真コレクションでたどる、地味だけれど貴重な企画だった。その新宿歴史館でいま、前回の続編となる『写真展 新宿50−60年代<昭和>の終わりの新宿風景』と題された展覧会が開催中だ(2月22日まで)。

photography
ダンシングベアー——芦沢武仁の辺境写真紀行 03(写真・文:芦沢武仁)
世界の辺境を旅する写真家・芦沢武仁の短期集中連載、最終回となる第3話ではトルコとブルガリアから、熊遣いのルポルタージュをお送りする。いまから30年近くも前に、イスタンブールで出会った熊遣いに魅せられた芦沢さんは、それから6回にわたって、消えゆく大道芸を追いかける旅に出るのだった・・・。

photography
新宿でロックと白目の写真展!
いま新宿でふたつの楽しい写真展が開催中だ。まずひとつめは新宿ビームス6階のBギャラリーで開かれている、『MUSIC LIFE PHOTO EXHIBITION〜長谷部宏の写真で綴る洋楽ロックの肖像〜』展。『ミュージックライフ』といえばオールド・ロック・ファンは涙なしに語れない、ロック創成期から続いてきた音楽誌。1951年にスタートして、惜しくも1998年に休刊してしまったが、2011年からは『MUSIC LIFE plus』というKindle版の電子雑誌として復活。値段の200円ちょっととお手頃なので、興味あるかたはAmazonのサイトで「ミュージックライフ」と検索してみてほしい。で、今回の写真展は、そのミュージックライフ誌の専属カメラマンを長く勤めた長谷部宏さんによる、ロック史をいろどる貴重なショットを一同に展示したもの

photography
シンパシー・フォア・ザ・デッド——倉谷卓の写真について
先月(1月21日号)に倉谷卓写真展『Ghost’s Drive』の告知記事を掲載したのを、気づいていただけたろうか。会場となった日本橋茅場町の森岡書店は小さな展示スペースだったが、山形県内のユーモラスなお盆の風習を記録したシリーズはすごく興味深かった。『Ghost’s Drive』展とほぼ同時期に京橋の72ギャラリーでも、『カーテンを開けて』と題された別の写真展が開かれていることを知って、そちらにも足を伸ばし、本人とお話することができた(1月21日〜2月1日まで開催)。

photography
駅もれ考現学(写真・文:萩原幸也)
「駅もれ」という言葉をご存知だろうか。駅で漏れるから「駅もれ」。駅構内で漏水が起きているときに、急場しのぎとしてビニールやホースなどで漏水を床やバケツに誘導する、その対処法を「駅もれ」と言うのである。日本中でこの「駅もれ」という言葉が通用しているわけではない。駅構内での漏水だけに、まず駅があって、それも多くの利用者がいる駅であって、さらに地下駅のほうが漏水は多いので地下鉄や地下駅があるところ=クルマ社会の田舎ではなく都会にしか、「駅もれ」は見ることができない。しかも、それは見られるためのものではない。むしろ駅の関係者にとっては見られたくないお漏らし、それが「駅もれ」である。

photography
自然が超自然になるとき――遠藤湖舟写真展によせて
身近に見つけた美しい自然の表情、動植物や天体、そして作品集の帯文は平山郁夫・・・このメルマガともっとも相性が悪い(笑)写真の数々が、目の前に開かれている。今月末から日本橋高島屋で写真展を開く、遠藤湖舟の作品だ。いわゆる「美しい風景」にこころ惹かれないのはなぜだろうと、ときどき考える。写真としてだけではなく、その場に立つことを含めて。夕陽に輝く富士山を眺めても、夜のグランドキャニオンで星々に包まれても、オレゴンの森深くで緑の濃さに窒息しそうになっても、ハワイの海にぷかぷか浮きながらコバルトブルーの空を眺めても。あ〜きれいだな〜とは思うけれど、5分で飽きてしまう。カメラを向けることも、ほとんどない。

photography
テンダーロインをレアで
あれは鞆の津ミュージアムが開館したときだったから2012年、いまから3年前のことだ。展覧会に参加した縁でトークに招かれて、終わった後に参加してくれたひとたちとおしゃべりしていたとき、ちょっと・・・ではなくて、いかにも一癖ありそうな革ジャン姿の青年が近寄ってきて、僕に聞いた――「都築さん、サンフランシスコのリサーチって知ってますか」? リサーチ=『RE/Search』は1980年代から90年代にかけてサンフランシスコで発行されてきた、元祖オルタナティブ・マガジンで、その後のZINEをはじめとする世界のオルタナ系出版に決定的な影響を与えた、最重要雑誌である。もちろん、僕も含めて。その『RE/Search』という名前が、こんな場所で、こんな若い日本人の口から出るなんて・・・一瞬、30年前にぐいっと引き戻されたような、目眩に近い感覚に襲われた。弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)は鞆津のある福山に暮らす若い写真家。

photography
地べたからパリを眺めてみれば
おもしろそうな展覧会があると聞けば、どこへでも走っていきたいが、さすがにニューヨークやパリやロンドンに「じゃあ明日行ってきます」というわけにはいかなくて、悔しい思いが日々募る。先月もパリでものすごく興味深い写真展があるのを知って悶絶、本メルマガで去年オルセー美術館のサド展などを取材していただいた、パリ在住の作家・飛幡祐規(たかはたゆうき)さんにさっそくリポートをお願いした。パリ市庁舎の建物を囲む柵をギャラリー代わりに、つまり屋外で開催されたこの展覧会は、パリのホームレスたちが撮影した作品を集めた写真展なのだ。

photography
近世店屋考、ふたたび
いまから3年ほど前、鳥取市の図書館で僕は『近世店屋考』というモノクロームの写真集に出会い、その一冊が池本喜巳(いけもと・よしみ)さんへと導いてくれた。本メルマガの2012年9月12日号で特集した『近世店屋考』は、山陰地方の片隅に隠れるように生きてきた昔ながらの商店を撮影した、派手さのかけらもない写真集だったが、予想外の反響をもらい、スタートからまだ半年ちょっとだったメルマガ制作に大きな励ましを得た。それから鳥取に行くたびに池本さんは僕にこの、日本有数に地味な、でも日本有数に暮らしやすい地方のことを教えてくれた。「店屋考はまだ撮ってるんだよ」と会うたびに言いながら、池本さんはなかなかその成果を見せてくれなかったのだったが、今月20日から銀座ニコンサロン、そのあと大阪ニコンサロンで、その『近世店屋考』の新成果が披露される。

photography
サラの魔法
1970年代、写真界のスターといえば、それはいまのようなアート・フォトグラファーではなく、疑いもなくファッション・フォトグラファーだった。デザイン界のスターがファッション・デザイナーであり、グラフィック界のスターがアーティストでなくイラストレーターで、メディア界のスターがファッション・マガジンであったのと同じように。そういうキラ星のようなファッション・フォトグラファーのなかで、アヴェドンやヘルムート・ニュートンのような評価を、少なくとも80年代後半以降の日本では受けることがなかったが、70年代当時にコアなファッション業界人からオシャレ少年少女まで、もっとも熱狂的な人気を誇ったのは、実はサラ・ムーンだったのではないか。

photography
雑種のしあわせ――佐々木まことの動物写真
『ジワジワ来る関西奇行』で毎回、「こんな関西もありか!」と驚かせてくれる吉村智樹さん。ずいぶん前からの知り合いだが、連載をお願いすることになって久しぶりに話しているうちに出てきた名前が「佐々木まこと」という動物写真家だった。佐々木さんは写真集『ぼく、となりのわんこ。』を、吉村さんが編集を担当して2005年に発表しているのだが、いまは古本を探すしかないし、早く2冊めをつくりたいけれど、「なかなか進まないんですよ~」と苦笑。最近は写真集も難しいしねと相槌を打ったら、「そうじゃなくて、粗選びして渡してくれと佐々木さんに言ってるんですが、ぜんぜん送ってこなくて」という。訳を聞いてみたら、「犬猫写真だけで100万カット以上あるので、そこから100枚とかチョイスするのが大変すぎるらしくて」と言われて絶句。1万枚に1枚か・・・(笑)。いったいどんな写真家なんだろうと、堺市のご自宅を訪ねてみた。

photography
北京銀山
いま発売中の写真雑誌『IMA』では「ドキュメンタリーの新境地」という特集が組まれているが、その中で僕も北京在住のフランス人、トーマス・サルヴィンの作品群を紹介してる。といってもサルヴィンは写真家ではなく、リサーチャーでありコレクターでもある。彼があるとき、北京で行き当たった膨大なネガの山から発掘されたイメージの集成、それがサルヴィンの写真集『Beijing Silvermine=北京銀山』なのだ。いつもなら告知コーナーでお知らせするのだが、サルヴィンが掬い上げたイメージがとても興味深いので、ここで記事としてほんの一部分を、文章の抜粋とともに紹介したい。興味を持ってくれたら、『IMA』にはもっと多くの図版が掲載されているので、ぜひご一読を。

photography
湯けむりの彼岸に――『雲隠れ温泉行』と村上仁一の写真
温泉が好きで、日本はもとより外国の温泉にもずいぶん入ってきたが、日本の田舎の、どうってことない温泉場に漂う独特の「彼岸感」は、ほかの国にはなかなか見つからない。いくらおしゃれな建築にしようが高級エステや豪華料理を入れようが、そんなことで真の「非日常」を演出できはしない。非日常はすぐそこに、日常のすぐ裏側にびたっとくっついているものだから。・・・そんなことを思い浮かべながら村上仁一の『雲隠れ温泉行』を2007年に初めて見て、最初はそれが現代の、若手写真家による作品とは信じられなかった。荒れたモノクロの画面は1960年代のコンポラ写真のようでもあり、ときに戦前のアマチュア写真家の作品のようでもあり、しかしそれが弱冠30歳の写真家であるという事実。それは本人の、というよりも日本の温泉が、どんなに近代化されようが拭い落とすことのできない、時代を超越した「彼岸感」にまみれたままであることを、確信させてくれるのでもあった。

photography
踊る水中花
池谷友秀という写真家がいる。「水中写真家」ではないけれど、人間のからだと水を組み合わせた、というより溶け合わせた写真をずっと撮っていて、その最新写真展がいま銀座ヴァニラ画廊で開催中だ(7月18日まで)。もちろん、その作品はバンコクのゲイお魚ショーなんかよりはるかに美しい。こんな書き出しをして申し訳なかったが、水というのは不思議な視覚効果があって、人間を地上とはまた別の生きものとして見せてくれる気がする。水中で光が屈折するように、常識にとらわれていた僕たちの見方をも、水は微妙に屈折させてくれるようなのだ。今回展示されている「BREATH」「MOON」というふたつのシリーズは、いずれも水中や水面上で撮影された、おもに裸の人体である。モデルは美少女だったり暗黒舞踏家だったり、身体障害者だったりするのだが、地上で見ればほとんどまったく異質なはずの人間たちが、水中で浮遊したり泡に包まれているうちに、深い部分でひとつに結ばれた存在であるように見えてくる。

photography
写真の寝場所
早稲田大学キャンパスを取り巻く牛込から西早稲田周辺には、東京都心部のエアポケット的な空気感がある。たいした再開発が進行中なわけでもなく、昔からの家並みや入り組んだ細い道が残っていて、都心部なのに交通の便がそれほどよくないことも関係しているのだろうが、やや取り残された感が漂う。それが独特の居心地良さにつながっている。路地の奥、迷路のような住宅街のなかに、2階建ての銭湯がある。松の湯、昔から早稲田の学生に愛されてきた銭湯だ。1階はいまも盛業中だが、2階はすでに営業終了、銭湯の造作を残したまま、ギャラリー・スペースとして活用されている。そこで6月の1週間、開催されていたのが大阪の写真家・赤鹿麻耶による『ぴょんぴょんプロジェクト vo.1「Did you sleep well?」』という奇妙なタイトルの、奇妙な展覧会だった。

photography
林忠彦の戦後
林忠彦といえば、瞬間的に頭に浮かぶのは銀座の酒場でご機嫌の太宰治だったり、汚部屋で原稿用紙に向かう坂口安吾だったりする。その林忠彦が1955年にアメリカを訪れ、大量のスナップ写真を残していたことを、今回初めて知った。7月31日に出版されたばかりの写真集『AMERICA 1955』がそれで、品川のキャノンギャラリーではそのプリントと、林忠彦の代表作のひとつである『カストリ時代』のシリーズを並置した、興味深い構成の展覧会が開催中だ。

photography
佐世保の夜の女と男――松尾修『誰かのアイドル』
見るだけで行った気になる写真と、見てるうちに行きたくてたまらなくなる写真がある。この6月に発表されたばかりの写真集『誰かのアイドル』をAmazon経由で手に入れて(自主制作なのでウェブか限られた書店でしか手に入らない)、僕は眼を見張るというより腰が浮く思いで、ウズウズを抑えかねた。『誰かのアイドル』は佐世保出身の写真家・松尾修が個人で進める「サセボプロジェクト」の、2冊めとなる出版物。去年(2014)11月には『坂道とクレーン』と名づけられたタブロイド式の写真集を、1冊めに発表している。

photography
写真のマジック・リアリズム――『ブッシュ・オブ・ゴースツ』を見て
フライヤーを壁に貼っておいても、グーグルカレンダーに書き込んでおいても、なかなか気になる展覧会ぜんぶには行ききれない。この11月8日で終わってしまうクリスティーナ・デ・ミデルの写真展『ブッシュ・オブ・ゴースツ』も、ほんとうはもっと早い時期に紹介しておきたかったが果たせず、ぎりぎりのタイミングでのお知らせになってしまった。クリスティーナ・デ・ミデルは1975年スペイン生まれ、メキシコ在住の写真家である。彼女の作品に出会ったのは数年前になるのだが、それは『The Afronauts』と名づけられた奇妙なシリーズだった。「アフロノーツ」は「アフリカ」と「アストロノーツ」を混ぜあわせた造語。

photography
日々、常に――オカダキサラの日常写真
東京都心部でもっとも東に位置する街のひとつ、南葛西。旧江戸川を隔てた対岸はディズニーランドのある浦安・舞浜という、トーキョー・イーストエンドである。1980年代に建設された戸数900近い巨大団地にオカダキサラは生まれ、いまも住んでいる。1988年生まれ、27歳の写真家だ。

photography
渋イケメンの国から
美しさに絶句する写真集もあれば、刺激的な内容に絶句する写真集もある。でも、「なぜこれが一冊の本に!」と存在自体に絶句する写真集にはなかなか出会わない。そんな驚きで、久しぶりにフラフラな気持ちにさせてくれたのが『渋イケメンの国――無駄にかっこいい男たち』だった。著者である三井昌志はもう十数年間、アジアを中心に長い旅を続けて、その道程で撮影した写真を本にまとめたり、CDーROMにして自分のサイトで販売して生計を立てている「旅の写真家」である。2010年にはバングラデシュで購入したリキシャ(三輪自転車タクシー)に乗って、日本一周6600kmを走破するプロジェクトも達成している。過去の作品には『アジアの瞳』『美少女の輝き』『スマイルプラネット』など7冊の写真集があり、その幾冊かは旅行本を専門にする書店などで見た覚えがあるが、「渋イケメン」にフォーカスした写真集はさすがに初めて。おそらく類書もゼロだろう。

photography
シカの惑星
『渋イケメン』と同じく、こちらも誤解されがちなタイトルと裏腹にシャープな視点を持った写真集『しかしか』をご紹介する。「ねこ派? いぬ派? しか派! フシギでカワイイしかの魅力に迫る」なんていう女子っぽい帯文にだまされないように。タイトルどおり、シカを撮った写真集ではあるけれど、ここにあるのはかなりシュールでダークな光景だ。見方によっては『猿の惑星』ならぬ『シカの惑星』という映画のスチル写真集のようでもあるし、ここにいるシカたちは「バンビ」のイメージとはまるで別種の、人間と野生の境界線を自由に行き来する、しぶとく不可解な生物にも見えてくる。みずからを「シカ写真家」と名乗る著者の石井陽子さんは1962年生まれ。53歳でのこれが初写真集だ。

photography
自撮りのおんな
「セルフィー」という英語すら普通に通用する時代になって、世にはさまざまな自撮り写真があふれているが、先週出会った「自撮り写真家」田岡まきえには、ひさびさに興奮させられた(いろんな意味で)。トークに来てくれた田岡さんは慎ましやかで可愛らしい奥様、という雰囲気を漂わせていたが、抱えていたポートフォリオを見せてもらうと、そこにはスケスケ・セーラー服やホタテビキニ!を着用したり、なにも着用していなかったりする田岡さんが、手にカメラのリモコンを持った「自撮り熟女グラビアモデル」になっているのだった。田岡まきえは1966年大阪生まれ。今週ちょうど50歳になったところだという。

photography
GABOMIの光
高松の路面電車「ことでん」や、香川のロードサイドをめぐる『高松アンダーグラウンド』の連載で、本メルマガでもおなじみの写真家GABOMI。ここ数年はドキュメンタリー・スナップと平行して、実験的な作品制作にも意欲的だった彼女が、きょう(3月2日)から銀座・資生堂ギャラリーで個展を開く。「shiseido art egg」と名づけられた、新進アーティストをピックアップする公募連続企画の一環として開催される今回の展覧会。

photography
ストレンジ&ファミリアー――外国人が見た英国式日常
アート・ファンのみならずクラシック音楽ファンにも、演劇ファンにもおなじみのロンドン・バービカンセンター。地味な高層住宅群に囲まれた地味な建築に、初めて訪れるひとはいささか拍子抜けするかもしれないが、1982年の完成以来、現在でもヨーロッパ最大級の複合文化施設である。バービカンのアートギャラリーで先週スタートしたばかりの展覧会が『Strange and Familiar』。「Britain as Revealed by International Photographers =世界各国の写真家によってあらわにされた英国」と付けられた副題のとおり、イギリス人ではない写真家たちによって捉えられたイギリス、という興味深いテーマ設定。そのキュレーションを担当したのがストレンジ・フォトの元祖であり、「カスハガ」をはじめとする珍物収集狂でもあるマーティン・パーとなれば、さらに興味が湧くはずだ。

photography
「流しの写真屋」の見た新宿
竹橋の東京国立近代美術館ではいま『安田靫彦展』が開催中だが、同時に所蔵作品展として『MOMATコレクション 特集「春らんまんの日本画まつり』も開催中。これが「日本画まつり」というタイトルとはうらはらに、佐伯祐三からパウル・クレーにいたる油絵あり、高村光太郎やロダンの彫刻あり、戦争画あり、岡本太郎やピカソもあり・・・と、ぜんぜん「春らんまん」らしくないラインナップで充実。その展示の一室にあてられているのが、『渡辺克巳「流しの写真屋」の見た新宿』だ。ご承知の方もすでに多いだろう、渡辺克巳は近年、急速に再評価が進んでいる昭和のストリート・フォトグラファー。1941年に岩手県盛岡市に生まれ、高校卒業後いちどは国鉄に就職するが、20歳で上京。写真館で技術を学んだのち、1965年から新宿で「1ポーズ3枚200円」で写真を撮って翌日プリントを渡す「流しの写真屋」を始める。

photography
浅草暗黒大陸
広島県福山市の若き写真家・弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)が、2000年代のサンフランシスコ・アンダーグラウンド・シーンを撮影した写真展『SAN FRANCISCO』を、2015年4月8日号で紹介した(『テンダーロインをレアで』)。その展覧会と同じ新宿のギャラリーPLACE Mで今月11日から、こんどは「浅草」をテーマにした写真展が開催される。弓場井さんは1980年広島県生まれ。2003年から2008年までサンフランシスコの元祖オルタナティブ・マガジン『RE/Search』編集部で住み込みインターンとして生活。そのとき撮影された作品が去年の展覧会だったわけだが、サンフランシスコから帰国後は東京・浅草に居を移し、ホッピー通りにある煮込み屋で働きながら、「いつもポケットにコンパクトカメラを忍ばせて、仕事までの道すがら、休憩中、そして仕事中に撮影した」のが今回の作品群。

photography
美脚の自撮り宇宙
去年9月、恒例の「東京アートブックフェア」がちょうどフランス出張と重なって、行けずに悔しがっていたら、「こんなおもしろいの見つけました」と持ってきてくれたひとがいた。『巨大娘』と『美脚星人』という2冊の写真集である。『美脚星人』から見てみると、いきなり表紙がピンヒール姿の美脚。しかも下半身だけで、上半身がない! それがコラージュかフォトショップ加工かと思いきや、上半身を絶妙の角度に曲げて、それを三脚に据えたカメラを使って自撮りしてるという!(写真集の最後にも「これらの写真は修正して上半身を消したのではありません。ポーズや角度を試行錯誤して撮りました」と、ちゃんと記されている)そして『巨大娘』のほうは、自分の足によって踏みつぶされそうな風景や「小人」を、なんと自撮り棒とスマホを使って撮影したシリーズ。そう、例の自撮り棒を頭上ではなく、地面すれすれに下げて撮影するという、こちらも意表を突いたスタイルなのだ。

photography
ブルジョワジーの豊かな愉しみ――写真展「ジャック=アンリ・ラルティーグ 幸せの瞬間をつかまえて」
これまで何度も展覧会が開かれて、日本でも人気の高いジャック=アンリ・ラルティーグの写真展が埼玉県立近代美術館で開催中だ(5月22日まで)。プロフェッショナルとは「レベルの高い写真を撮るひと」、アマチュアとは「そこまでいかないひと」と思われるようになったのは、19世紀にさかのぼる写真の歴史の上で、実はここ数十年のことにすぎない。日本でも東京や関西、鳥取など各地の裕福な趣味人が「芸術写真」を戦前に育んできたように、かつてプロとは依頼されて人物や風景を撮る「写真師」であり、高価なカメラ機材を購入して「好きなものを好きなように撮る」のはアマチュアの特権だった。

photography
昭和の終わりの新宿で
新宿区三栄町、といっても地元の人間以外にはイメージが浮かばないだろう。JR.四ッ谷駅から徒歩約10分、市ヶ谷の防衛省方面に下る坂道の途中にある、静かな住宅街にあるのが新宿歴史博物館。本メルマガではすでに2014年3月19日号で『新宿・昭和40年代 ―熱き時代の新宿風景―』、2015年1月7日号で『新宿・昭和50―60年代 <昭和>の終わりの新宿風景』と、ふたつの新宿風景写真展を紹介してきた。新宿歴博では2010年から新宿の風景写真展を連続開催してきたそうだが、その総まとめとして、太平洋戦争終戦から昭和の終わりまでの変遷を写し取った、約100枚のプリントによる『戦後昭和の新宿風景 1945―1989』を開催中だ(6月12日まで)。

photography
雑種のしあわせ、ふたたび――佐々木まことの動物写真2016
ちょうど1年前の2015年5月27日号で、大阪の動物写真家・佐々木まことの紹介記事『雑種のしあわせ』を掲載した。本メルマガで『ジワジワ来る関西奇行』を連載してくれている吉村智樹さんの編集で、2005年に発売された小さな写真集『ぼく、となりのわんこ。』を見たのがきっかけだったが、その佐々木さんが毎年参加している『大阪写真月間』と、同時期開催の『日本猫写真協会展』に、今年も選りすぐりの犬猫写真を出品するとのお知らせをいただいた。

photography
映画館からフィルムが消える日に
京橋の近代美術館フィルムセンターでは、『写真展 映画館――映写技師/写真家 中馬聰の仕事』を開催中である。この展覧会についてはきちんと紹介したいと思っていて、そろそろというタイミングで、イギリスでやはり消えゆくフィルム上映の映画館と映写技師を撮影してきたリチャード・ニコルソンの作品を知ることができた。まったくの偶然だが洋の東西で同じく、「フィルム」という映画のよろこびのオーラをまとったメディア――その終焉を見据えるふたりの写真家を今回は同時に紹介する。ひとつのテーマが、視点によってこんなふうに異なる作品に結実する、というおもしろさとあわせ、ご覧いただけたら幸いである。

photography
どこまでいくのかマキエマキ
今年2月10日号で『自撮りのおんな』として紹介した「50歳人妻セルフポートレートフォトグラファー」、マキエマキ(田岡まきえ)さんが、いま新作写真展を東京・入谷のバーで開催中だ(18日=今週土曜日まで!)。バー「Lucky Dragon えん」でマキエさんが個展を開くのは2回目。去年の展覧会タイトルは「J'ai 50ans」(私は50歳)だったけど、今年のタイトルは「Ju suis toute chaude」。マキエさん本人の和訳によれば「アタシ、もう、熱いのよ~ん♡」ということで、その急速なレベルアップぶりがタイトルからも見て取れるというもの。

photography
東京の穴ふたたび
2014年11月26日号『東京のマルコビッチの穴』で紹介した「ダクト・フォトグラファー」木原悠介のの写真展が、東京中目黒ポエティックスケープで始まっている(8月6日まで)。木原さんの写真に出会ってから、まだ2年にもならないけれど、最初からそのミステリアスな画面には強く引き込まれるなにかがあった。記事のなかで、僕は木原さんをこんなふうに紹介させてもらった――不思議な写真を見た。息づまる、というより、ほんとうに息が詰まるような狭苦しい空間が、ずっと先まで伸びていて、それはどこに続くのか、それともどこにも着かないのか・・・。見るものすべてを閉所恐怖症に追い込むような、それでいて難解なSF映画のように異様な美しさが滲み出るそれは、ビルの内部を走るダクトの内部を撮影したものだという。

photography
羽永光利アーカイブ展――ある写真家の時代遺産
もっと早く紹介するつもりが、会期終了直前にずれ込んでしまったけれど、いま東京目黒区祐天寺のギャラリーAOYAMA | MEGUROでは、『羽永光利アーカイブ展』を開催中だ。羽永光利、という写真家をどれだけのひとが知っているだろう。本メルマガではおなじみ、『独居老人スタイル』でもフィーチャーした仙台のダダカンの、若き日の「殺すな」とかかれた書を持って歩く姿を撮った写真家が、羽永光利である。1933年生まれということは、戦争まっただ中に少年時代を送った羽永光利は、戦後しばらくたった1956年になって文化学院に入学。卒業後はアート・フォトグラフィを目指すが、1962年からは作品制作と平行して、フリーランス・カメラマンとして前衛アーティストたちの記録を雑誌などで発表するようになる。1981年からは新潮社の写真雑誌『フォーカス』の立ち上げに参加。その後、国内外の写真展に参加したり個展を開いていたが、1999年に死去。2014年になって、AOYAMA | MEGUROTOとぎゃらり壷中天によって、あらたな紹介が始まった。つまり死後15年も経ってから、いわば「再発見」された写真家、それが羽永光利なのだ。

photography
Campus Star ―― 制服から透けて見えるなにか
中田柾志の写真と出会ったのは2012年ごろ。最初に見たのは、パリ・ブローニュの森の奥で客を引く娼婦たちを撮影したポートレートだった。木立の陰に潜んだ獣のように生命力に満ちた、ときに高貴にすら見えるその姿に魅了され、本人に会ってみると、ほかにもさまざまなシリーズを手がけていることが分かり、本メルマガでは2013年の1月に、3週連続で紹介させてもらった。その中にはフランクフルトの娼館街「エロスセンター」の、娼婦たちの部屋を撮ったシリーズがあったし、素人女性が応募してくるモデル募集サイトで探した女性たちを撮影した「モデルします」、世界でいちばんセクシーな学生服といわれるタイの女子大生のぴちぴち制服シリーズなど、エロと社会性が絶妙の割合で配合された膨大な作品がたくさんあって、どうしてこれほど興味深い写真が一冊の写真集にも、写真雑誌の特集にすらなっていないのか、僕には理解できなかった。

photography
女子部屋――川本史織と女の子たち
ずっと昔、こんなふうに中国が開ける前の北京に通っていた時期があった。そのころ北京でいちばん大きな書店に行くと、一冊の本に群がる男たちを仏頂面の店員がにらんでいて、いったいなにを見てるのかと思ったら、それはデッサン用の「人体ポーズ集」だった。なぜそれが?と手に取ってみると、小汚い白黒印刷のページには、ちょっとくたびれた全裸の白人モデルがいろんなポーズを取っていて、ようするに北京の男たちはそれをエロ本(というものは存在しなかったから)に代わる貴重なネタとして凝視していたのだった。2013年1月に川本史織の『堕落部屋』という写真集を紹介したことがある。「デビューしたてのアイドルだったり、アーティストの卵だったり、アルバイトだったりニートだったり・・・さまざまな境遇に暮らす、すごく可愛らしい女の子たちの、あんまり可愛らしくない部屋を50も集めた、キュートともホラーとも言える写真集」と書かせてもらったが、その川本さんの第二弾写真集が『作画資料写真集 女子部屋』というので、もう20年以上も前の北京の思い出が甦ったのだった。

photography
移動キャバレーの誘惑――沈昭良写真展『STAGE』
これまでも本メルマガで何度か取り上げた台湾の写真家・沈昭良(シェン・ジャオリャン)によるステージ・トラックの写真展『STAGE』が、いま東京虎ノ門の台湾文化センターで開催中だ(10月28日まで)。台湾式ステージ・トラックの再解釈とも言える、やなぎみわのステージ・トレーラー・プロジェクトをご存じのかたもいらっしゃると思うが、今回展示されるステージ・トラックは、2006年から2014年までに撮影されたものだという。

photography
トーキョー・ハロウィーン
10月30日深夜、福岡空港から地下鉄に乗って天神駅で降りようとしたら、ナース・コスチュームのゾンビがひとりで、ぽつんとホームに立っていた。きょうは31日。いまごろ渋谷の交差点は大変な賑わいになっているのだろうか。「バカやってるいまどきの若者たち」を探して、マスコミがぎらついた眼(とレンズ)で走り回ってるのだろうか。キリスト教徒でもなんでもない日本の子供(とママ)への新規市場開拓として導入されたはずのハロウィンが、こんなに異常な、日本独特の盛り上がりを見せるようになってもう数年が経つ。いったいこの事態を誰が予測しただろう。

photography
時速250キロの車窓から
世の中にはいろんな職業があるが、増田貴大の仕事は「毎日2回、新大阪と広島を新幹線で往復すること」。病院から検査機関に送られる血液検体を運ぶための「荷運び屋」である。いつものように荷物を持って窓際の席に座って、外の景色を見ていたら、こちらに向かって手を振る親子連れが見えた。「いい絵だなあ、これを写真に撮ったら、いい作品になるだろうなあ」と思ったのが、それまでカメラマンを目指したものの上手くいかず、30歳を過ぎてもフリーターのような生活に甘んじていた生活の転機になった。次の日からカメラを持って新幹線に乗るようになって、撮りためた車窓からの風景はこの9月に新宿コニカミノルタプラザで『車窓の人々』と題した写真展になり、ビジュアルアーツフォトアワード2016で大賞を獲得、来年1月には初写真集も発売される。

photography
築地魚河岸ブルース
いよいよ今年、もう待ったなしの築地魚河岸はどうなるのだろうか。本メルマガ2014年2月12日号『夜をスキャンせよ』で紹介した「白目写真」の沼田学による新作展が、1月6日から歌舞伎町の新宿眼科画廊で開催される。タイトルは『築地魚河岸ブルース』、築地に働く男たちを定点観測のように記録したシリーズだ。これまで築地をテーマにした写真は数えきれないほど発表されてきた。日本だけでなく、海外の写真家による写真集もたくさんある。先日も本橋成一による15年間の築地通いの成果をまとめた『築地魚河岸ひとの町』が日英バイリンガルで出版されたばかりだし(朝日新聞出版社)、いざ移転となればこれからもさまざまなメディアで、多くの作品が発表されていくのだろう。

photography
ロック・スターズ・イン・ジャパン!
『ミュージックライフ』といえばオールド・ロック・ファンは涙なしに語れない、ロック創成期から続いてきた音楽誌。1951年にスタートして1998年の休刊にいたるまで、一時は日本最大の洋楽専門誌だった。そのミュージックライフ誌の専属カメラマンを長く勤めた長谷部宏さんによる、ロック史をいろどるアーティストたちの貴重な「来日ショット」ばかりを一同に展示した楽しい写真展、『ROCK STARS WILL ALWAYS LOVE JAPAN ~日本を愛したロックスター~』が開催中だ。本メルマガでは2015年1月14日号で新宿ビームスBギャラリーでの展覧会を紹介していて(偶然にも、そのとき一緒に取り上げたのが沼田学写真展『界面をなぞる』だった)、ちょうど2年ぶりの告知となる。

photography
菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.1 重慶と夜のクイーンたち(写真:菊地智子 インタビュー:茅野裕城子)
菊地智子さんは1973年生まれ、武蔵野美術大学空間デザインかを卒業したあと、香港を経て1999年から北京に在住というから、もう17年間も北京をベースに写真を撮っていることになる。2006年からドラァグクイーンの撮影を始め、そのシリーズ『I and I』で2013年には第38回・木村伊兵衛写真賞も受賞した。年末から今月にかけて一時帰国した菊地さんにお願いして、ロードサイダーズ・ウィークリーではこれから数回にわたって、菊地智子によるドキュメンタリー・シリーズをお届けする。掲載は不定期になってしまうが、とりわけ隣国であるこの国では、予断と偏見に満ちたイメージばかりが先行する、中国という巨大な国家の「もうひとつのリアリティ」を知っていただけたらうれしい。その第一弾となる今回は、『I and I』のテーマとなった、重慶を中心とする中国全土のクイーンたちをめぐるドキュメンタリーをお見せする。聞き手は、かつて僕自身の中国珍スポット取材を手伝って、重慶にも同行してくれた小説家・茅野裕城子さんにお願いした。写真作品とインタビューが織りなす物語を、じっくりご覧いただきたい。

photography
『NOZOMI』増田貴大写真集、発売!
去年11月9日号で特集した「新幹線車窓写真家」増田貴大の初作品集が、めでたく発売になった。『NOZOMI』・・・いいタイトルだなあ。『時速250キロの車窓から』と題した記事を読んでくれたかたはおわかりだろうが、増田さんは検査用の血液検体を運ぶという珍しい仕事で、新大阪と広島のあいだを毎日2往復しながら、乗車中ずっとデッキに立って、窓に貼りついて景色を撮影している。それだけでは生活が成り立たないので、「午前中、あべのハルカスで医療フロアへの案内看板持ちもやってるんです。朝9時から12時までハルカスで、そこから急いで新大阪に移動して、新幹線に乗って。家に帰れるのは夜11時ごろになっちゃうので、車窓写真しか撮れないです」。

photography
食に淫する女と男
先日、早稻田大学に呼ばれて、トークのあと学食の一角に机を並べて、居残ってくれた学生たちと話していたとき、「こんなの作ってるんです」とZINEを渡してくれた子がいた。イチゴをくわえた唇が大写しになった表紙には『食に淫する』というタイトルがついていて、ページをめくるとケーキや果物を頬張って、ぐちゃぐちゃになった口中がアップになっていたりして、非常に汚く、どぎつく、美しくもある。ウェット&メッシーと言ってしまえばそれまでだけど、それだけでは片付けられない、視覚と触覚と味覚を混ぜ合わせた複雑な快楽のような、甘みと深みがとろとろと画面から流れ落ちている。

photography
追悼 レン・ハン
すでにSNSなどでニュースを知ったかたもいらっしゃるだろうが、2月24日、中国の写真家・任航 (Ren Hang=レン・ハン)が亡くなった。レン・ハンは本メルマガの2014年12月10日配信号で特集した、中国写真界の若きスターだった。記事中で書いたが、その秋の東京アートブックフェアで、台湾から参加したブースでレン・ハンの写真集『SON AND BITCH』を見つけ、衝撃的な内容に驚愕。さっそく北京在住のジャーナリスト、吉井忍さんにお願いしてインタビューしてもらったのだった。それから2年と少し、レン・ハンはヨーロッパ各地で大きな展覧会を続けざまに開催。タッシェンから分厚い作品集が発売され、いまこの時もストックホルムの写真美術館フォトグラーフィカで個展が始まったばかりである。それなのに自殺してしまった彼は、まだ30歳の若さだった。

photography
「ハナヤ勘兵衛の時代デェ!!」追補
先週お伝えした、兵庫県立美術館でのアドルフ・ヴェルフリ展と同時に開催されている『小企画 ハナヤ勘兵衛の時代デェ!!』展。「収蔵品によるテーマ展示」室のひとつで開催されている写真展だ。ヴェルフリ展は先週末で終了してしまったが(3月7日より名古屋市美術館に巡回)、ハナヤ勘兵衛ののほうは3月19日まで開催中。ここに掲載した以外にも、特に戦後期のスナップがたくさん見られるので、この機会にぜひご覧いただきたい。

photography
サンフランシスコの裏側で
2015年4月8日号で弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)という写真家を紹介した(『テンダーロインをレアで』)。サンフランシスコのアンダーグラウンドの最底辺まで、広島県福山市出身の若者が降りていったことがまず驚きだったし、そのハードエッジな画面にみなぎる「ITバブル」以前のサンフランシスコの空気感が、懐かしくもうれしくもあった。その弓場井宜嗣が2年ぶりに新宿の写真ギャラリー「PLACE M」で、『SAN FRANCISCO #2』と題した個展を開催、同時に写真集もリリースする。

photography
渋イケメン集合!
2015年12月23日号で取り上げた写真家・三井昌志の展覧会『渋イケメンの国』が今週13日から1週間、銀座キャノンギャラリーで開催される。1年前に発表された写真集『渋イケメンの国――無駄にかっこいい男たち』の、まずタイトルにやられ、写されたまさしく「無駄にかっこいい男たち」の存在感にやられたひとは、僕以外にもたくさんいるだろう。記事の中で三井さんをこんなふうに紹介した――

photography
『羽永光利一〇〇〇』刊行記念展
去年8月17日号で紹介した写真家・羽永光利の作品集『羽永光利一〇〇〇』がついに完成、そのお披露目を兼ねた展覧会が恵比寿ナディッフで開催される。戦中世代である羽永は文化学院卒業後、アート・フォトグラフィーを目指しつつ、フリーランス・カメラマンとして前衛アーティストたちの記録を雑誌などで発表するようになる。1981年からは新潮社の写真雑誌『フォーカス』の立ち上げに参加。その後、国内外の写真展に参加したり個展を開いていたが、1999年に死去。2014年になって、AOYAMA | MEGUROTOとぎゃらり壷中天によって、あらたな紹介が始まった。つまり死後15年も経ってから「再発見」された写真家だ。

photography
いま、そこにある異景
ラルフ・ユージーン・ミートヤードという写真家の不思議な作品を初めて見たのはいつだったろうか。モノクロームの画面の、一見どこにでもあるようなアメリカの郊外風景でありながら、その登場人物たちがハロウィーンのような不気味な画面をつけ、しかしこちらを怖がらせようとするふうでもなく、ただそれが自分の顔であるようにたたずみ、こちらをまっすぐ見ている。怖がらせようとしていないのが、よけい怖い。ひどい悪夢から目が覚めて、まだ現実とのあいまいな境界に意識があるような、落としどころのない気持ちにさせられる。その写真家の名前がミートヤード(Meatyard=肉の庭!)だと知って、さらに不思議な気持ちになったのを覚えている。この3月から5月初めまで、サンフランシスコのフランケル・ギャラリーでミートヤードの写真展『American Mystic』が開催された。観に行くことはできなかったが、展覧会に際して発行された作品集を入手できたので、小さな紹介を試みてみたい。

photography
食卓の虚実
シャネルにプラダ、マックイーンにラガーフェルドと、世界のハイファッション・メゾンを顧客に持つ超売れっ子でありながら、いつもちょいブラックで悪戯っぽいテイストを忘れないノーバート・ショーナーという写真家がいる。本メルマガでは2012年7月18日号で作品集『Third Life』を取り上げ、そのときは代官山蔦屋書店で一緒にトークもした。古い友人である、そのノーバートが久しぶりに東京でいま写真展を開催中(5月21日まで)。『NEARLY ETERNAL』と題された今回の展覧会は、なんと食品サンプルがテーマ。たしかに「ニアリー・エターナル=ほとんど永久」・・・。

photography
異郷のモダニズム――満州写真展に寄せて
この3月に『アドルフ・ヴェルフリ 二萬五千頁の王国』展記念トークをやらせてもらった名古屋市美術館で、いま『異郷のモダニズム―満州写真全史―』という珍しい展覧会が開催中だ(6月25日まで)。会期末近くになってしまったけれど、これだけまとまった規模のコレクションはなかなか見られないと思うので急いで紹介させていただきたい。ご存じのとおり「満州」とは20世紀初めの日露戦争終結から、第二次世界大戦で日本が敗戦するまでの期間、中国東北部に存在した国家・・・であり幻の国家でもある。

photography
遺された家の記憶
かつて「グラフ雑誌」というものがあった。「アサヒグラフ」「毎日グラフ」など、アメリカの「LIFE」を範とするグラフ・ジャーナリズムは20世紀の報道媒体として重要な役割を果たしてきたのだが、そうしたグラフ誌が全滅してしまった現在、とりわけ硬派なドキュメンタリー・フォトグラファーにとっては厳しい状況が続いている。ネットがあるじゃないかと言っても、個人での発信は影響力でも経済力でも全国誌とは比べものにならないし、セールスが期待できない写真集を出そうという出版社は減るばかりだ。そんな現状でときたま、時間をかけて丁寧につくられたドキュメンタリー作品に出会うと、背筋が伸びる思いがする。『遺された家』は奈良県在住の写真家・太田順一が去年12月に発表した写真集だ。大阪の朝鮮人コミュニティ、沖縄人コミュニティ、ハンセン病療養所など、入り込むことすら簡単ではないテーマばかりを選び、「歩いてなんぼ」と通い詰めて本にまとめてきた太田さんにとって、これは久しぶりの写真集になる。

photography
菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.2 迷境/傷城~重慶 若者のセクシュアリティーと壊れゆく街(写真・文:菊地智子)
私は1999年に香港から北京に移りましたが、その当時、同性愛というのはまだまだ口にするのもはばかられる感じで、友人同士でこっそり家で集まったりと、かなり閉鎖的でアンダーグラウンドな存在でした。親にカミングアウトするのはもちろんもってのほか。そのためゲイであることにまつわる涙ぐましい話は尽きなかったんです。中国の著名作家余華の言葉に「西洋人が400年かけて経験してきた天と地ほどの差のあるふたつの時代を、中国人はたった40年で経験してしまった」というのがありますが、中国のセクシュアリティーに関していえばこの20~25年(もしくは約四半世紀)あまりで数百年の変化を遂げていった感があります。

photography
走り続ける眼
どうしたら写真家になれるんですか、とよく聞かれる。そんなのこっちが知りたいけれど、写真ギャラリーでのグループ展→個展→アート系出版社から写真集発売、というよくある流れの外側で、ちょっと前まで考えもつかなかったやりかたで活動する写真家が現れてきた。今週・来週と2回にわたって、最近出会ったユニークなスタイルの写真家をふたり紹介したい。種田山頭火を放浪の俳人と呼び、山下清を放浪の画家と呼べるならば、天野裕氏(あまの・ゆうじ)は放浪の写真家である。家を持たない。展覧会を持たない。写真集の出版もない。軽自動車に寝泊まりしながら日本中を走り回り、ツイッターで「きょうはこの町にいます」とつぶやき、喫茶店やファミレスやスナックや公園で「客」を待つ。
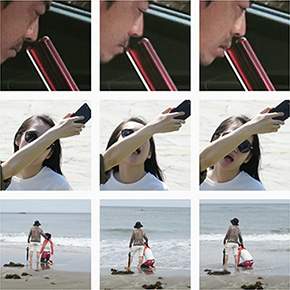
photography
日常の切断面
先週は車中泊で日本中を移動しながら写真を撮り、コンビニでプリントアウトした「写真集」を喫茶店やファミレスやスナックで見せ、その「見料」で制作/生活する写真家・天野裕氏を紹介した。「移動し続けること」が作品の中心にある天野さんとまったく対照的に、今週ご覧に入れるのは「どこにも行けないこと」がユニークな作品に結実している写真家・北村千誉則(きたむら・ちよのり)だ。つい最近、たしかFacebookだったと思うが、なんとも不思議な写真集を紹介する投稿に偶然目が止まった。表紙にはおっさん(たぶん)の口元からこぼれる白米とイクラ1粒が超望遠で捉えられ、『buh___bye』なる不可解なタイトルがついている。説明を読むと、作者はChiyonori Kitamuraというので、日本人だとは思うが名前を聞いたことがないし、発行元の「modes vu」という香港の出版社も知らなかったが、とりあえず購入希望のメッセージを送ってみると、数日後にちゃんとポケットサイズ48ページほどの小さな写真集が自宅に届いた。

photography
オキナワン・ソウルシスターズ
先々週号の編集後記で少しだけ沖縄・コザのことを書いた。極東最大の空軍基地である嘉手納基地に隣接するコザは、米軍人を対象とするサービス産業で急激に発展した町だったが、いまでは大通りに面した数軒のバーやポールダンス・クラブ、衣料品店などに、最盛期の面影をわずかに見て取れるのみである。1972年の日本復帰前から沖縄は多くの写真家たちを引き寄せてきたわけだが、「沖縄以外のものはそこの土地のひとが撮ればいい」と、生まれ故郷の沖縄にこだわり続けてきた写真家が石川真生(いしかわ・まお)。本メルマガでも沖縄の港町に生きる男たちを捉えた『港町エレジー』を2012年に紹介している(2月15日号参照)。その石川さんが1982年に発表した処女作『熱き日々 in キャンプハンセン!!』(あーまん企画刊)が、35年の歳月を経て『赤花 アカバナー、沖縄の女』と新たなタイトルと編集により、ニューヨークの出版社セッション・プレスから発表された。

photography
ロバート・フランク 本と映像展
そういえばうちにロバート・フランクの写真集は一冊もなかった、なぜだろう――神戸で開催中のきわめてユニークなロバート・フランク展を観ながら、まずそんなことが頭に浮かんだ。かつて神戸市立生糸検査所だった建物が、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO)として生まれ変わった広い空間で、『Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe』が開催中だ(9月22日まで)。2014年カナダ・ハリファックスで始まり、去年は東京藝術大学でも開催された、世界50ヵ国を巡回中の展覧会「神戸バージョン」である。ただし、この展覧会は白い壁に額装されたオリジナルプリントが整然と並ぶ、普通の写真展ではない。

photography
どうでもいいものの輝き――平原当麻の写真を見る
写真ファンならご存じだろうが、東京新宿一丁目あたりには写真専門のギャラリーが何軒か集まっている。中にはひとつのビルに複数のギャラリーが入っていることもあるので、ついでに覗いてみた展覧会で予期せぬ出会いや発見があったりもする。先日、用事があって写真家の瀬戸正人さんらが運営するギャラリーPLACE Mに行ったとき、階下のRED Photo Galleryで展覧会を開いていたのが平原当麻さんだった。REDは若手の写真家十数人が共同で運営するギャラリーで、各自が年に何度か展覧会を開くことになっていて、そのときちょうど平原当麻さんが『ライヴ・アンダー・ザ・スカイ』という、お洒落でジャジーなタイトルの、ぜんぜんお洒落でもジャジーでもない都市風景を撮りためたプリントを展示していたのだった。

photography
狂女の日常――YOSHI YUBAI写真展『URI』
これまで本メルマガにサンフランシスコ・テンダーロイン地区や浅草のアンダーグラウンド・ドキュメンタリーを寄せてくれた、広島県福山市出身のフォトグラファー弓場井宜嗣(ゆばい・よしつぐ)=YOSHI YUBAI。2016年の『浅草暗黒大陸』に続いて新宿PLACE Mで新作展『URI』を開催する。展覧会サイトの説明にたった一行「狂女『URI』の記録」と記されているURIは、YUBAIくんが「以前付き合っていた女の子」。そういう関係でないと撮れないであろう、ひとりの女性が内在するフリーキーなエネルギーが、モノクロームを主体とした画面上で暴発しているようだ。

photography
自撮りのおんな2017
2016年2月10日配信号で初めて紹介した「自撮り熟女」田岡まきえ=マキエマキさん。あれから1年半経って、ずいぶん溜まった新作をこの11月に銀座1丁目の古風なギャラリービル「奥野ビル」内の銀座モダンアートでご披露する。ツイッターやFacebookなどSNSでの発信がすごく活発で、あまりご無沙汰感がないけれど、実は久しぶりのマキエさんに、この1年半のことを聞いてみようとお茶に誘ってみた。で、入ってきたマキエさんを見てびっくり。去年よりずっと若返ってる!

photography
センター街のロードムービー、再映!
このメルマガを始めた年の2012年10月17日号で、『センター街のロードムービー』という記事を掲載した。小岩のゴムプレス工場で働きながら、週末ごとに夜の渋谷センター街に出て、2000年ごろからずっと写真を撮っている鈴木信彦のことを書いたのだった。印画紙の上にあらわれ消える男女たち。それはいまから数年前、日本でいちばんスリリングな夜があった時代の渋谷センター街に、生きていた男の子と女の子たちだ。焦点の合った主人公と、その向こうのぼやけた街並み。

photography
「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」瀬戸正人x都築響一・二人展
東京・新宿御苑の大木戸門から新宿方向に広がる新宿1丁目界隈が、写真専門ギャラリーの集まるエリアとなって久しい。通常の商業画廊ではなく、写真家たちがみずから運営することで、発表の場をつくり育てようという、ノンプロフィット・ベースのギャラリーが集まっているのが特徴だ。なかでも老舗のPLACE Mは、写真家の大野伸彦、瀬戸正人、中居裕恭、森山大道らによって運営される「写真の実験の場」として1987年に設立。今年で30周年を迎えた。本メルマガでもPLACE Mで開催される展覧会をずいぶん紹介してきたし、写真ファンにはおなじみのギャラリーだろう。そのPLACE M30周年を記念して、代表の瀬戸正人(せと・まさと)さんに声をかけていただき、二人展を開催することになった。グループ展はよくあるけれど、二人展というのは僕にとって初めてかもしれない。

photography
「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」開催中!
先週号でお伝えしたように東京・新宿御苑の写真専門ギャラリー、PLACE M30周年を記念して、代表の瀬戸正人(せと・まさと)さんとの二人展「TOKYO STYLE/LIVING ROOM」が月曜日にスタートした。1996年に発刊されて、その年の第21回木村伊兵衛賞を受賞した瀬戸さんの『部屋 Living Room, Tokyo』(新潮社)と、1993年に出版した僕の『TOKYO STYLE』。どちらもバブル崩壊直後という時期に、東京の部屋から部屋へとさまよった記録である。

photography
女装の目線
先日、新宿PLACE Mの写真展で、ひとりの女性に声をかけられた。ワークショップに通うアマチュア写真家で、日本三大寄せ場のひとつ、横浜寿町で炊き出しを手伝ううちに帽子おじさん=宮間英次郎とも仲良くなったという。どんな写真を撮ってるんですかと聞くと、「横浜の女装おじさんたち・・」と小さな声で話してくれて、がぜん興味が湧いてきた。ポートフォリオを見せてもらったら、すごくいい。いまどきの女装子のような可愛さはないけれど、そのぶん愛嬌があるし、それをファインダー越しに見る視線のあたたかみがじんわりと伝わってくる。矢崎とも子さんは1960(昭和35)年東京生まれの横浜育ち。多摩美大の油絵科を卒業し、ギャラリーで働いたあと、いまは専業主婦。その矢崎さんは今月15日からPLACE Mで『女装放浪記』と題した写真展を開く。

photography
SIRARIKA 池田宏とアイヌ
ロードサイダーズにはすでになじみの深い東京新井薬師・スタジオ35分で池田宏写真展『SIRARIKA』が始まっている。今週は池田宏の写真を長く見てきた編集者の浅原裕久さんに、池田さんとその作品について書いていただいた。今回展示されるシリーズ以前に撮影された写真を交えたインタビュー、さらに「SIRARIKA」誌上写真展と3部構成で、いま、現在進行形としてのアイヌの生のありようをご覧いただきたい。

photography
山と熊と田の物語――亀山亮「YAMAKUMATA」
先月のメルマガで池田宏の『SIRARIKA』を紹介したばかりの新井薬師前スタジオ35分で、また興味深い写真展が始まっている。「マタギの村」として知られる新潟県最北部の村上市山熊田、山あいの小さな村にいまも息づく、熊と人とが自然の中で織りなす暮らしを捉えた、亀山亮の作品集刊行に合わせた写真展『YAMAKUMATA』だ。亀山亮(かめやま・りょう)は1976年千葉生まれ、戦場写真家として知られてきた。生死が隣り合うギリギリの場所で写真を撮ってきた亀山さんは、何年間も通い続けた山熊田でなにを見て来たのだろうか。展覧会の会期中には写真家・鬼海弘雄さんとの対談が予定されている。鬼海さんは村上市と隣り合う山形県の寒河江出身。今回は無理にお願いして、亀山さんの写真に寄せる文章を書いていただいた。

photography
それぞれの決壊
トークのあとにいろんなひとが話しかけてくれる。初対面のひとも、久しぶりに会うひともいて、目の隅で話しかける順番を待ってるひとをチラ見しながら、適当な時間で切り上げなくてはならないのが残念なときも多い。で、そういうタイミングで「写真撮ってて、見てほしいんですけど」と分厚いポートフォリオをカバンから取り出すひとがいる。ちょっと・・・。でも、きちんと名刺交換してアポを取って後日尋ねてくるひとよりも、そんな不器用な(?)見せ方しかできないひとのほうが、実はおもしろい写真を撮っていたりもする。先日、あるトークのあとにそんなふうにポートフォリオを取り出した青年が砂田耕希さんだった。砂田さんは東京や横浜の路上で出会ったひとたちのポートレートをずっと撮っているそうで、4月の1ヶ月間、このメルマガ読者にもきっと大ファンが多いにちがいない新宿駅地下のBERG(ベルク)で初めての写真展『それぞれの決壊』を開く。

photography
ぼろを撮る
昨秋から何度か青森県をめぐって写真を撮っていた。その仕事がようやく形になって、これから1年間の展示が始まる。浅草・浅草寺二天門脇にあるアミューズミュージアムの開館10周年特別展『BORO 美しいぼろ布展 ~都築響一が見たBORO~』と題された写真展。アミューズミュージアムが収集する「ぼろ」の展示にあわせて、僕が撮影した青森を中心とした北の風景、それに青森の人間にまとってもらった「ぼろ」のポートレートで壁や床を埋める展覧会――というと大げさなので、「ぼろ」展示の装飾ぐらいに思ってもらえたらうれしい。

photography
隙ある風景 2017(写真・文:ケイタタ)
みなさま、ケイタタこと日下慶太です。しばらく『隙ある風景』をお休みしていて「地図にない街 釜ヶ崎」の方に集中しようと思っていたのですが、釜ヶ崎と隙ある風景は似ているようで全然違った。ということで二兎追いましてこれから両方寄稿させてもらおうと思います。まずは、復活ということで2017年の隙ある写真を100点どーんと紹介。

photography
ラブドール王国の宮廷写真家
凝りに凝ったセッティングのもの、家族のスナップみたいな気軽なもの、ドール愛に溢れるたくさんの写真を見ていくのは最高に楽しい体験で、受賞作を選ぶのは難しかったけれど、けっきょくグランプリに決めたのが『たべる?』と題された一枚。新妻の風情をまとったドールがエプロン姿で、朝食のトーストとサラダを用意しながら、プチトマトを指でつまんで「たべる?」と差し出している台所の情景だった。可愛らしいけど、エロくはない(ラブドールなのに)。でも、なにか曰く言いがたい恋みたいな感情がそこには漂っていて、目が離せなくなったのだった(フォトコンテストの応募作品は先日発売された『愛人形 Leve Dollの軌跡』に掲載されている)。グランプリ受賞作の作者「SAKITAN」は、その後もTwitterなどでドール写真をコンスタントに発表していて、フォローするのが楽しみだったが、この3月に初の写真展を大阪で開催すると知って、さっそくインタビューをお願いした。撮っている写真にも興味はあったし、なによりSAKITANってどんなひとなんだろう?と気になって仕方がなかった。

photography
渋谷残酷劇場、開演!
すでに告知してきたとおり、今週土曜日(4月14日)から渋谷アツコバルーで『都築響一presents 渋谷残酷劇場』がスタートする。2016年に開催した『神は局部に宿る 都築響一presents エロトピア・ジャパン展』からちょうど2年。その続編(?)として、エロの次はグロにフォーカスした、展覧会なのか見世物小屋なのかお化け屋敷なのかわからない・・・かなりビザールな展覧会になることは間違いないので、18歳以上のみなさまは覚悟の上でご参加いただきたい!

photography
スラム街の記録者――佐々木さんのプノンペン・ライフ
4月の暖かい午後、待ち合わせの時間の少し前に郊外駅の改札を出ると、もう佐々木さんが待っていてくれた。会ってほしいとお願いしたのはこちらなのに、ちょっと申し訳ないというようなはにかんだ表情をして。正月にプノンペンで初めて会ったときのように。毎年プノンペンに通って、スラムで暮らす人々を撮影している日本人写真家がいる、と教えてくれたのは『シックスサマナ』の編集長・クーロン黒沢さんだった。スラムのすぐそば、それも小学校の建物のひと部屋に住みついて、毎日スラム街を歩きまわってるらしいと聞いて、その小学校を訪ねてみたのだった。佐々木健二さんは1966年八王子生まれ。いまも八王子の実家に住んでいる。ふだんは学校の行事や卒業アルバムの写真を撮るのが仕事。1年のうち10ヶ月はそうして働いて、2ヶ月間をプノンペンで暮らす生活を、2004年からずっと続けている。

photography
異界へお出でと笛を吹く――内藤正敏『異界出現』
いまから20年以上前、『珍日本紀行』という企画で地方の町や野山を走り回っていたころ。最初の2、3年はあちこちで出会う妙な風景や建造物を、とにかくなるべくきっちり写さないと、というだけで必死だったが、旅と撮影の生活に身体が少し慣れてくると、ときに白日夢のように眼前に広がる光景を、白日夢のように写せたらと思い始めて、行き着いたのが針穴写真(ピンホールカメラ)だった。だれもいない湖に浮かぶ白鳥型のボートとか、国道脇に立つ古タイヤを組み合わせた巨人とかの前に三脚を立てて、寒さに震えながらじりじり時計を見ているうちに、自分はいま写真を撮っているというよりも、この場所の空気と時間を木箱に封じ込めようとしているんじゃないかと思ったりもした。カメラというのは、単に目の前にあるものを視覚的に記録するための道具とは限らない、と気づいたのがその時だった――というような思い出が、東京都写真美術館で内藤正敏の『異界出現』を見ていて、ふいに甦ってきた。

photography
それからの北朝鮮
ドナルド・トランプと習近平と文在寅、金正恩をめぐる複雑怪奇な輪舞に、日本だけが入れてもらえないきょうこのごろ。北朝鮮をめぐる政治情勢が大きく動きつつあるタイミングで、初沢亜利の写真集『隣人、それから。 38度線の北』が発売された。2012年末にリリースされ、本メルマガでも2013年1月23日号で特集した『隣人。38度線の北』に続く、初沢さんの北朝鮮第2作品集だ。これまでイラク戦争、東日本大震災などの現場に飛び込んで長期間撮影を続けてきた初沢さんにとって、今回は『隣人。』以降、2013年から1年3ヶ月沖縄に移住して撮影した『沖縄のことを教えてください』(赤々舎刊)に続く写真集ということになる。『隣人、それから。』は2016年から18年にかけて3回の訪朝で撮影された写真で構成されている。前回の写真集のために4回、初沢さんはこれまで計7回にわたって北朝鮮を訪れているが、そこにはいつも「2500万人が暮らす隣の国の、普通の暮らしを隣人として知ることの大切さ」への思いがあった。

photography
マーシャ・イヴァシンツォヴァを追って(文:鴻野わか菜)
数ヶ月前、ネット上でマーシャ・イヴァシンツォヴァというロシアの女性写真家を知った。本メルマガでは2015年に、住み込みのナニー(乳母/ベビーシッター)として働きながら、だれにも見せないままニューヨークとシカゴの街や人々を撮りつづけ、死後になって奇跡的に「発見」されたヴィヴィアン・マイヤーの作品を紹介したが、マーシャ・イヴァシンツォヴァは月並みな言い方をすれば「ロシアのヴィヴィアン・マイヤー」とも言える存在である。1924年から91年までのソヴィエト連邦時代にレニングラードと呼ばれていたサンクトペテルブルクに生まれ暮らし、やはりどこにも発表しないまま街や人々の写真を撮りつづけ、死後になってこれもまったくの偶然から、膨大なフィルムとプリントが発見されたのが、いまから半年ほど前のこと。

photography
俺のエロ 2018
先週告知で小さくお知らせした写真展「俺のエロ 2018」が、土曜日から始まります。POPEYE、BRUTUSの時代から組んできて、とりわけ音楽畑では知らぬもののないライブ・フォトグラファーである三浦憲治さん。カップヌードル「hungry?」などの撮影で知られるコマーシャル・ムービーカメラマン瀬野敏さん。御大ふたりとも長年の飲み仲間で、酒の席の勢いで一昨年『俺のエロ』という、冗談みたいなグループ展を六本木のギャラリーで開催。それが「そろそろまたやんない?」という、またも酒の席の勢いで、ふたたび開催することになってしまいました。

photography
迷子のお知らせ――平くんのパンツ
2017年19月11日号『どうでもいいものの輝き――平原当麻の写真を見る』で紹介した、ラブホテルのある郊外風景写真。その平原当麻(たいら・はらとうま)は今年3月、新宿REDフォトギャラリーでの『おんなのアルバム キャバレーベラミの踊り子たち』展をオーガナイズしてくれたが、こんどは平当麻(たいら・たぎま)と、またややこしい名前に改名して、奇妙な写真展を開くというお知らせをもらった。『迷子のお知らせ』というタイトルの展覧会では、ランジェリーショップで買い集めたパンツを、ディスプレー用の電飾マネキンに履かせて撮影した、これもそこはかとなくサバービア感覚漂うイメージの集積である。

photography
霧の山のいのち
山歩きはほとんどしないけれど、山道を運転することはけっこうある。街を走っていたときは晴れてたのに、山道に入ったらいつのまにか、次のカーブが見えないくらい深い霧の中でヒヤリ、というようなこともあって、そんなときのヒヤリはおもに事故の恐怖だけど、同時に、この霧が晴れたら、それまでとはまるでちがった場所になっちゃってるんじゃないかという妄想に、僕はときどきとらわれてしまう。変なSF映画みたいに。ROSHIN BOOKSから阿部祐己(あべ・ゆうき)という新人作家の写真集リリースのお知らせが来て、さっそく注文して届いたのが『Trace of Fog』=霧の痕跡という題名の一冊。それは信州八ヶ岳の霧ヶ峰を撮影した写真集だった。年間を通した観光地としてしられる霧ヶ峰は、その名のとおり、年間200日以上も霧が発生する高原なのだという。

photography
ふりかえれば台湾
いろんな国に行くけれど、台湾だけは空港に降り立つたびに「帰ってきた」感覚に襲われる、とどこかに書いたことがある。同じような気持ちになる台湾ファンが、けっこういるのではないか。清里フォトアートミュージアムではいま『島の記憶――1970~90年代の台湾写真』という展覧会が開かれている。おもに1950年代から60年代前半に生まれた、つまりいま60代から70代のベテラン写真家たち11人の、若き日の作品152点が並ぶこの展覧会は、作品のほぼすべてが日本、そして台湾でも初公開であり、そもそも台湾の写真がこんなふうに日本の美術館でまとまって紹介されることが初めてだという。1970年代から90年代という時期は、中国本土では文化大革命が終息し、周恩来・毛沢東が死去、米中・日中国交正常化、開放化政策の推進、そして天安門事件、香港返還と中国現代史のターニングポイントとなる出来事が連続するが、台湾でも国連脱退、蒋介石死去、38年間続いてきた戒厳令の解除と国民党独裁の終焉、そして進展する民主化という急流の中にあった。「島の記憶」という展覧会タイトルは、そのように激変する島のありようを見つめ、歩き、記録せずにいられなかった若き写真家たちの熱情や興奮、怒り、苛立ち、悲しみといった心情が、「記憶」という言葉のなかに包み込まれている。

photography
Freestyle China 即興中華 見てはいけない箱だった――写真家・劉錚に聞く中国(文:吉井忍 作品提供:Liu Zheng)
6月末に中国武漢を訪れたときのこと。アート系のお洒落な書店に立ち寄り、現代中国の写真家コレクションみたいな本を見つけてページをめくっているうちに、一群のモノクロ写真を載せたページから目が離せなくなった。アーティスティックな現代美術写真ではないし、ゴリゴリの社会派ドキュメンタリーでもない。被写体は普通の中国を生きるひとびとなのだろうけれど、どこか違和感が漂っていて、アウグスト・ザンダーやダイアン・アーバスや、ヴィヴィアン・マイヤーのポートレートを見せられているような気持ちになってくる。その写真家・劉錚(リュウ・ジェン)は調べてみると北京在住。さっそく、本メルマガで「Freestyle China 即興中国」を連載中の吉井忍さんにお願いして、インタビューが実現した。写真家であり、写真集出版者であり、写真キュレーターでもあるリュウ・ジェン。2010年代の中国写真はこんなにもエネルギッシュなのだった。

photography
夢は廃墟をかけめぐる
「廃墟写真」というジャンルが確立してから、もうずいぶん時が経つ。僕自身は廃墟よりも、廃墟になる一歩手前の場所で生活の気配を写そうとすることのほうが多いけれど、廃墟の写真を見るのはもちろん嫌いではなくて、国内・海外の廃墟写真家の作品をずいぶん見てきた。人間の表情のように建物や遺跡や風景は始終変わっているわけではないので、同じ場所にいれば、だれが撮っても同じようなものと思われるかもしれないが、それが微妙に異なるところが廃墟写真のおもしろさでもある。資料としてかっちりと、スキャンデータのように写される廃墟もあれば、建造物を包み込む空気感のようなものが掬い取られる、そういう廃墟写真もある。同じ場所から、同じ角度で撮影しているのに。図面と絵がちがうように、それは撮影者の視点や思いが、デジタルデータという無機的なメディアにもちゃんと反映されるのだ。

photography
天幕の見世物小屋、サーカスの時間
『サーカスの時間』という写真集をご存じだろうか(河出書房新社刊)。1980年にオリジナルが発表され、2013年に再刊された本橋成一による貴重な昭和の旅芸人たちの記録を、本メルマガでは2013年に詳しく紹介した。ご存じのように本橋さんは写真家・映画監督であり、東中野ポレポレ坐のオーナーでもある。そのポレポレ坐で今月14日(きょう!)から25日まで、『天幕の見世物小屋、サーカスの時間』が開催される。

photography
ホテルニューマキエの、おピンク・クリスマス!
田岡まきえ(現・マキエマキ)の写真を本メルマガで初めて紹介したのが2016年2月10日号(「自撮りのおんな」)。そのときマキエさんは50歳の誕生日を迎えたばかりで、セクシー自撮りを始めてから1年も経っていなかった(前年10月末のグループ展が初お披露目)。それがいまや! あっという間にツイッターのフォロワーは15,000を超え、その作品の過激さにしばしばアカウント停止をくらう「インスタ垢バンクイーン」として熟女シーンに君臨する存在に。これまで主な発表の舞台は自身のSNSや、展示にあわせてリリースされる自費出版の冊子やポストカードだったが、年明けには初写真集の商業出版も予定されている。そういう、いろんな意味でホットなマキエさんの個展『ホテルニューマキエ ♥マキエクリスマス♥』が、おなじみ板橋のカフェ百日紅で29日からスタートする。

photography
つめたくてあたたかい浴槽
たとえば「道に寝てる酔っ払い」とか「田舎の案山子」とか、ひとつのテーマをしつこく追い続ける写真家を、このメルマガではいろいろ紹介してきた。2014年10月22日号「浴槽というモノリス」で特集した牧ヒデアキさんは、路傍にうち捨てられたポリやステンレスの浴槽をしつこく撮っている「浴槽写真家」だ。牧さんは1971年生まれ。三河湾に面した愛知県西尾市で、建築設計の仕事をしながら、2009年から写真を撮っている。これまで何度か展覧会を重ね、小冊子をつくり、とうとう自費出版で写真集『浴槽というモノリス』を発表することになった。届いた写真集はA5サイズの小ぶりなサイズ、しかしポリ浴槽そのものの淡いブルーに丸く落とした角(何冊か重ねると浴槽のように見える!)、そして浴槽に溜まったお湯のように、表紙の写真にブルーの枠が糊付けされているという凝った造本だった。

photography
欲望の形の部屋
新宿駅西口から高層ビル街を抜け、中央公園を横切った通りに、ちょっと前までは真っ黒いお湯で知られた十二社(じゅうにそう)温泉があった。麻布十番温泉と同じように、西新宿の地元民にこよなく愛されてきた温泉がなくなったいま、表情の乏しい大通りに足を運ぶ理由はほとんどなくなってしまったが、通りに面したマンション内にビューイングルームを持つギャラリーYUMIKO CHIBAでは高松次郎から東恩納裕一、鷹野隆大までキャラの立った作家たちをいろいろ見せていて、今月は山本渉の『欲望の形/Desired Forms (2012-2017)』を展示中だ。山本渉(やまもと・わたる)は写真をつかうアーティスト。2013年に写真雑誌『IMA』から原稿を頼まれたのが彼の作品を知るきっかけだったが、高尚な写真評論が並ぶ中でなぜ僕に原稿依頼が来たかというと、そのとき取り上げた作品「欲望の形」が、オナホールの内部を石膏で型抜きした棒状の物体を撮影したシリーズだったから・・・だと思う。

photography
菊地智子「The River」とプリピクテジャパンアワード
不定期連載「菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド」で、重慶のドラァグクイーンや錯綜するセクシュアリティなど、いまこの瞬間にある中国のリアリティを伝えてくれてきた写真家・菊地智子さん。代官山ヒルサイドフォーラムで開催中のグループ展『プリピクテジャパンアワード2015―2017』に参加しています。聞き慣れない名前かもしれないけれど、プリピクテとはスイスの超名門プライベートバンク、ピクテ銀行が設立した写真賞。プリピクテジャパンアワードは――「地球の持続可能性(サステナビリティ)の問題に対して強いメッセージを投げかけている、優れた若手日本人写真家を支援することを目的にしています」(公式サイトより)ということで、2015年以来2名の受賞者を出しています。菊地さんはその第1回目(2015年受賞)、2回目が2017年の志賀理江子さん。

photography
菊地智子が歩くチャイニーズ・ワイルドサイド vol.3 ネオンライトの下の葬式~パフォーマンス化する死(写真・文:菊地智子)
初めて行った中国重慶の郊外で行われていた葬式に私は度肝を抜かれた。僧がお経を唱える声、葬式儀式用の楽器の音、音楽バンド、泣き女が大声で泣く声、爆竹、花火、博打の音、麻雀の牌のじゃらじゃらという音、様々な騒音が同時に会場を駆け巡り、まるでお祭り騒ぎの喧噪で沸き立っていた。葬式用の花輪や装飾が並ぶ派手な会場は、私の想像していたモノクロームの葬式とは全く異なる原色の風景だった。トランスジェンダーの友人が、都市でのショービジネスから退き田舎の葬式でパフォーマンスをするようになったというのを聞き、彼女に会いに行ったのは2011年のことだった。ドラァグクイーンパフォーマンスが農村で?と半信半疑で葬式に足を踏み入れ、私は葬式の光景に圧倒された。

photography
猫に引かれて香港参り
香港の街に降りたって、さあお買い物!というときにまず本屋を探す、というひとは多くないだろうけれど、写真集のコーナーに行くと「昔と今の香港」みたいな地味な色合いの大型本が並ぶ中に、ひときわ明るくチャーミングな表紙のペーパーバックが山積みになっている。2016年の発売からずっと売れ続けて、もう5刷となっている『香港舗頭猫 HONG KONG SHOP CATS』がその一冊だ。書名のとおり香港の店先の、日本で言う「看板猫」を集めた写真集。作者のマルセル・ハイネン(Marcel Heijnen)はオランダ生まれ、香港在住の写真家である。香港島上環、骨董通りで知られる摩羅上街(キャットストリート)から石段を上りきった古い住宅街にある写真ギャラリー「ブルーロータス」(Blue Lotus Gallery)で、先月新刊のリリース記念展覧会を開いたばかりの彼と会うことができた。

photography
中国ラブドール製造工場訪問記
2018年4月18日号「ラブドール王国の宮廷写真家」で特集したSAKITAN。大阪をベースにラブドールの写真を撮ってはSNSにアップしたり、自費出版写真集をすでに数冊発表している、ラブドール・ピンナップのエキスパートだ。やはり2018年11月28日号で掲載した吉井忍さんの「Freestyle China 即興中国」の中国ラブドール写真コンテストで、SAKITAN氏が審査員のひとりとして日本から招かれたことが記事中で触れられていたが、コンテストのあとに広東省へと足を延ばし、いまや世界のラブドール市場を席巻しつつある中国ラブドール・メーカー2社の本社工場を見学、その様子を新たな写真集としてリリースしたばかり。ちょうど年末の冬コミ出店のために上京したSAKITAN氏をつかまえ、お話を聞かせてもらうことができた。中国の新興メーカーがどんなドールを作っているのかは、各社のwebサイトを見ればわかるけれど、どんなふうにドールを作っているのかは、なかなか見ることができないはず。写真と共に、インタビューをお楽しみいただきたい。

photography
顔ハメ看板ニストふたたび
「顔ハメ看板ニスト」塩谷朋之(しおや・ともゆき)さんに出会ったのは2015年のこと。その年の9月9日号で『穴があればハメてきた――顔ハメ看板ハマり道』と題して、そのころすでに顔ハメ歴数年のキャリア、作品数にして約2200点という顔ハメ看板写真コレクションを紹介した。中学でヤン・シュヴァンクマイエルと出会って映画の道を目指し、カリフォルニア・オークランドでパンクに浸っていた塩谷さんが、なぜに顔ハメにハマり、通勤カバンにもカメラと三脚を常備するまでになったかは、アーカイブから記事を読んでいただきたいが、その塩谷さんがこのほど久しぶりの写真展『顔ハメ看板ニスト 塩谷朋之「15年目の顔ハメ写真展』を開く。前回が2013年だったから、6年ぶりの写真展ということになる。

photography
消され者たちの歌
「垢BAN」という言葉にビクッと反応してしまったら、それはSNSのヘヴィユーザーである証だ。垢BAN=アカウントban(禁止)、すなわち投稿内容が運営会社の規約に抵触して、警告、投稿削除、そしてアカウント凍結とペナルティが課せられることを意味する。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムなどそれぞれ基準は微妙にちがえど、SNSを舞台に主張や作品を発信しているユーザーにとっては、当然ながらかなりの打撃となる。実は本メルマガもかつてフェイスブックの投稿が削除されたり、メルマガそのものに(おそらく)不穏当な単語が含まれるといった理由で購読者の手元に届かないといったトラブルを経験しているが、性的な表現を追求するアーティストにとってはいまや、日々が垢BANとの闘いともいえる。今月11日から神田のギャラリーCORSOで開催される『私たちは消された展 ―凍結削除警告センシティブな内容を含みます―』は、垢BANを食らった写真家9人と画家1人、計10人のアーティストによるユニークなグループ展なのだ。

photography
ラブドールが見た夢
「人間ラブドール製造所」という奇妙な写真撮影サービスがあると知ったのは半年ぐらい前のこと。すでにいくつものメディアが取材しているが、そのサービスを運営しているのが女性2名ということを知って、男である僕はよけいこころ乱された。ラブドールとはそもそも男の性欲に奉仕する機械なのに、そういう「もの」になりたい女たちがいて、それを生み出すのもまた女であるという、考えようによっては観念的淫蕩の極致(三島いわく)でありながら、その退廃の香りと、報道やwebサイトで見る「作例」の明るさが、なんだかしっくりこない。エロだけどいやらしくはなくて、でも健全とも言いがたい・・・そういう世界観がどのように生まれるのかと思っていたときに、縁があって運営のおふたりと会うことができた。「では製造所にいらっしゃい」と許されて向かった先は、東大阪・河内花園という「なにしてけつかんじゃい!」的濃厚河内文化の中心地。住宅街の片隅にその「人間ラブドール製造所」はあるのだった。

photography
地下台北の眼
先週号『圏外でつながった台湾』のなかで、台北きってのアンダーグラウンド中古レコードショップ「先行一車」で出会った大阪LVDB BOOKSのことを少しだけ書いた。LVDB BOOKSは大阪東住吉にあるインディペンデント・ブックストア。空襲で焼け残ったという古い住宅街の、築80年の一軒家を使って、しかし外からはまるで本屋とわからない店構えで営業しているLVDB――ちなみに店名はアキ・カウリスマキの映画『ラ・ヴィ・ド・ボエーム』の頭文字で、特に意味はないが、なるべく憶えにくい店名にしたかったとのこと――では、いま台北の若手写真家・陳藝堂(チェン・イータン)と、本メルマガ2015年7月22日号『写真の寝場所』で特集した大阪の写真家・赤鹿麻耶(あかしか・まや)の二人展を開催中だ。

photography
イギリスの出口はどこに
ニュースを読むたびに不可解さが増すばかりのブレグジット問題。いつまでも先送りしておくわけにもいかないだろうし、どうなるんでしょうか。長い友人である写真家・金玖美(Koomi Kim)さんは、いまやファッションやポートレートで大人気ですが、いまから20年ちょっと前にマガジンハウスで働きはじめ、POPEYEやan・anの写真を撮っていたころ知り合いました。当時から仕事のかたわら、バンコクに通ってキックボクシングのジムに入り浸ったり、変わった作品を撮影してましたが、2004年には忙しい出版社生活を終わりにしてロンドンに移住。4年間滞在したあと帰国して、フリーランス・フォトグラファーとして活躍中です。そんな金さんがこつこつ通って撮りためたイギリスの、ふつうの場所のふつうのひとたちが一冊の写真集にまとまって、今月末に発刊。あわせて写真展が開催され、僕との公開対談も予定されてます。当初は「ブレグジットの期限にあわせてリリース!」というつもりだったらしいのが、こんな混迷状態に突入するとは……笑。

photography
辻徹が見ていたもの
去年4月、ひとりの老写真家が亡くなった。ずっと好きなように写真を撮っていたのに、病を得てふんぎりがついたように死の3年前、最初の個展を開くまで周囲がどんなに勧めても「そのうちね」と微笑むだけだった。ひとと会うときはいつもお酒で顔を赤らめて、というよりお酒が入らないとしゃべれないくらいシャイで言葉少なで、するっと宴席に紛れ込んでいながら、お金を持たないこともよくあって、それを隣のひとが払ってあげることにだれも違和感を持たない、そんな辻徹(つじ・とおる)という写真家のことを、名古屋の小さなサークルの外で、どれだけのひとが知るだろうか。去年、佐藤貢さんの記事を書いた縁で(『漂着した人生』2018年9月12日号)、名古屋のギャラリーNao Masakiから展覧会の案内をもらい、載っていた小さな写真にこころをつかまれて追悼展を訪ねた。

photography
ダークサイド・オブ・顔ハメ(文:スナック・アーバンのママ、写真:らんちゃん)
らんちゃんと出会ったのは「マニアフェスタ vol.2」だ。約100組のその道のおマニアさんたちが思い思いに熱量たっぷりに自分たちのマニア道をプレゼンしているなか、すらっとしたきれいなお姉さんのブースがあって、彼女が「顔ハメ姿をパネルの裏から撮るマニア」、らんちゃんだった。って、いまさらっと書いてみたけど、正直、意味わからないですよね?(笑) なんだか気になってしょうがないので、らんちゃんの暮らす京都でじっくりお話を聞いてきました。百聞は一見にしかずなので、らんちゃんからお借りした裏ハメ画像と共にお楽しみ下さい。

photography
僕が鬼海弘雄になれなかったわけ
都心の病院の面会室は眩しいほどの陽射しが差し込んで、あっちのテーブルではパジャマの男たちが小声で密談しているし、隣ではものすごいハーネスに頭を固定されて微動だもしないおばあさんを、家族たちが取り囲んで楽しげにおしゃべりしてる。『PERSONA 最終章 2005―2018』を出してすぐ入院した鬼海弘雄さんは、パジャマ姿がむしろ自宅の起きぬけのよう。元気よく話す姿を見ていると、この面会室がやけにシュールな空間に思えてきた。ちなみに鬼海さんは十連休の終わりに無事退院されたので、ファンのみなさまはご安心されたし。ちょうど恵比寿の東京都写真美術館で展覧会『東京ポートレイト』が始まるタイミングで、筑摩書房のウェブマガジンで連載していた『東京右半分』のためにインタビューさせてもらったのが2011年。そのあとも立て続けに新刊が数冊出たり、展覧会があったりと活発に活動してきた鬼海さんが、この3月末に発表したのが『PERSONA 最終章 2005―2018』だ。

photography
なにげなく愛おしい街で――オカダキサラ新作写真集
2015年12月16日号「日々、常に」で特集したオカダキサラ。1988年生まれ、東京南葛西の団地に住み、美大と写真専門学校で学んだあと、不動産の写真を撮る会社に勤めながら、一眼レフに50ミリの標準レンズをつけて、東京中を歩きまわってはストリート・スナップを撮ってきた。2016年に最初の写真集『©TOKYO 全てのドアが開きます』を発表してから、3年ぶりとなる2冊目の自費出版写真集『©TOKYOはなぞのぶらりずむ』が4月にリリースされた。

photography
国ではない国を歩く――星野藍と未承認国家アブハジア
こちらは2018年11月7日号「夢は廃墟をかけめぐる」で特集した写真家・星野藍の写真展『未承認国家の肖像・アブハジア』が今週土曜からスタートする。「考えるよりも先に、足が動くタイプかもしれません。恐らく酷い放浪癖があります」と自称する彼女の、前回は共産圏の廃墟をまとめた写真展『共産主義が見た夢の痕』を紹介したが、今回フィーチャーされるのは「未承認国家」。ナゴルノ=カラバフ共和国、沿ドニエステル共和国といった、国際社会からいまだ独立国として承認されていない地域のことで、廃墟とともに星野さんが長く取り組んできたテーマである。

photography
バングラデシュの地べたから
前項「二度と行けないあの店で」でコンニャク・カレーの思い出を書いてくれた梶井照陰(かじい・しょういん)さんは、佐渡島に暮らす真言宗の僧侶であり写真家である。これまで4冊の写真集を発表してきて、この5月に新刊『DIVE TO BANGLADESH』を刊行したばかり。今週末からは刊行記念写真展も開催される。また9月には瀬戸内国際芸術祭2019の秋会期に参加、高見島で瀬戸内の海をテーマとした新作『KIRI』を発表予定。瀬戸内海での撮影行から佐渡島に帰る途中に立ち寄った東京で、お話を聞くことができた。梶井さんのデビュー写真集『NAMI』が出たときのことはよく覚えている。2004年だったが、あのころの数年間、僕は木村伊兵衛写真賞の審査員をしていて、藤原新也、篠山紀信、土田ヒロミ各氏とともに、朝日新聞社の会議室に積み上げられた写真集を何時間も見ていて、そのなかに『NAMI』もあった。

photography
南さんはヘンな眼をしている
これまでずいぶんいろんな写真家の作品を紹介してきたけれど、じっくり語りたくなる写真と、「まあとにかくこれを見てください!」とドサッと写真を並べたくなる写真家がいる。南阿沙美の『MATSUOKA!』は、もう黙ってページをめくるのがいちばんいいんじゃないかと思う写真集で、これは「理解」とかそういうことではなく、写真家の感覚と共振できるかどうか、どこに行くのかわからないまま一緒に走っていきたいかどうか、それだけが好き嫌いの分かれ目になる作品の典型だろう。そして、こういう写真が僕にはいちばん撮れなくて、だから見たいけれど怖くもある。小説家は歳を重ねて円熟していくが、詩人は初心のころがいちばんいいと言われることがある、そんなことも思い出したりした。
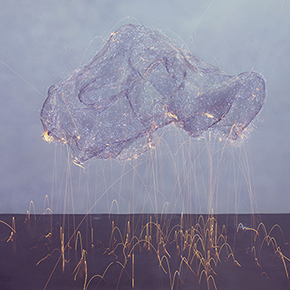
photography
Freestyle China 即興中華 網戸のメッシュが散らす命:写真家・仇敏業(チョウ・ミンイエ)(写真:チョウ・ミンイエ/文:吉井忍)
中国に『城市画報(City Zine)』という月刊のカルチャー誌がある。国内最大級のメディア企業「南方報業伝媒集団」を母体としていることもあり、他誌が出版不況を背景に停刊になったりオンラインに移行する中、なんとか耐え抜いて今年20周年を迎えた。個人的には10年以上前に北京のカフェで見つけたのが出会いで、その日は店にある同誌のバックナンバーを夢中になって読み漁った。音楽やアートに本屋さんなど、中国の若者の身近な話題に焦点を当てた誌面が、その頃はまだ珍しかったのだ。以来、新聞スタンドで見つけると買うようにしていたのだが(当時は隔週発行だった)、ある時ページをめくっていたらふと気になる文章を見つけ、切り取ってノートに挟んでいた。その文章を書いたのが、今回お話を伺った広州市在住の写真家、仇敏業(チョウ・ミンイエ)さんだ。

photography
博物学と写真の邂逅
タスマニアの本でもないかとシドニーの書店をネットで探し、ホテルのそばからバスに乗っていると、中心部のハイドパーク脇、古風な建物を通りすぎた。モノクロの動物写真のような展覧会ポスターが貼ってあるのが車窓から見えて、妙に気になったので帰りに寄ってみたら、それがオーストラリア博物館で開催中の『Capturing Nature』展だった。「1857-1895 オーストラリア博物館所蔵の初期科学写真」と副題のついたその展示は、19世紀後半から終わりにかけて、つまり写真技術がガラス乾板からフィルムに移行する直前の時期に、収蔵標本を撮影した最初期の科学記録写真展なのだった。

photography
わたしのからだは花の器
去年9月に東京藝術大学大学美術館で開かれた展覧会「台湾写真表現の今〈Inside / Outside〉」で出会った、台北の若い写真作家・許曉薇(シュウ・ショウウェイ)の『花之器』に衝撃を受けてから、まだ1年も経っていない。今年2月6日号では本メルマガに「Freestyle China 即興中国」を連載中の吉井忍さんに、台北でシュウさんを取材してもらったばかり(「緊縛する私たち」)。そのシュウさんが台北の写真ギャラリーで、初の個展を開くという。来月には大阪で、そして来年には東京茅場町のギャラリーKKAGで僕が担当する連続企画「都築響一の眼」でも登場していただく予定なので、その前にどうしても見ておきたくて、2泊3日で慌ただしく台北に行ってきた。ちょうどそのころ吉井さんも台北を訪れる予定があるというので、またもお願いして、さらにじっくりお話を伺ってもらうことに。

photography
それぞれの香港愛
香港はいったいどうなるんだろう・・・・・・と上海で考えた。6月のデモが200万人、きょう(8月19日)が主催者発表で170万人、と聞いてもピンと来ないかもしれないけれど、香港の人口は700万人ちょっと。実に全香港人の4人にひとりがデモに参加したわけだ。ちなみに東京の人口は1千万人弱なので、250万人が街に繰り出すって・・・・・・想像できます? そういう香港のこれからはだれにもわからないけれど、とりあえず僕らにできることは「香港を忘れないこと」だろう。騒乱の香港とともに、「いつもの香港」を見続けることだって大切なはずだ。
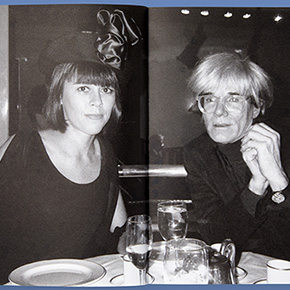
photography
ニューヨークが「ほかのどこにもない場所」だったころ
マンハッタン、ソーホーのすぐ北側、いまは「ノーホー(NoHo)と呼ばれるエリアに、「ダッシュウッド・ブックス」という小さな写真集専門書店がある。気をつけていないと通り過ぎてしまうような外観だが、店内には丹念にセレクトされた新刊・古書の写真集数千冊がストックされているほか、出版も手がけていて、日本人写真家でも荒木経惟の初期作品集や、今年は橋口譲二が1982年に発表した記念碑的な『俺たち、どこにもいられない』に、奈良美智のエッセイを添えて甦らせた『We Have No Place to Be 1980-1982』もリリースするなど、かなりエッジのきいた本づくりを続けている。編集者のひとりに日本人女性がいることもあってダッシュウッドと数年前に知り合い、それから新刊案内のメールが届くようになったのだが、2~3ヶ月前だろうか、『Paige Powell』という箱入り豪華写真集の新刊お知らせを受け取って、エエーッと思わず声が出た。

photography
ペイジ・パウエル「ビューラ・ランド」展、開幕!
先々週号「ニューヨークが「ほかのどこにもない場所」だったころ」で特集したペイジ・パウエルの写真展「BEULAH LAND」が、先週末にドーバー ストリート マーケット銀座で開幕した。ドーバー ストリート マーケットの1階には「エレファントルーム」と呼ばれる小部屋がある。中央にイギリスの立体作家ステファニー・グエールによる巨大ゾウが鎮座するガラスの空間が、今回の展示室。ゾウは半透明スクリーンで囲い込まれ、壁面すべてと床面に約3,000枚のプリントを貼り込められて、なんだか80年代に直結するタイムカプセルに飛び込んだ気分にさせられた。壁面のあちこちには無料のポストカードが仕込まれていて、好きなものを持って帰れるようになっている。

photography
失われた京都を求めて
「ニュイ・ブランシュ」は毎年10月初めの週末にパリで開催される「徹夜のアート・イベント」。こういうのはほんとうにパリが羨ましいところだよなあ・・・・・・と思っていたら、パリと姉妹都市である京都でも「ニュイ・ブランシュ京都」が京都市とアンスティチュ・フランセ関西(昔は「日仏学院」でしたね)が共同開催されるようになって、今年は10月5日の土曜夕方から、京都市各所で開催される。その関連企画のひとつとして、なんと二条城で開催されるのが甲斐扶佐義初回顧展『京都詩情』。このメルマガでも何度か登場している甲斐さんは元「ほんやら洞」店主、いまは木屋町でいちばん汚いとされる(誉めてるつもり!)「Bar八文字屋」の店主であります。

photography
死体が見た夢 ―― 東大阪シタイラボを訪ねて
むかしから落語家や芸人、変人文化人などが「生前葬」を催す例は珍しくない。そういう、半分シャレとしての生前葬は自分よりも家族や友人知人など、むしろ他人のために開くといってもいいかと思うが、完全に自分ひとりのための生前葬を体験させてくれる場が大阪にある。今年2月27日号「ラブドールが見た夢」で特集した東大阪の奇妙な写真撮影サービス「人間ラブドール製造所」を覚えていらっしゃるだろうか。「人間をラブドールに仕立てる」ことのもう一歩先にある、さらなる「逆転変身」の取り組みとして、この9月から本格始動したのが「シタイラボ」。~~したい(want to do)でも、肢体でも姿態でもなく、死体のラボ。自分が望む「こんなふうに死にたい」という状況・場面を再現し、「擬似の死」として体験してもらうという、人間ラブドール化を上回るユニークで奇妙な写真撮影サービスなのだ。

photography
いまそこにいるイヴのために
「ラブドールの写真集をつくってるんです」と言われて一瞬、またかという気持ちになった。先々週、馬喰横山町KKAGで開催された石井陽子さんの写真展『鹿の惑星』トーク会場でのこと。話しかけてくれた青年はいかにも手づくりっぽい、薄い写真集を取り出してみせた。「SAORI」とタイトルがついているのは、オリエント工業の一番人気モデル「沙織」のことだろう。正直言ってあまり期待しないままページをめくってみると、そこにはめったに見られないラブドールの写真が載っていた。SAORIと名づけられてはいるけれど、この写真集の主人公はラブドールではなくて、ラブドールを愛するひとりの中年男なのだった。人造美女ではなくて、ラブドールと人間――サオリとナカジマさん――が交わした愛の記録が、写真と文章でつづられているのだった。

photography
黄金の町の「幸子」の幸はどこにある(写真・構成:兵頭喜貴)
本メルマガではもうおなじみ、9月25日号では「ラブドール誘拐事件」の顛末も特集した八潮秘宝館・館主の兵頭喜貴氏。その兵頭くんから「黄金町にすごいギャラリーができたのでメルマガでやってください! 俺が書きますから!」と連絡があり、「へ~、どんなところ?」とか言ってるうちに、いきなり写真と文章のセットが送られてきた。あれほどのマニアを、これほど興奮させるとはいったい・・・・・・。

photography
無限界の浜辺にて――山本昌男「手中一滴」展
「うちとしては異例の入場者数でした!」というロバート・フランク展を終えたばかりの清里フォトアートミュージアムで、山本昌男「手中一滴」展が始まっている。写真好きでロバート・フランクを知らないひとはいないだろうが、山本昌男という名前に頷けるひとがどれくらいいるだろうか。展覧会のお知らせをもらうまで僕も不勉強でよく知らず、チラシに載っている写真を見て「知られざる物故作家の発見か」と思ったら、なんと1歳違いとはいえ年下の現役写真家なのだった・・・・・・涙。美術館のスタッフによれば、館長の細江英公さんも「こんな昔の人、よく見つけてきたねえ」と感心したそうなので、その年代詐称というと変だけど、時代感覚の超越ぶりはかなりのものである。

photography
Freestyle China 即興中国 存在することの、一抹の不安――写真家・張克純インタビュー(文:吉井忍 写真[作品]:張克純)
先日訪ねた寧波の写真専門ライブラリー「Jiazazhi」で写真集を見せていただいている時、オーナーの言由さんから「これは黄河の流域を撮ったやつ」と手渡された一冊があった。よくある「われわれの文化を育んだ偉大なる河」を表現した風景写真かな……と思いつつページをめくると、予想とは違った世界が広がっていた。黄河ももちろん写ってはいるが、面白かったのはどの作品にも写り込んでいる人々の姿だ。荒廃しながらもまだ圧倒的なパワーを持つ中国の自然と、その中でどうしようもない自身の小ささを受け入れながら弾け散る人々の生命。この『北流活活(The Yellow River)』は四川省成都市在住の写真家・張克純(ジャンクーチュン)さんの作品集だ。

photography
失われた築地の磁場
築地の魚市場が豊洲に移転して1年が経った(2018年10月6日に営業終了)。江戸時代から日本橋の川べりにあった魚市場が(だから「魚河岸」)、関東大震災によって築地に移転したのが1923(大正12)年。1935年に現在の旧築地市場に施設が完成・稼動を始めたので、2018年まで80年間以上にわたって日本最大の取引高を誇る卸売市場として君臨してきたわけだ。これまで「場内」と呼ばれてきた業者間の競りや相対売の機能は豊洲に移ったわけだが、「場外」の店舗や飲食店は観光地としていまも賑わっているので、築地市場がまるごと消滅したわけではないけれど、やはり2018年までの「築地」とはもうまったくの別物だ。
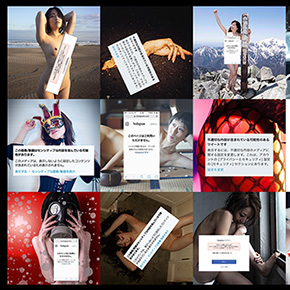
photography
私たちは消された展 2020
2019年2月6日号「消され者たちの歌」で紹介した『私たちは消された展』と、主宰の写真家・酒井よし彦さん。神保町のギャラリーで開かれた展覧会は、たった1週間の会期に900人もの観客が訪れたという。『私たちは消された展』はFacebook、InstagramなどのSNSに、性的な内容が「ガイドラインに反する」とされて、アカウントを凍結・削除・警告されてしまった表現者たちが集まって開いたグループ展。来場者は展示を撮影して「#私たちは消された」のハッシュタグをつけてSNSへの投稿を要請(強制?笑)され、それによって来場者までもが投稿削除されるという……なかなかに刺激的な観客参加型展覧会だった。予想をはるかに超える反響を受けて、2月3日からスタートしたのが『私たちは消された展 2020』。前回を超える16名の作家たちが参加して、より挑発的な喧嘩上等展覧会になっているはずだ。

photography
都築響一の眼 vol.3『許曉薇写真展 花之器』
東京馬喰町の写真専門アートギャラリーKKAGで連続開催している「都築響一の眼」。3回目となる「許曉薇(シュウ・ショウウェイ)写真展『花之器』The Vessel That Blossoms」が3月18日からスタートする。台湾の写真家・シュウ・ショウウェイについては2019年2月6日号「緊縛する私たち(文:吉井忍)や、去年夏に台北で開かれた展覧会リポート「わたしのからだは花の器」でも紹介してきた。2018年9月に東京藝術大学大学美術館で開かれた展覧会「台湾写真表現の今〈Inside / Outside〉」で出会ったのがきっかけで、去年は大阪でも展示があったが、東京での本格的な個展はこれが初めてになる。

photography
隙ある風景 2019 BEST50(写真・文:ケイタタ)
みなさまご無沙汰しております。昨年は念願の写真集を出版して、隙ある風景としても節目の年となりました。写真集の販売を通して「いつも記事楽しみにしてたよ」とか「ケイタタっていう名前を見て、うちの子の名前をケイタと名付けたんです」(←これ、まじ!)と言われまして、あ、がんばらなきゃ!と思いましたよね。というわけで、2019年のBEST50を選んでみました。もう2020年が4分の1ほど過ぎてしまいましたが、そこは大目に見ていただいて、いってみましょう。

photography
オカダキサラと2020年の日常写真
2015年12月16日号「日々、常に――オカダキサラの日常写真」で紹介したスナップ・フォトグラファー、オカダキサラの3年ぶりになる個展が、「許曉薇(シュウ・ショウウェイ) 花之器」に続いて馬喰町KKAGで4月8日からスタートする。ストリート・スナップといえば富士フイルム+鈴木達朗のCMが大炎上、公開後数時間で削除されるという情けない事件があったばかり。僕が写真を好きになったころは「キャンディド・フォト」なんて便利な言葉があったものだが、「出会い頭に勝手に撮る」という行為は、いまやなかなか難しい時代になってきた。僕自身も無許可撮影になってしまうことが少なくないので、今回の炎上は他人事ではない。相手が嫌がってるのに無言で逃げるというのはナシでしょ、というのが素直な感想だが、このジャンルにはニューヨークの悪名高いスナップシューター、ブルース・ギルデン(Bruce Gilden)という先人がいるので、イラつきたいひとは検索してみてください。

photography
地下鉄日記――東京砂漠の片隅で
『雲隠れ温泉行』という、つげ義春の世界が写真で21世紀に甦ったような写真集を2015年6月10日号で紹介した(「湯けむりの彼岸に」)。作者の村上仁一(まさかず)は月刊誌『日本カメラ』の編集者として働きながら、写真作家としても長く活動を続けてきた。『雲隠れ温泉行』を刊行したroshin booksは、このメルマガでも幾度か紹介した、斉藤篤という写真好きの青年が別の仕事で生計を立てながら、理想の写真集を世に出したいとひとりで始めたマイクロパブリッシャーである。そのroshin booksからこのほど村上さんの2冊目になる作品集『地下鉄日記』が刊行される(4月14日リリース)。

photography
フロントステップス・プロジェクト 玄関先でつながる世界
日本以外の多くの国が、市民に自宅に留まるようほぼ強制しているという、ほんの少し前まではサイエンスフィクションの世界でしかあり得なかった事態が現実化している現在。たくさんのひとたち、家族たちが孤立に物質的にも、精神的にも苦しむなかで、こころのつながりだけでもどうにかして保とうとする試みが世界中で行われている。決まった時間にバルコニーに出て、みんなで拍手したり歌をうたったりとか。ボストン郊外の町ニーダムに住む写真家キャラ・スーリーと、友人のクリスティン・コリンズが始めたのが「ザ・フロントステップス・プロジェクト」という素敵にアメリカ的な企画だった。

photography
ヤングポートフォリオ誌上展1
新型コロナウィルス感染防止のために、全国各地の美術館で展覧会の延期や中止が続いている。先月告知に書いたとおり、メルマガではおなじみ清里のフォトアートミュージアムでも、恒例の新人作家展「2019年度 ヤング・ポートフォリオ」が3月20日から始まる予定が開催できないまま休館が続いている。世界各地から35歳以下の写真家が応募し、選考委員が気に入った作者のプリントを、委員が選んだだけ買い上げて収蔵!という、世界でも稀に見る太っ腹な新人写真賞。今回は東欧、アジア全域から日本まで、ミュージアムによって購入された136点のプリントを一挙公開という意欲的な展示であり、2019年度の選考委員は川田喜久治、細江英公館長と僕の3人が務めた。

photography
ヤングポートフォリオ誌上展2
新型コロナウィルス感染防止のために休館状態が続いている、清里のフォトアートミュージアムで開催予定だった新人作家展「2019年度 ヤング・ポートフォリオ」。世界各地から35歳以下の写真家が応募し、選考委員が気に入った作者のプリントを、委員が選んだだけ買い上げて収蔵!という、世界でも稀に見る太っ腹な新人写真賞。今回は東欧、アジア全域から日本まで22名、計136点のプリントを川田喜久治、細江英公館長と僕の3人が選考、ミュージアムが購入することになった。2019年4月15日~5月15日の応募期間に寄せられた応募者総数152人、応募総点数3848点という大量の作品のうちから、選ばれた作家全員を紹介する誌上展。先週に続く後編では、選考会のあとに行われた委員3人による座談会と、先週紹介できなかった9名の作家をまとめてご覧いただく。

photography
もの言わぬ街から
休館を余儀なくされている美術館の興味深い企画展を誌上で紹介するシリーズ、というわけでもないけれど毎週お送りしている特集、今週は埼玉県東松山の「原爆の図 丸木美術館」で2月22日に始まったものの、新型コロナウィルス感染防止のために4月9日から臨時休館、残念ながらそのまま閉幕してしまった「砂守勝巳写真展 黙示する風景」を紹介させてもらいたい。 「黙示」とは文字どおり暗黙のうちに示される真理だが、「黙示の風景」とはいったいどんな風景が、どんな真理を示しているのだろうか。そもそも砂守勝巳とは、どんな写真家なのだろうか。

photography
我的香港 (写真・文 ERIC)
ERIC(エリック)という写真家をご存じだろうか。1976年香港生まれ、97年に来日してから写真を学び、道行くひとに大光量のフラッシュを浴びせて一瞬の表情を切り取る、独特のスタイルで知られるストリート・フォトグラファーだ。最初に彼の写真を知ったのは、僕が木村伊兵衛写真賞の審査員をしていたころだったので、東京を拠点にしたERICの活動もずいぶん長いことになる。そのERICがいまになって故郷の香港に目を向け、通うようになった。2014年の雨傘革命をきっかけに、いつものスタイルのストリート・スナップ、極小空間で暮らす人々、スーパーリッチ・・・・・・無限の差異を内包しながら、ひとつの巨大な生命体のようにうごめく香港という希有な都市に、彼なりの歩幅で飛び込んでいったのだった。昨年初夏から始まったデモの報道に接して、いてもたってもいられず東京との往復を繰り返した成果は、昨年末に緊急出版された写真集『WE LOVE HONG KONG』(赤々舎刊)に結実したが、ご承知のようにいま重大な局面を迎えている香港を、いまだからこそERICという眼を通して眺め直してみたくて、「我的香港」=マイ・プライベート・ホンコンのような短期集中連載をお願いした。

photography
我的香港 Vol.002 香港の住宅事情 (写真・文:ERIC)
2014年の秋に香港で起きた、雨傘革命。僕は、それをきっかけに、自分が生まれた香港を撮ってみたいと思うようになっていた。 ちょうどその少し前から、僕は実家に泊まることに居心地の悪さを感じていた。父と母が暮らすその家に泊まると、早朝、母が決まって寝ている僕を起こしにくる。 「飲茶に行くよ」 「あぁ?(またか……)」 香港では、昔から朝ご飯を外で食べる習慣がある。軽食メニューが豊富な喫茶店のような店<冰室>(ビンサッ)に行く人も多いけれど、僕の家では昔から家族で出かける馴染みの茶樓(飲茶をするレストラン)があって、物心ついた頃から毎朝のようにそこへ行っていた。

photography
我的香港 Vol.003 Wさんの肖像画 (写真・文:ERIC)
雨傘革命の撮影に一旦区切りをつけ、僕は一度、香港から東京に戻った。その3週間後の2014年11月、再びそのデモを撮影するために香港を訪れた僕は、友人であるジョン君の家に、また泊まらせてもらうことになった。 彼の家に行くと、前回訪れた時に彼が描いていた、Wさんの絵が完成していた。ジョン君がWさんを描いたその作品は、僕が知るいわゆる肖像画とはまるで違っていた。 「わっ! 何これ 笑」 青い空に光る無数の星と、宙に浮かぶ3つの惑星。輪がかかったその惑星の上には、それぞれ、ランボルギーニ、ネコ、チーターが乗っている。そして、真ん中に大きく描かれるのは、赤い水着とハイヒール姿で、プロペラ機に微笑みながら寝そべる、長い黒髪の女性。そう、Wさんだ。下には、チャイナドレスやスリッパの柄に描かれるなど、昔から香港の人たちに愛されてきた紅色の牡丹の花が咲き乱れている。

photography
我的香港 Vol.004 香港空撮 (写真・文:ERIC)
空から香港を撮影してみたい、という僕に、香港でヘリコプターの操縦を学んでいるWさんが紹介してくれたのは、Jさんという男性だった。Jさんは既にパイロットライセンスを持っていて、ヘリさえあれば空を飛ぶことができる。Wさんは、操縦士免許を取得するための教習を受けている香港ヘリ協会で、彼と知り合ったらしい。Jさんは、某有名ファストファッションブランドのベビー商品を生産する会社を経営する社長。僕と同じ年齢だけれど、香港の富裕層に属するセレブな人である。

photography
そこにあるコロナ
写真家・初沢亜利(はつざわ・あり)を初めて紹介したのは2013年1月23日号「隣人。―― 北朝鮮への旅」だった。 「緊急出版」という煽り文句はよく使われるが、これはそうとう緊急だなとまず驚かされたのが、初沢さんの新作写真集『東京、コロナ禍』。2月下旬から7月初めにかけて東京の街を歩きまわり撮影したコロナ禍の東京風景を142点、時系列に並べた写真集で、書店の店頭に並ぶのが今月20日ごろというスピード感。今回のコロナ禍を撮影した自費出版写真集やZINEのようなものは、うちにも届きだしているが、一般の商業出版ではこの写真集がたぶん初めての「コロナと東京の記録」ではないだろうか。

photography
「イルマタル」――岡部桃がいるところ
あの「まんだらけ」から写真集が出ると聞いて、瞬間的に思い出したのは2001年に出版されたカリスマ・コスプレ店員「声」ちゃんの緊縛写真集『人間時計』(本人の陰毛1本付き!)だったが、そういうのではなくて今回は岡部桃の作品集『ILMATAR』だった。薄くて軽い本ばかりが書店に並ぶなか、これはサイズが32.5X25.7センチ、革装ハードカバー、限定550部というずっしりヘヴィな作品集である。 岡部桃は東京に暮らす写真家だけど、日本の写真ファンにどれくらい知られているだろう。2013年と14年に出版された2冊の写真集は、いずれもニューヨークの出版社によるものだし、部数も少なかったから、ごく一部の幸運な読者しか手に取ることはできなかったはず。専門家の評価は高いけれど公式webサイトもなければ、いまネット上で読めるインタビューも英語版DAZEDの記事があるくらい。ミステリアスという言葉が適当かわからないけれど、その作風と同じくらい、活動のスタイルもきわめてパーソナルな作家であることは間違いない。

photography
ハッテンバの暗闇ドラマ ――山田秀樹写真展『映画館』
新宿御苑まわりに写真専門ギャラリーが集まっているのは、写真ファンならご存じかと思うが、ギャラリーごとに微妙なテイストのちがいがあって、瀬戸正人さんらが運営するPLACE Mではたまに、すごく変わった、ほぼ無名の写真家たちの展示が、しれっと紛れ込んでいる。基本1週間の展示なのでほとんど見逃してしまうが、8月30日(今週日曜)まで開催中の山田秀樹写真展『映画館』は、「都築さん絶対好きだから」と教えられて、今週号のメルマガに間に合うように急いで行ってきた。 成人映画館は最初から専門館だったところと、一般映画館が集客難で成人映画に鞍替えしたところがあるので、最盛期に何館あったかはよくわからないが、日本全国で数百館はあったはず。それがいまでは40数館を残すのみである。

photography
死者の反撃 ―― 事件写真家エンリケ・メティニデスをめぐって
慎重に再起動しつつあるニューヨーク在住の小説家バリー・ユアグローから連絡が来た――「僕らの大好きなメティニデスのこと書いたよ」。送られてきたリンクはイギリスの新聞オブザーバーのウェブ版で、「メキシコのウィージー」とも呼ばれた伝説の事件写真家エンリケ・メティニデスの活動と近況を伝える記事だった。ストリート・フードからルチャまでメキシコのポップ・カルチャーが大好きなバリーにとって、メティニデスの写真はただ衝撃的という以上の、特別な意味を持つものらしい。 僕がメティニデスのことを知ったのはまったく偶然で、2003年にロンドンのフォトグラファーズ・ギャラリーで『着倒れ方丈記/Happy Victims』の展覧会を開いたとき、同じ会場でメティニデスの個展も開催されていて、とてつもなくドラマティックな写真にいきなり魅了されてしまったのだった。

photography
我的香港 Vol. 005 我的親戚 (写真・文:ERIC)
今年の6月初め、この連載が始まると同時に、僕の父方の祖母が亡くなった。95歳だった。“僕は香港で生まれ、香港で育った、香港人である”と、連載の初めに書いたけれど、僕の両親は共に、元々は中国から香港にやってきた中国人である。彼らの親、つまり、僕の祖父母も中国の人。そう、僕には中国人の血が流れている。もしも生まれ育った場所が香港ではなく大陸(香港の人は中国を大陸<タイロッ>と呼ぶ)だったなら、僕も中国人と呼ばれることになっていただろう。 香港は、様々な意味で特別な場所だ。僕が生まれた時、そこはまだイギリスの植民地だった。僕が香港を離れ、日本へやってきた1997年7月に、香港は中国に返還された。けれど、香港人にとってこの地は、“香港”以外のどこでもない。

photography
鴨川べりの甲斐さん
ロードサイダーズではもうおなじみ、京都の公式ストリート・フォトグラファー甲斐扶佐義さん。9月9日配信号で告知したとおり、ただいま京都出町商店街周辺と、京都駅ビル内で「青空写真展」を開催中。青空、なのでもちろん常時オープン。常時無料。展示壁面の前を通りかかった地元のひとたちが、「自分も写ってるかも!」みたいに興味深く覗き込んでいる写真が甲斐さんのFacebookにたくさんアップされていて、そういう街とのつながりかたがすごく羨ましい。 出町商店街は初めて京都に住んだときにいちばん近かった商店街で、自転車でほぼ毎日通っていた場所だ。行列の絶えない和菓子屋とかもありながら、観光一色に染まらない、ローカルな空気感をいつも保ってきた、僕にとっては京都でいちばん大切な商店街でもある。 その出町を舞台に甲斐さんが大々的な写真展を開催するというので、連日の取材攻勢のあいまに「なんか書いてください!」とお願いしたら、さっそく出町と、甲斐さんが長く店主をつとめた喫茶店「ほんやら洞」の思い出を書いて送ってくれた。東京ともまた微妙に異なる、70年代の京都に特有だった、あの空気感をエネルギッシュな文章から感じ取っていただけたらと願う。

photography
すぐそこにある汚部屋と台湾 『Hoarders』黄郁修インタビュー (写真:黄郁修 文:吉井忍)
コロナのために延期となっていた「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭(KG)』が現在、京都市内で開催されている。今年で第8回目を迎え、会期は10月18日まで。新人写真家やキュレーターの発掘を目指した公募型アートフェスティバル「KG+」も同時開催されているのだが、ここからさらに審査をくぐり抜けた10組を展示するプログラム「KG+SELECT」があり、都築編集長によると、なんと台湾の”汚部屋”シリーズ『Hoarders』が選出されているという! これは行かなくては。 Hoarders(ホーダーズ)とは耳慣れない響きだが、実は我々にも身近な言葉で「物を過剰に溜め込む部屋で暮らす人たち」を指す。hoardは「貯蔵する」の意味、いわゆる汚部屋のような状態になるまで物を溜め込んでしまう行為はhoardingと呼ばれる。そしてこの『Hoarders』シリーズは、若き写真家・黄郁修(ファン・ユウシュウ)さんが、台湾各地を巡って見つけた汚部屋を撮影した作品だ。つい最近まで京都に住んでおられたが、現在は台湾に帰省されているとのことでzoomを通じて取材をお願いした。

photography
工藤正市の奇跡
ずいぶんたくさんの写真を日常見ていて、うまいとか、かっこいいとか思うことはよくあるけれど、こころ揺さぶられる出会いというのはなかなかない。 いま、インスタグラムを中心に共有の輪が静かに、世界中に広まっている工藤正市という写真家をご存じだろうか。1950年代にアマチュア・カメラマンとして積極的に活動したあと、ぱったりと作品発表を止めてしまい、2014年に亡くなってから家族が膨大なネガの束を発見。スキャンした画像をインスタにアップしたところ、驚くほどの反響を呼ぶようになったという、以前このメルマガでも特集したアメリカのヴィヴィアン・マイヤーやロシアのマーシャ・イヴァシンツォヴァにも通じる「発見の物語」である。

photography
我的香港 Vol. 006 返大陸 (写真・文:ERIC)
僕が香港の人たちに興味を覚え、写真を撮り始めたのは、5年ほど前からのこと。以降、僕は数ヶ月ごとに香港へ足を運び、街の中でスナップを撮り続けてきた。特に、昨年の6月から今年1月末の旧正月を迎えた頃までは、デモの撮影をするため、毎月のように香港を訪れていた。けれどその春節の時を最後に、僕はもう半年以上も香港に行けていない。理由は言うまでもなく、新型コロナウィルス流行のため。感染拡大防止策として、香港は日本よりも早い時期に、諸外国からの来港者の入境を禁止した。 僕がこんなにも長い間、香港に帰れないなんて初めてのことだ。デモはどうなっているのか、デモに参加していた若い子たちはどうしているのか、コロナ禍にある香港の街はどうなっているのかーー。SNSの発信やテレビニュースの報道からではなく、僕は今の香港に自分の足で立ち、自分の目でその事態を確かめたかった。

photography
ネオン管の抒情
アメリカの田舎のハイウェイを夜走っていたら、真っ暗な空にオレンジ色の巨大なネオン十字架が突然あらわれた。タイの村はずれにあるお寺の眩しい境内から本堂に入ってみたら、暗いなかに座った仏様を何色ものネオン光背が照らしていた。LEDがない時代の単なる照明器具なのに、ネオン管というものになにか神秘的な魅力を感じてしまうひとって、少なくないのではないか。 今年7月に大阪、9月下旬から10月にかけて銀座のニコンサロンで、下川晋平の写真展『Neon Calligraphy』が開かれた。カリグラフィーとは「書」のこと。おもにイランの夜の街を飾るネオン看板を撮影した、珍しいドキュメンタリーだった。

photography
バンコクのリカちゃん (写真:Sasamon (Didi) Amatyakul)
あまりInstagramは活用していないけれど、2年ほど前だろうか、不思議に魅力的な写真をフィードしているアカウントに出会った。「liccachan lover = リカちゃんラヴァー」というユーザー名のとおり、可愛らしい人形を撮影した写真がたくさん上がっているアカウントだった。 人形というと、アニメから派生したセクシーなフィギュアだったり、ハンス・ベルメールの球体関節人形的な耽美系だったりが僕の身近には多いけれど・・・・・・リカちゃんラヴァーの人形写真はそういうものとはぜんぜん違っていた。ただのコレクション自慢写真ではないし、かといって耽美系にありがちな闇/病みを匂わせる偏執も見えない。ローリー・シモンズのような現代美術系でもない。リカちゃんというくらいなのでほとんどが女の子人形だし、そこに官能性はあるけれど、ひねくれたエロスはない。「ガーリー」という言葉が当てはまるかどうかはわからないけれど、すごく真っ直ぐな、ある年齢の女の子だけが持つ強度がある気もする。人形なのに。

photography
我的香港 Vol. 007 逃港 (写真・文:ERIC)
僕は香港で生まれ育った。子どもの頃、学校が夏や冬の長い休みに入ると、僕は中国広東省の小さな町にある親戚の家に預けられた。ひと月ほどそこで過ごし、休みが明ける頃になると、迎えにきた父と母とともに香港へ帰る。 大陸(=中国)に行くことやそこでの生活、文化や習慣について、僕もまだ幼かった頃は特に何も感じていなかった。けれど、9歳、10歳、11歳……と年を重ねていくごとに、香港と中国の違いを徐々に感じるようになっていった。 自動車ではなくて、自転車に乗るの? 大人が地面に座ってご飯を食べてる! ゲームセンターのゲームの値段がこんなに安いなんて! はじめはただ無邪気に面白いと感じていたその違いに対して、いつからか優越感を抱くようになる。

photography
ハトの国から
2019年06月12日配信号「南さんはヘンな眼をしている」で特集した写真家・南阿沙美。仕事の同僚だったマツオカさんを撮った『MATSUOKA!』も、偶然友達になったOLを制服姿で撮った『島根のOL』も最高で、いきなり大好きになった。おもしろいけど茶化してるのではなくて、なんだこれと思うけど冷たくなくて。その南さんの写真展「ハトの国」が、かつて嬉野観光秘宝館があった佐賀県嬉野温泉の「おひるね諸島」で12月11日からスタートする。

photography
サバービア・ガーデニング ――前川光平「yard」を見て
去年と一昨年の2回、清里フォトアートミュージアムが主催する国際公募展「ヤング・ポートフォリオ」の審査員を務めたことは以前にもメルマガで書いた。現代美術的なアプローチの作品から社会派のドキュメンタリーまで、さまざまなスタイルで写真に取り組む若きフォトグラファーたちのなかで、いっぷう変わった数十枚のプリントに「ん!?」となった。 担当スタッフから詳細を聞くまでもなく、あきらかに日本の、それも伝統美とはまるで対極にある雑然とした庭先。玄関。塀や垣根まわり。そういう、日本のどこにでもありながら、だれも目に留めない光景が延々と現れる。

photography
モルドバの土に頬をつけて
2020年のヨーロッパの写真界でいちばん話題になったひとりにザハリア・クズニアがいる。しかしつい最近まで、どんな写真通でも彼の名前を知るひとはいなかったはずだ。なぜなら彼もまた「発見」された写真家だったから。本メルマガでは2015年にニューヨークのヴィヴィアン・マイヤー、2018年にサンクトペテルブルクのマーシャ・イヴァシインツォヴァ(リンク張る)、さらには2020年の青森の工藤正市と、死後発見されたアマチュア写真家を記事にしてきた(新聞社の写真部にいた工藤さんは正確にはアマチュアとは言えないが)。ザハリア・クズニアは彼らに続く、またも奇跡の発見物語である。

photography
我的香港 Vol.008 雲南 (写真・文:ERIC)
外国にいる日本人に向かって質問をする。 「あなたの故郷はどこ?」 おそらくほとんどの人は、躊躇うことなく「日本」と答えるだろう。「母国は?」という問いに対しても答えは同じである。日本人の大多数は、日本人の先祖をもち、祖父母も両親も自分も日本で生まれ、日本で育つ。 僕は香港で生まれ、香港で育った。それならあなたの故郷は香港でしょう? 大抵の日本人は僕にそう聞いてくるし、故郷=生まれ育った土地、と定義するなら、間違いなく僕のそれは香港ということになる。けれど昔から、僕はそのことに何か釈然としないものを感じていた。 僕の両親は、ともに中国大陸の出身である。広東省の小さな町に育ち、年頃になって出会った二人はやがて恋人同士となり、結婚を目前にして密入国という形で香港へ渡った。そこで生まれたのが、僕、というわけである。

photography
イッツ・ア・スモールワールド・・・・・・世界はひとつなのか
平安神宮に向かい合う京都市勧業館、通称「みやこめっせ」。大学の入学式やさまざまな大会、見本市、即売会などに利用されていて、地下には京都伝統産業ミュージアムなどもあるのだが、これまで足を踏み入れたことがなかった(名前もちょっと・・・・・・)。 その「みやこめっせ」地下・京都伝統産業ミュージアムで2月6日から28日まで開催されていたのが「イッツ・ア・スモールワールド:帝国の祭典と人間の展示」。市内各所を舞台に2010年から続けられている「KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭」の一環として開かれた、きわめて挑発的な展覧会だった。僕も閉幕直前に知ってあわてて駆けつけたので、開催中に記事を配信できず申し訳なかったが、その概要だけでも見ていただきたくて、企画者のインディペンデント・キュレーター小原真史(こはら・まさし)さんにお話をうかがいながら展覧会を振り返ってみることにする。

photography
隙ある風景 2020 (写真・文:ケイタタ)
ストリートに人が少ない。マスクで顔が見えづらい。ストリートを撮る写真家としては受難の2020年ではありましたが、今年しか撮れないものもありました。コロナ禍の選りすぐりの隙をどうぞご覧ください。

photography
CONTACT ZONE 砂守勝巳写真展
2020年05月20日配信号で「もの言わぬ街から」と題して、埼玉県東松山の「原爆の図 丸木美術館」で開かれた展覧会「砂守勝巳写真展 黙示する風景」を紹介した。本来なら丸木美術館の展示と並行して開催される予定だったのが、東京と大阪のニコンプラザでの写真展「CONTACT ZONE」。こちらは残念ながら新型コロナウィルス感染防止で延期となってしまったが、幸い4月13日から新宿のニコンプラザで、そのまま5月には大阪で開催されることになった。

photography
新連載! 妄想ホテル (写真・文:フクサコアヤコ)
写真家のフクサコアヤコさんと出会ったのは数年前。あるフェティッシュ・イベントだったか、フェチ話で盛り上がった酒の席だったか記憶が定かではないけれど、その題材も本人の存在感もすごくセクシーで、でも卑猥というのもちがう、エロいけど、どこか爽やかな微風も感じられる……女が撮る女のイメージに魅せられた。 そのときはラブホテルで、モデルに志願した女の子たちを「ひとりひと部屋」で撮影するというシリーズを見せてもらったのだが、最近久しぶりにお会いしたら「男の子も加えてホテル・シリーズを再開してます」と言われて、その場でメルマガで連載をお願いした。これから毎月いちどずつ、ひとつの部屋で、ひとりの女や男とフクサコさんが出会い、交わり、別れていく物語をお送りする。さて、そのひとりめは……。

photography
妄想ホテル room 002「東京」をあきらめると彼女は言った (写真・文:フクサコアヤコ)
今年の桜は早咲きで、春を待たずに散ってしまうような気がして落ち着かない日々を過ごしていた。そんな3月の終わり、一通のメッセージが届いた。 「東京を離れることにしました。最後に撮ってもらえませんか」 浅葉爽香、ラッパー、ポエトリーリーディング、詩を纏うキメラ、文字と肉体の表現者からの依頼だった。 彼女とは数年前、劇団の撮影を通じて知り合った。そして去年の夏、彼女自身からの依頼で彼女のミュージックビデオ「無修正ポルノ」に挿入するスチール写真を撮り下ろしていた。

photography
「portraits 見出された工藤正市」展@KKAG
東京東神田の写真専門ギャラリーKKAGで、2019年から開催している「都築響一の眼」シリーズ。「ラマスキー写真展 肌見の宴」(2019年4月)、「石井陽子写真展 鹿の惑星」(2019年9月)、「許曉薇(シュウ・ショウウェイ)写真展 花之器」(2020年3月)に続く4回目として、6月9日から「portraits 見出された工藤正市」展を開催させていただく。 メルマガ2020年10月14日号で特集した工藤正市は、これまでほとんどだれも知らなかった青森の写真家。亡くなった後に発見された膨大なネガを家族がスキャンして、1年ほど前からInstagramにアップを始め、いきなり世界に知られるようになった。 周囲の写真好きにも工藤正市はかなりの話題を呼んだが、「発見」から1年あまりのいま、青森市民図書館で「くらしのかまり 工藤正市が撮った昭和30年頃の青森市」というパネル展示が開かれてはいるが(6月30日まで)、本展は東京における工藤正市の初写真展となる。

photography
我的香港 Vol.009 我的劏房(写真・文:ERIC)
僕は香港で生まれ、香港で育った。数年前から、僕は香港の住宅、中でもまるで物置のように狭い部屋と、そこに住む人を撮影している(とは言え、新型コロナウィルスの影響で昨年の2月以降、香港へは帰れていないのだけれど)。部屋の写真を撮ってみたいと思ったのは、ヘリコプターに乗って空の上から香港の街を見下ろしている時だった。2014年の秋から冬にかけて、雨傘革命と呼ばれる香港の若者たちによるデモ活動を撮影するため、僕は頻繁に香港を訪れていた。その時、ある出来事をきっかけに出会った女性が、香港ヘリコプター協会なるものに所属していて、彼女の仲間が操縦するヘリに僕も便乗させてもらえることになったのだった。その翌年の初夏、僕は初めて香港の上空をヘリコプターから見下ろした(香港でヘリに乗るまでの経緯と空撮については本連載Vol. 003 & 004をご覧ください)。

photography
妄想ホテル room:003「もうこれで死んだ後のことを頼まれなくてもいいんだね」と彼女は言った (写真・文:フクサコアヤコ)
今回は少しプライベートな話をしたいと思う。 私フクサコアヤコが、ここ数年体験したこと、そしてそれをおそらく一番近くで見守っていたであろうモデルの話である。 長い間コンスタントに撮り続けているモデルがいる。名前はテレジア、商業コスプレイヤーでもある彼女はれっきとしたプロのモデルだ。 そんな彼女との出会いは7年前。 撮影の現場で何度か顔を合わせてはいたが、言葉を交わすほどではなかった。 そんな中、彼女がネットで見かけた私の作品を気に入ってくれて、私の出版イベントに来てくれたり、撮影中もいろいろ話すようになったりと、2人の距離は徐々に近づいていった。

photography
陽はまた昇る この東京デルタ
『東京右半分』とかつくったくせに、ふだんから浅草や錦糸町に入り浸ってるわけではぜんぜんなくて、コロナ禍になってからはよけい足が遠のいているが、久しぶりに東武スカイツリーライン(伊勢崎線)に乗って東向島に行ってきた。玉ノ井カフェで開催中のマーク・ロビンソン写真展『東京の水辺 TOKYO SHORES』を見に行くためだった。 東向島、なんて風情のない名前だとピンとこないが、玉ノ井カフェのあるあたりはその名のとおり、かつて東京屈指の売春地帯だった玉ノ井である。永井荷風が入り浸り、『濹東綺譚』などでしつこく描いた場末の私娼街。隅田川の東側にあるから「濹(墨)東」なので(隅田川は古くから墨田川とも書かれた)、地理的には隅田川を挟んで西側、つまり浅草側に由緒も格式もある吉原があり、東側に由緒も格式もない玉ノ井や鳩の街が位置していた。

photography
妄想ホテル room:004 「ここにあなたは確かにいるよ」そういう気持ちでシャッターを押している (写真・文:フクサコアヤコ)
今年の東京は梅雨入りが遅く、始まりそうで始まらない雨の季節を待ちながら、私は少し焦っていた。 もちろん雨が降らないことに対する焦りではない。定期的に訪れる「自分の写真このままでいいのか問題」にぶち当たっていたのだ。それに伴ってこの連載のテーマにも悩んでいた。 私は世間的には「エロい写真を撮る女性カメラマン」と思われている。 自分ではことさら「エロ」を意識しているわけではないのだが、比較的多めな肌色の割合と写真から漂う湿度のせいでそのように認識されているように思う。 そのおかげで撮ってほしいと言ってくださる人も一定数いて、妄想ホテルシリーズが存続している。

photography
新連載! ニュー・シャッター・パラダイス 01 ホームレストラン (写真・文:オカダキサラ)
ロードサイダーズではすでにおなじみ、東京の何気ない、でも思わず二度見せずにはいられない瞬間を切り取り続けるスナップシューター、オカダキサラ。コロナ禍にもめげず活発に動き回る彼女の新連載が始まります! これから隔週ペースでおおくりする「ニュー・シャッター・パラダイス」。名作「ニュー・シネマ・パラダイス」最後の連続キス・シーンのように、毎回ひとつのテーマを決めて、新作と膨大なストックからリミックス。バラバラの場面の隙間から、いつのまにか浮かび上がる写真物語をお楽しみください!

photography
妄想ホテル room:005 誰もが曖昧なまま生きている (写真・文:フクサコアヤコ)
梅雨が明けた。 今年は毎日雨が続く梅雨らしい季節だったと思う。そんな中オリンピックを控えた東京では4度目の緊急事態宣言が発令された。 飲食店には時間短縮もしくは休業が要請され、私も7月後半に予定していたイベントの中止を余儀なくされた。 そのイベントとは私が主宰を務めるPhoto’sGateという団体で定期的に行っている写真交流会のことである。 Photo’sGateの写真交流会は写真を撮る人、撮られる人、写真を使って何かしたい人がゆるく集まって交流する会で、もう10年近く続いている(現在は不定期開催)。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 02 さよならホーム (写真・文:オカダキサラ)
都心の駅では、日々たくさんの別れを見つけることができます。 電車を見送る親子、笑顔で手を振る学生、時間ギリギリまで見つめ合うカップル、握手を交わす男性たち、ハンカチで顔を覆いうずくまる女性… 駅構内で交わされるサヨナラの数は、私の一生分の経験をもってしても追いつきません。 人と人とが出会い、それぞれの時間を分け合い積み上げて、その先にあるのが「さようなら」です。 私は、最後のシーンにたまたま居合わせた通行人です。脚本で喩えるなら、起承転をすっとばして結末だけ見ているようなもので、登場人物の名前はもちろん、関係性も把握できていません。 それでも別れのシーンについ注目してしまいます。今まさにその人達の一章に、ピリオドが打たれようとしている特別な場面だからなのでしょう。 ホームでサヨナラを交わしている写真をまとめていて、別れの挨拶を面と向かってすることが、ここ最近少なくなっていることに気がつきました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 03 ハグシェルター (写真・文:オカダキサラ)
通行の妨げにならないように、互いに気を配らなければならない都会の往来。人々はスマホの画面を見たり、音楽を聴いたりして、窮屈さから気を紛らわせながら、足並み揃えて目的地へと向かいます。 そんななかでのハグは、人の流れを遮ることでもあり、かなり悪目立ちしているはずなのですが、通行人は彼らを無視して通り過ぎていきます。 その光景はいかにも東京らしく、私にとってはシャッターチャンスでもあります。 ハグをする彼らの腕の中にある「二人だけの世界」は、人混みの息苦しさから逃れるシェルターのようにも見えます。

photography
遠藤文香に聞く:オンライントーク誌上再現
8月22日の日曜夜、代官山蔦屋書店で小さな展覧会『Kamuy Mosir カムイ・モシリ』を開催中の遠藤文香(えんどう・あやか)さんとのオンライン・トークがあった。 告知にちょっと書いたが遠藤さんの作品を知ったのはこの春、東京藝大大学院の修了展を知らせる彼女のツイート。そのときは行けなかったのが、7月に初個展が丸ノ内KITTEであると知ってさっそく見に行き、感想をFacebookに書いたのを彼女が見てトークの相手に呼んでくれたのだった。初個展からわずか1ヶ月と少し。大学院の修了展からだってまだ数ヶ月なのに、もういろんなメディアが彼女の作品やインタビューを掲載しているし、ファッション・メディアなどでの仕事もアップされてきていて、注目度の高さに驚く。 トークの夜はフジロックの最終日、よりによって電気グルーヴとまるかぶりしたりで、あまり多くのひとに見てもらえなかったと思う。でも遠藤さんとのお話はとても興味深かったので、『カムイ・モシリ』以前につくられてきた作品などもたっぷり紹介しながら、トークの内容を紙上再現してみたい。

photography
アメリカから里帰りした京都の「色」気
7月末に京都に出張したとき、ホテルのロビーで小早川秋聲展「旅する画家の鎮魂歌」のチラシを見つけた。あの、戦死した日本兵の顔を日の丸の旗で覆った特異な戦争画《國之楯》で知られる日本画家。会場の京都文化博物館はホテルのすぐそばだったので、東京に帰る前に寄っておこうと足を運んでみると、まさかの開催前(8月7日から)……。入場券売り場で呆然としていたら、「戦後京都の「色」はアメリカにあった!」という展覧会のポスターが目にとまった。サブタイトルには「カラー写真が描く<オキュパイド・ジャパン>とその後」とある。せっかくなので入場してみると、予想外に興味深い写真ばかり! 70年前に撮られた京都の街は、もちろんいまとはちがうけれど、けっこう一緒だなと思える場所もたくさんある。そしていまは(コロナ禍前は)インバウンド観光客であふれていた場所に、そのころはジープに乗った進駐軍の米兵たちが闊歩している。街と人間、さらには地元のひとびとと兵士たち。妙な違和感と、でも観光都市という特性なのか、異質な人間が街景に溶け込んでもいるようで、すごく興味深い。焼け野原の東京からやってきて、空襲による破壊をほぼまぬがれて戦争前そのままの景観にいきなり踏み入れた兵士たちの興奮、タイムトラベル観光気分まで伝わってくるようだ。

photography
妄想ホテル room:006 人生はSM だけど今は少しだけハードモード (写真・文:フクサコアヤコ)
「人生はSM」。かつてそう語ってくれた女王様がいた。 新宿パラフィリアの女王、エリカ様だ。 日常のどんな出来事もSMに例えて「これはこういうプレイ」と割り切れば、人生は少しだけ楽しくなる、とそんな話をしてくれた。 私もなるほどなあと感心し、それからはちょっと大変なことやツラいことがあっても「これはそういうプレイ!」と自分に言い聞かせるようにした。そうしたらツラいことも少しは楽しめるようになった気がした。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 04 We are dancer (写真・文:オカダキサラ)
今回は街で見かけたダンサーを紹介します。 私はリズムにあわせて動くのが、とても苦手です。今でこそ「それはそれで私」と思えるようになってきましたが、他のひととリズムを合わせられないことに、焦りや悩みを抱えたこともあります。 リズムの共有はあらゆるところで求められます。その都度引け目を感じてる私でした。 学校の授業、会社でのコミュニケーション、カラオケ、カーテンコール、ライブやイベント、宴会の締めの手拍子…。 写真に写っているひとたちは、おそらく自分オンパフォーマンスが誰かの目に止まっているなんてことは、頭にないのでしょう。 彼らの中には、ぶれることのない、しっかりとしたメロディーが流れているように見えます。 そんな彼らから勇気をもらっているのは、撮影者の私だったりするのです。

photography
ただそこにいるひとたち ――二本木里美の2冊の写真集
薬局を経営していた父親のほぼ唯一の趣味が書店巡りだったので、小学生のころから日曜日になると神保町の古書店街に連れていかれた。時には大通り裏のすずらん通りやさくら通りにあった映画館で戦争ものや怪獣ものを見て、靖国通りを走っていた都電に乗って帰る小学生時代を送り、中学生になると自分で通うようになって……そのころから覚えている古書店のひとつが小宮山書店だった。 むかしは文学や哲学の難しい本が並んでいた覚えがあるが、いつのまにかアートやデザイン、それにアンダーグラウンドなテイストが強くなっていった小宮山書店に、先日メルマガでも紹介した根本敬の「画業40周年記念展」を見に久しぶりに立ち寄ったときのこと。階段状になった店内の、根本くんのひとつ下のフロアで展示してあった二本木里美という写真家の、ゲイボーイたちを撮ったプリント群にぎゅっと胸を掴まれた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 05 握手進化論 (写真・文:オカダキサラ)
この連載も今回で5回目を迎えました。 私は数字や記号を覚えるのが、とにかく苦手です。 前回の原稿を納品するときも「3回目です」と送ったところ「4回目ですよ」と指摘されてしまいました。 え!? もう4回も掲載させていただいたのか、とミスを恥じるより、驚きや嬉しさのほうがまさってしまいました。 自分のうっかりですが、サプライズをいただいた気分です。 この記事を読んでくださっている方々に改めて感謝申し上げます。 ありがとうございます。これからも頑張ります。 そんな記念すべき5回目は、手をつないだシーンを集めてみました。

photography
気配の写真――酒航太『ZOO ANIMALS』
中野のすぐ隣とは思えない静かな(ひなびた)新井薬師駅かいわい。もともと写真屋さんだった店舗を使ったギャラリー&バー「スタジオ35分」は、これまで何度もメルマガに登場してもらった。写真屋時代の看板の「プリントスピード仕上げ35分」から、「プリントスピード仕上げ」の部分を削っただけという「35分」のネオン看板。しかもギャラリーなのに夜しか開かず、隣接のバー(もとラーメン屋)との壁をくり抜いたのでギャラリーからそのままバーカウンターに移動・飲酒可能という、いろいろユニークなギャラリーだ。 店主の酒航太(さけ・こうた)は1973年生まれ、サンフランシスコ・アート・インスティチュートを卒業した写真家であり、自身の制作を続けながら、2014年からスタジオ35分のギャラリーを運営、カウンターにも立っている。

photography
妄想ホテル room:007 ハトが見たヒトの世界はロストコミュニケーション (写真・文:フクサコアヤコ)
子どものころ、フランスではハトを食べるということをテレビで知って、翌日公園のハトを捕まえて家に持ち帰ったことがある。 今考えたら諸々アウトだが、子供のすることである。もちろん親にこっぴどく怒られた。 流石に大人になった今では、公園でのんきにえさをついばんでいるハトは食べれたもんじゃないと理解しているが、それでもお腹がすいているときなどにはぎらぎらした目で見てしまう時もある。 そんな私とハトとの関係だが、偶然にも私にはハトの友人がいる。 たまにパフォーマンスに出てたりするが普段何をしているのかはよく知らない。そういえばヒッチハイクでNYへ行ったりもしていたな。 友人であるハト、豆山はハト目ハト科、学名はmameyama。

photography
顔ハメニストの憂鬱
展覧会のたびに顔ハメ看板を設置しようと提案しては学芸員を困らせている、僕もけっこう顔ハメ好きではあるけれど、このひとにはかなわないと思うのが「顔ハメ看板ニスト」をみずから名乗る塩谷朋之(しおや・ともゆき)さん。2015年に顔ハメ看板行脚の集大成的記録集『顔ハメ看板ハマり道』が刊行された際に、本メルマガでも「穴があればハメてきた――顔ハメ看板ハマり道」(2015年09月09日号)で紹介させていただいた。「おそらく日本でいちばん「顔ハメにハマった男」。これまでハマった穴が2千枚以上!」とそのとき書いたが、すでに6年前なので、いまは何千枚に記録を更新していることか……。 塩谷さんは『顔ハメ看板ハマり道』出版のあと、県別顔ハメ記録集として2019年に第一弾『顔ハメ百景 長崎天領ぶらぶら編』(阿佐ヶ谷書院刊)を発表。そして2年後の今月、第二弾『顔ハメ百景 青森最果てワンダー編 』をリリースした。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 06 ニューノーマルキススタイル (写真・文:オカダキサラ)
今回のテーマは「キス」です。 ドラマやアニメなどのキスシーンには、恥ずかしくて目を反らしてしまいがちなのですが、路上で見かけると5度見くらいしちゃいます。 唇を重ねるという優しい行為の裏には、「好きだ!」とか、「自分のものにしたい」とか、「愛おしい」とか、「かわいい」とか、そういった狂おしいほどの思いが詰まっています。 感情を抑え「理性的」に振る舞うことを良しとする往来のなか、こっそりと、または大胆に互いへのアツイ気持ちを確かめ合う姿に、いつも感動させられます。 しかし最近、以前よりキスシーンを見かけなくなってしまいました。 感染対策が徹底されている今、マスクをちょっと外してチュッとするのは、たしかにしらけてしまいますが、私としては非常に残念です。 この記事を書くにあたり、「キス」についていろいろと調べました。 なんと、愛するもの同士のキスは免疫力を高める効果があるというトピックを発見。マスクとキスは最強の感染対策であると医学的に証明されれば、今度は街中にキスシーンが溢れるようになるかも知れません。 そんなニューノーマル時代の訪れに、密かな期待を抱いています。

photography
我的香港 Vol.010 我的猫部屋 (写真・文:ERIC)
僕は香港で生まれ、香港で育った。 数年前から、僕は香港の住宅を撮影している。住宅と言ってもインテリア誌に出てくるようなオシャレな家ではない。僕が撮っているのは、狭くて暗い、まるで物置のような部屋だ。 香港という場所には、昔から華やかなイメージを持つ人が多い。ここ数年の間の香港の状況を思えば、その印象はもはやかつてのものとなってしまったかもしれない。しかしそれでもやはり、香港と聞くと今でもたいていの人は賑やかできらびやかな街の様子を思い浮かべるだろう。もちろんそれは間違った見方ではない。けれど、香港で生まれ育った僕にとってこの街は単なる日常で、過ごしてきた日々や目にしてきた光景は明るいことばかりではない。 香港の明と暗。それが最も表れているのが、住宅事情だろう。

photography
細江英公という怪物
ロードサイダーズにはもうおなじみ、山梨県の清里フォトアート・ミュージアムでは夏から「細江英公の写真:暗箱のなかの劇場」が開催中だ(12月5日まで)。戦後日本写真史のなかで、細江英公は重要な一章を占めるフォトグラファーであり、その膨大な作品群はいまもテーマごとに大小さまざまな展覧会が日本各地、また海外で開かれているが、今回は1960年代に取り組んだ、そして細江英公の名を世に知らしめたシリーズを横断的に、それも発表時(つまり約60年前!)のヴィンテージ・プリントで見せるという、細江さんとしてもかなり珍しい展覧会である。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 07 次回までお楽しみに (写真・文:オカダキサラ)
自分で自分にカメラを向けている様子は、初めこそ、ギョッ!としましたが、今となっては文化といってもいいくらいに世間に浸透しました。 若い方はもちろん、おじさんもおばさんもお年寄りも、自撮りを楽しんでいます。

photography
妄想ホテル room:008 二足のわらじで駆け抜けろ!人生を2倍楽しむ方法 (写真・文:フクサコアヤコ)
突然だが私はこう見えて(?)仕事人間である。 仕事と言っても写真の方ではなく、通常のオフィスワーカー、いわゆるOLというやつである。 私は専業カメラマンではない。写真を初めて20年以上になるが、常に写真活動と並行して写真とは別のフルタイムの仕事に従事してきた。 時には正社員として時には契約社員として、雇用形態を問わず基本的には月曜から金曜の日中はいわゆる「会社員」として写真とは関係のない仕事をしながら過ごしているのである。 このように昼はOL、夜はカメラマンとして常に二足のわらじで歩いてきた私であるが、常々仕事について思うところがあり、今回はそれについて語ってみたいと思う。 少々堅苦しい話にはなるかもしれないので、その分今回のモデル、謎のラバー美女ナマダメタボさんのクールなラバー姿とファニーな表情のギャップをお楽しみいただきながら読んでいただけると嬉しい。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 08 ひとりスポーツ (写真・文:オカダキサラ)
最近、エアスポーツをやりそうな人の気配を察知できるようになりました。 エアバッティングやエアピッチ、エアスイングなど電車やバスを待っている時や、次の仕事までの合間など、ちょっとした空き時間に楽しむ人が多いようです。 フォームの正しさや美しさについて、スポーツと縁がない私には分からないのですが、本人たちは思い描いている理想をなぞって動いているのでしょう。 最初は軽かった身の動きが、繰り返しているうちにだんだん真剣みを帯びていきます。

photography
Freestyle China 即興中華 世界を纏うステージ:沈昭良『STAGE』から (写真:沈昭良 / 文:吉井忍)
台湾の写真家、沈昭良(シェン・チャオリャン/Shen Chao-Liang)といえば、本誌でも何度か取り上げられている『STAGE』がまず思い浮かぶ。10年ほど前に発表されて台湾に一大“ステージブーム”を巻き起こした写真集だ。この沈昭良と同書について考察した論文『世界を舞台化する:異文化間の理解もしくは無理解、および台湾における移動式ステージ現象と沈昭良の作品について(※)』を、都築編集長から送っていただいた。 『STAGE』が台湾の人々に与えた影響を分析しつつ、あの華やかなステージトラックには彼らの世界観が凝縮されているとする内容だ。『STAGE』は海外でも評価が高く、私たちも外国人としてその作品を堪能することはできるが、この論文にある台湾の内部での受け止め方という視点は新鮮だった。

photography
よみがえる加納典明
11月3日配信号で清里フォトアート・ミュージアムで開催中の「細江英公の写真:暗箱のなかの劇場」を紹介した(12月5日まで)。88歳という細江さんは、さすがにあまり写真は撮っていないようだが、去年お会いしたときも気力充実、お元気な声を聞かせてくれた。細江さんは1933年という戦前生まれだが、戦後どころか戦中生まれの写真家で、いまでも現役バリバリで活躍しているひとがたくさんいて、写真家は特別に長生き人種なのかとつくづく思ったり。細江さんは別格としても、僕が子どものころに平凡パンチやアンアンで見知った写真家の御大たちが、いまでも元気にカメラを握っているのは驚異的というか、年下の写真家には脅威的というか。僕は長濱治さんとはPOPEYE時代に編集担当としてずいぶん仕事をご一緒したが、その長濱さんと高校の同級生というのが加納典明。荒木経惟とは別の方向性のスキャンダラスなヌード写真の数々で、このひと以上に一世を風靡した写真家はいないと思う。その加納さんがいきなり脚光を浴びることになった1969年のシリーズ「FUCK」が、発表から60余年の歳月を経て、初めてきちんとプリントされた写真展となって、いま天王洲アイルのYUKIKO MIZUTANIで開催中である。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 09 NO/ZO/KI (写真・文:オカダキサラ)
穴や隙間を見つけたら、なんとなく覗きたくなってしまうものです。 一説によれば、長い狩猟生活で身につけた本能によるものらしいとのこと。 「獲物がいるかもしれないから探ってみよう」という意識が何世代にも渡って受け継がれ、好奇心や警戒心として進化していったようです。 私はどちらかといえば、狭い隙間の向こうの景色よりも、そこを覗いている人たちの方に興味があります。 その様子を観察しているうちに、「その先に何があるんだろう」と気になり始めます。彼らの滞在時間が長ければ長いほど、私の探究心は増していきます。 彼らが去ったあと、「しめた!」と、私もワクワクドキドキしながら真似してみます。

photography
妄想ホテル room:009 闇から光へ。進化したきのことポリアモリーの話 (写真・文:フクサコアヤコ)
2021年も終わろうとしている。 4月にこの連載が始まり9人の方(ハト含む)とラブホテルの一室で濃密な時を過ごさせていただいた。 イケメンモデルとの疑似恋愛から始まり、ラッパー、アイドル、女王様、ハト、といろんな被写体を撮影させていただいた。実にバラエティ豊かな交流だったと思う。 そんな今年のラストを飾ってくれる被写体はきのこである。しかもただのきのこではない。闇から光へと進化を遂げたきのこである。 しかもこのきのこには恋人が複数いる。何のことだかわからないかもしれないが、今回も最後までお付き合いいただけたら嬉しい。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 10 走る! (写真・文:オカダキサラ)
年の瀬も近づき、慌ただしい日々を送っている方も多いと思います。 かくいう私も例に漏れず、あまりの忙しなさに、現実逃避してしまいそうなこの頃です。 普段落ち着いている師匠(僧)も、この月ばかりは目まぐるしく走り回ることから「師走」と呼ばれるようになったという12月。 ということで、今年最後の配信である「ニュー・シャッター・パラダイス」は「走る」をテーマにしました。 年末大放出で、写真をいつもより倍増して届けます。 楽しんでいただければ幸いです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 11 祝福のシャッター音 (写真・文:オカダキサラ)
ここ数年、お正月には早起きして、近所の公園に行くようになりました。初日の出を見るためです。 その公園は、規模に反して普段はひっそりしているのですが、この日はあたりがまだ暗い時間から賑わいます。 肌を刺すような寒さから、人々の抱く緊張や期待が伝わってくるようです。 カップルは身を寄せ合って暖かさを分け合い、子どもたちは興奮を抑えられない様子でご両親に何度も時間を訪ね、友人同士ははしゃいだ声を上げながら、東の空へと視線を向けています。 登り始めた朝日が夜空を美しいグラデーションで染める頃、そこらじゅうから祝福のようにシャッター音があがります。 長く続いた暗闇に、やっと光が差したかのような歓喜です。

photography
追悼:ラブドール写真家・SAKITANを偲んで
去年12月19日に101歳で亡くなったダダカン師のことをこのあいだ書いたけれど、11月29日に大阪のラブドール写真家SAKITANが亡くなっていたのを先週、関係者のかたのツイートで知った。1980年生まれだから、まだ40歳になってすこししか経っていない。ダダカンのように有名だったわけでも、朝日新聞に死亡記事が出たわけでもない、写真愛好家にすらほぼまったく知られていなかったと思うけれど、これほどラブドールにまっすぐな愛を込めて写真に写しとるひとはいない、僕にとっては大事な写真家だった。2019年、京都国立近代美術館からスタートした巡回展「ドレス・コード?―着る人たちのゲーム」でも、SAKITANさんの写真を数点、展示に使わせていただいている。

photography
妄想ホテル room:010 女の一生とセルフポートレート (写真・文:フクサコアヤコ)
2022年が始まった。新しい年になり連載も10回目となった。 今年もラブホテルの一室で、カメラのレンズを通して人の人生をそっと覗いていきたいフクサコです。 そしてその濃密な空気を記録し、少しでも皆様にお届けできれば。そんな想いで今年もがんばってまいりますのでお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。 さて、新年一発目のテーマはセルフポートレート。 実をいうと私自身はセルフポートレートというものが大の苦手である。 元々は写真に写るのが苦手すぎて撮る側に回っているうちに写真が人生の一部になってしまった人間である。そんな私から見るとセルフで撮れる人ってすごいなと常々思っていたし、どういう心持ちで撮っているんだろうという単純な興味もあった。

photography
「瀬戸正人 記憶の地図」
新宿御苑前を中心に写真専門ギャラリーがいくつも集まっているのは、東京の写真好きによく知られている。その中で僕がよく行くのがPlace Mというギャラリーで、ここは通常の商業ギャラリーではなく、5人の写真家による自主運営ギャラリー。展示会場のレンタル、ワークショップ、暗室レンタルなどを通じて、若手の写真家を育てる場をもう35年間も提供してきた。 Place Mでは土曜日の夕方に「夜の写真学校」というワークショップも開いていて、これも今年で22年目だそう。そのワークショップの中心になっているのが写真家の瀬戸正人だ。Place Mではメルマガで展覧会の取材を何度かさせてもらってきたほかに、瀬戸さんと2人展を開いたこともある。展覧会のオープニングや夜の写真学校の日など、たくさんのひとが集まる時間にPlace Mを訪れると、奥の小さなキッチンで大鍋の料理をつくってるおじさんと出会うことがあるかもしれない。それが瀬戸さんだ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 12 テンペンチーズ! (写真・文:オカダキサラ)
今回も人々が「覗いている」様子を集めてみました。 写真データを確認してみると、古いもので2012年秋に撮ったものがありました。 私は10年間も覗く人の姿を追っていたのかと思うと、驚きです。 スナップ写真を撮り始めて14年ほどが経ちました。 発表した写真について、「いつ撮ったものですか?」と、質問をいただくことがあります。ほとんど忘れてしまっていて、正確に答えることができません。 しかし2020年以降、新型コロナウイルスの感染が世界規模で広がっている今は、何年経った後でも撮影日を答えられると思います。 もうひとつ、記憶に深く刻まれているのは、2011年の東日本大震災です。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 13 のんべんだらり (写真・文:オカダキサラ)
自分の思考パターンを知りたくて、1年ほど前から日記をつけ始めました。 1ページが3段に分かれていて、全部書き終えたとき同じ日の過去を3年分見返せる仕様になっています。 iPhoneのリマインダー機能に「日記」というタスクを作ったことで、なんとか続けてこれました。 ところが、昨年の11月末に入ってから急に忙しくなり、日記を書くどころではなくなりました。 忙しないまま年末を迎え、時間ができたのはお正月休みのとき。2022年で初めて取り組んだのが、日記のページを埋めることでした。 この歳になって、小学生の夏休みの宿題みたいなことをやるとは…。

photography
暗く冷たい世界で熱を帯びるウィルスと僕ら――アントワン・ダガタ「VIRUS」
今年の初めごろには「日本人は清潔好きだし、コロナもそろそろ収束か」なんて呑気な気分だったのが、いまや緊急事態宣言再発出の瀬戸際に脅える毎日。そんななかで、2020年に新型コロナウィルスによってロックダウンされたフランスで撮影されたアントワン・ダガタの「VIURS」が恵比寿のナディッフアパート3階・MEMギャラリーで開かれている。2020年から世界各地を巡回しているこのシリーズの、日本では初の展示である。

photography
妄想ホテル room:011 女優という生き方~心の中に小さな女優を (写真・文:フクサコアヤコ)
ところで、皆さんには生まれ変わったらなりたいものはあるだろうか。 私にはある。私は生まれ変わったら女優というものになってみたい。 少女時代「ガラスの仮面」という漫画に夢中になった。北島マヤという天才的に演技の才能がある少女が様々な苦難を乗り越えて女優になる物語だ。 日本少女漫画史に燦然と輝き、今なお続いている驚異の演劇大河ドラマ。そう何を隠そう私はガラスの仮面世代のど真ん中である。 だが、少女ながらに自分は女優にはなれないとうすうす気づいてしまった私は、女優は無理でもせめて別の形で演劇の世界にかかわりたいと脚本(のようなもの)を書き始め、友達と演劇部の真似事をしたりしていた。 時は流れ大人になった私は案の定女優にはなれず、脚本も書けなかった。だが幸運なことに私には写真があった。舞台やイメージビジュアルの撮影などで夢であった演劇や舞台そして夢だった女優と関わるようになった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 14 ゲーム (写真・文:オカダキサラ)
私はゲームが苦手です。 中学2年生のときに、いとこからプレイステーションをお下がりでもらうまで、我が家にゲーム機はありませんでした。 もらいはしたもののゲームをする時間より使わない期間のほうが長く、いつもホコリを被っていました。 今はテレビゲームよりも、スマートフォンのアプリなどのほうが利用されているのかもしれません。

photography
現代アイヌの肖像 1
写真家・池田宏は2008年ごろから北海道に通い、アイヌのひとびとの生活を記録している。本メルマガでは2018年1月17日号「SIRARIKA 池田宏とアイヌ」で展覧会を紹介させてもらったこともある。2019年には10年間あまりの作品をまとめた写真集『AINU』を刊行。翌20年12月から写真展を東京で開催するはずだったが、新型コロナウィルスのためになんと2度にわたって延期という悲運に見舞われた。これからしばらくのあいだ、毎週!お届けするシリーズ「現代アイヌの肖像」は、宙ぶらりんの写真展を補完する誌上展覧会である。池田宏の写真、それに写真集の編集を手がけた盟友・浅原裕久によるテキストで、池田さんとアイヌのひとびとが共にした時間のかけらを体験していただけたらうれしい。

photography
現代アイヌの肖像 2 門別徳司
1982年生まれ/日高町(旧門別町)出身/平取町在住/猟師。 取材日:2019年3月12日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久 ── 門別君はどこの生まれだっけ? 門別 俺が生まれたのは両親が札幌に出てたときだけど、すぐにこっちに戻ったんだよね。門別町(現・日高町)の庫富(くらとみ)に。兵庫県と富山県からの入植者が多かったから兵庫の「庫」と富山の「富」を合わせた地名に変えたらしい。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 15 ネギ (写真・文:オカダキサラ)
買い物袋から、にょっきりはみ出してしまう食材があります。長ネギはそのひとつです。 日本人にとって長ネギはポピュラーな野菜で、我が家にとっても冷蔵庫に常にないと困る食材のひとつです。 日本では重宝されていますが、海外ではどうなのでしょうか。気になったので調べてみました。 どうやらスーパーマーケットに普通に置いてあるようです。

photography
現代アイヌの肖像 3 竹山明美
1991年生まれ/帯広市出身/帯広市在住/接客業。取材日:2019年7月25日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久 ──出身は帯広だよね。実家は大空団地? 竹山 そう。 ── 小学校は大空小? 竹山 小4から大空小学校。それまでは柏小学校だった。

photography
妄想ホテル room:012 不倫とは何か 愛の過剰供給説 (写真・文:フクサコアヤコ)
既婚者の約4割が不倫しているといわれている現代、私の周りにも夫以外の男性と関係を持っている女性は少なくない。 そして仕事がらなのか、単に話しやすいのか、そういうことを話しても大丈夫な人と認定されやすいのか、不倫話を聞かせていただくことが多い。 そんな中で前々から不倫には2パターンあると感じていた。 現状に不満があって現実逃避として不倫に走るケースと、何の不満もなく幸せな暮らしを送っているうえでさらにもっと刺激を求めてしまう恋愛欲(性欲も含む)が強いケースだ。 私はこれらのケースを前者を不幸型、後者を幸せ型と呼んで区別していた。

photography
現代アイヌの肖像 4 幌村真矢
1988年生まれ/三重県桑名郡出身/新ひだか町三石在住/漁師・配管工。取材日:2019年3月10日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久 ── 生まれは三石? 幌村 わけあって、三重県桑名郡の出身です。うちの父さんの母親のきょうだいが三重にいて、その孫が俺なんです。だから、父さんとも母さんとも血はつながってません。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 16 スポットライト (写真・文:オカダキサラ)
街灯は、ときに舞台の上のようなドラマティックな演出を通行人に仕掛けます。 当の本人は、ただ歩いていたり立ち止まっているだけなのですが、街灯が役者のような美しい仕草に仕立ててしまうのです。 東京都区内では、暗い道などないのではないかというくらい、街灯が設置されています。 デンマークからいらした方から「東京の夜の明るさを煩わしいと思ったことはありますか?」と訊かれたことがありました。東京の明るすぎる夜が不快かどうかなど、考えたこともありませんでした。逆に暗い夜道のほうが、私にとっては恐ろしいと感じます。

photography
現代アイヌの肖像 5 八谷恒二
1946年生まれ/旭川市出身/枝幸町歌登在住/配管工。取材日:2019年5月17日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久。── お生まれは旭川ですか? 八谷 生まれも育ちも旭川の錦町。── 当時、近所にはウタリの人が多かったですか? 八谷 俺が小さいころは、ほとんどウタリの人だった。10歳ぐらいのころにはシャモの人が入ってきたけどね。

photography
現代アイヌの肖像 6 川村兼登
1981年生まれ/旭川市出身/旭川市在住/木彫家・接客業。取材日:2019年5月17日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久。── お父さんが川村兼一さん、お母さんは和人の方ですか? 川村 そうです。── 兼一さんと同じく、お母さんも旭川のご出身ですか? 川村 そうですね。── 自分がアイヌだと意識しはじめた時期を覚えてますか?

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 17 バランス (写真・文:オカダキサラ)
危ういバランスで壁や椅子にもたれかかっている人たちがいます。休憩をしているようで、疲労も溜まっていくという矛盾スタイルです。 私も長旅のときはとんでもない格好で寝てしまって、起きたときの首や肩の痛さにしばらく動けないことがあります。 赤ちゃんが変な格好で寝ているのは微笑ましいのに、成人が同じようにしていると、その無防備さにかばんとか貴重品とか盗まれないのだろうかと、ヒヤヒヤします。

photography
現代アイヌの肖像 7 天内重樹
1985年生まれ/白糠町出身/白糠町在住/道路巡回員。取材日:2019年12月21日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久。── シゲの親の話から聞かせてもらっていいかい? 天内 母方がアイヌで、ばあちゃんは十勝の人なんだよね。母さんは白糠で育って、赤平や中標津にもいた。集団就職で内地にも行ったことがあるって聞いたわ。

photography
妄想ホテル room:013 「かわいい」の秘密 (写真・文:フクサコアヤコ)
季節はすっかり春。 春と言えば出会いと別れ、そして何といっても恋の季節である。 普段恋とは無縁の私でさえ風に散る花びらを見ながら移ろいゆく人間模様に思いをはせる、そんな季節が今年もやってきた。 春になると私には花粉症とともにもう一つ発症する発作のようなものがある。それは無性に「かわいい」が欲しくなるという発作だ。 こうなるとかわいいもの、かわいい人、かわいい服、かわいい食べ物…と、とにかくかわいいものに目が行くようになる。心と体が全力で「かわいい」成分を欲するのだ。

photography
現代アイヌの肖像 8 荒田裕樹
1985年生まれ/帯広市出身/白老町在住/団体職員。取材日:2019年12月18日、写真とインタビュー:池田宏、インタビュー構成:浅原裕久。 ── ご両親ともアイヌで、お母さんは白糠の人だよね。お父さんはちらっと何回かお会いしてて。 荒田 そうね。帯広のアイヌだね。それこそ父さんはさ、暴走族だから。生きてたら父さんの話を聞いても面白かった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 18 ぬいぐるみの呪い (写真・文:オカダキサラ)
私は一人っ子です。 幼い頃、兄弟がいない私にとっての遊び相手はたくさんのぬいぐるみたちでした。 ゲームや流行のおもちゃには関心が薄かったのに、ぬいぐるみへの情熱はかなりありました。 兄弟がほしいと思ったことがなかったのは、ぬいぐるみが寂しさを埋めてくれていたからかもしれません。 一つ一つに名前をつけるほど大切にしていたぬいぐるみたちでしたが、成長とともに見方が変わっていきました。 「大きくなってもぬいぐるみを持っているのは幼くて恥ずかしい」と思うようになり、中学に上る前に捨ててしまったのです。 ゴミ袋にぬいぐるみを詰める時の悲しさや切なさは、一つの呪いとなりました。 以降、かわいいぬいぐるみを見かけて懐が緩みそうになると、片付けていた時の痛みを思い出します。

photography
現代アイヌの肖像 9 西山涼
1996年生まれ/平取町振内出身/平取町振内在住/砕石場作業員。取材日:2019年11月16日/写真とインタビュー:池田宏/インタビュー構成:浅原裕久。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 19 傘がない (写真・文:オカダキサラ)
人間の最大の特徴の一つに、道具を作ることが挙げられます。 長い人類史と共に、道具は工夫を重ねられてきました。身近な例としては、カメラやテレビ、電話やコンピューターなどが挙げられます。 外観から大きく進化していったものもあれば、変化があまりみられないものもあります。 そのひとつが、傘です。 ジャンプ傘や折りたたみ傘など多少便利になりましたが、手で持たなければならない不便さはいつまでたっても解消しません。

photography
現代アイヌの肖像 10(最終回) 八谷麻衣
1982年生まれ/旭川市出身/札幌市在住/アーティスト。取材日:2020年10月19日/写真とインタビュー:池田宏/インタビュー構成:浅原裕久。

photography
妄想ホテル room:014 たまにはラブではないホテル (写真・文:フクサコアヤコ)
「○月○日 ○○ホテル、どうですか?」という短いメッセージが届く。 私は予定を確認してOKの返事をする。 たったこれだけのやり取りでここ数年撮影を続けている人がいる。 特にどう撮ってほしいとも、撮った写真が欲しいとも言われない。ただ「撮ります?」と連絡をくれるのだ。 ヒルトン、プリンス、マリオット、ハイアットリージェンシー、シェラトン、アンダーズ、椿山荘…彼女が宿泊するのはラブではない普通のホテル。しかも一度は泊まってみたい憧れのホテルばかりだ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 20 サンサン日傘 (写真・文:オカダキサラ)
5月。気温とともに紫外線もピークに向かって急激に強くなり始める時期です。 日傘をさして歩く人も多くなりました。 日傘には4千年の歴史があるといいます。初期の傘は高貴な人たちしか使えなかった上に、閉じることができませんでした。13世紀になって開閉ができるような仕組みがイタリアで開発され、18世紀にはヨーロッパ圏で一般人にも普及するようになったそうです。

photography
禁猟区の女神たち
神田馬喰町の写真専門ギャラリーKKAGできょう6月1日から「柊一華写真展 禁猟区」が始まる。2019年4月に「ラマスキー写真展 肌見の宴」で始まった連続企画「都築響一の眼」が、同年9月「石井陽子 鹿の惑星」、2020年3月「許曉薇(シュウ・ショウウェイ) 花之器」、2021年6月「portraits 見出された工藤正市」と回を重ね、今回が5回目となる。 一華さんと会うたびに、東京の夜の匂いってこういうのかと思う。 ホステス、風俗カメラマン、ギャラリーバー勤務、ミストレス、緊縛師、SMクラブオーナーまで、いろんな顔をして東京の夜の海を泳ぎながら、たくさんの出会いをカメラですくいとってきた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 21 三社祭り2022 (写真・文:オカダキサラ)
去年の三社祭はトラックにお神輿を乗せて町内を巡回したことで話題になりましたが、今年もまた違った工夫でお祭を開催していました。 本来であれば、3基あるお神輿は浅草神社を中心に、南側と西側と北側をそれぞれが巡回しますが、今年は台車にお神輿を乗せて、3基連ねて町内を巡回したのです。 たくさんのひと、ひと、ひと…。新型コロナウイルス感染拡大以降、こんなにもたくさんの人々が集まっている浅草を見るのは久しぶりでした。 コロナ禍であることを顔にかかったマスクがかろうじて示していましたが、それも初夏の陽気と祭の熱気にみんな外しがち。笑顔が溢れる下町は、とても魅力的でした。

photography
妄想ホテル room:015 妄想ホテル出張編~どこにでも行くよ、撮ってと言ってくれる人がいる限り (写真・文:フクサコアヤコ)
その日、私は甲府へ向かう特急かいじの中にいた。 ゴールデンウィーク終盤ということもあり下りの車内はそこそこすいていた。電車で食べる用に買ったお菓子を立川あたりで早々に食べ終わってしまった私はすっかり手持ち無沙汰になり、今回の撮影依頼のメールを読み返した。 「フクサコさんに撮ってもらわなきゃ自死するな、と焦燥感に駆られながらメッセージを打っています(いつもお願いするタイミングが重めですみません)。交通費もろもろお支払いするので、山梨で撮っていただけませんか」 昨年4月、「東京をあきらめる」と言って地元山梨へ帰ったラッパー、浅葉爽香からの依頼だった。

photography
盆栽という登山口に立って
旧知の写真家ノーバート・ショルナーがいまフランクフルトの応用美術館で「The Nature of Nature」という展覧会を開いている。いつもだったら現地で展示を見て記事をつくりたいけれど、まだ気軽にヨーロッパに行ける状況ではないし……と悩んでいた先月、ロンドンから鎖国明けの東京を訪れたノーバートに展覧会の写真を見せられ、少しでも早く紹介しなくては!と気持ちが焦った。 ノーバート・ショルナーはこのメルマガでも2012年07月18日号「サードライフにようこそ」、食品サンプルを美しくシュールな写真作品に仕立てた「食卓の虚実」(2017年05月17日号)など、何度か紹介してきた。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 01 ブルース・オズボーン(写真家)
今年で40年周年を迎えた「親子」写真シリーズでもっともよく知られる写真家ブルース・オズボーン。僕もずっと前にいちど、亡き父と一緒に撮ってもらったことがあるけれど、1982年にスタートした「親子」のプロジェクトは、もう3代目の親子を撮影することもあるという超ロングシリーズとなって、いまも続行中だ。 この春、高輪の泉岳寺近くにあるアダンという店で、ブルースのカリフォルニア時代の写真展を開いていると聞き、懐かしくなって足を運んでみたら、ブルースと奥さんの佳子さんと店主の河内一作さんが、まだ外が明るいうちから飲んでいた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 22 蛍光と電光 (写真・文:オカダキサラ)
ついつい口ずさんでしまう曲が私には2つあります。「ふるさと」と「蛍の光」です。 いつものように「蛍の光」を歌っていて、ふと私は蛍の光を見たことがないことに気づきました。気づいた途端、歌詞にあるように蛍の光は本が読めるくらい明るいものなのか確かめたくなり、先日千葉の清水渓流広場へと足を運びました。 清水渓流は、洞窟から差し込む光が水面に反射してハート型に見えると話題になった亀岩の洞窟がある観光スポットです。蛍の鑑賞地としても有名です。 役場の方から、羽化したばかりで蛍の数は少ないと事前に伺ってはいましたが、実際に見た蛍の光はなんとも儚いものでした。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 23 虹に流星群、オーロラ、そして花火 (写真・文:オカダキサラ)
新型コロナウイルス感染拡大から3年が経ちました。 2020年は正体の分からない疫病に誰もが怯え警戒していましたが、ワクチン接種が全国的に行き渡ってからはかつての日常に戻りつつあります。 とは言っても不安が完全に払拭されたわけではなく、今年も大きな花火大会は中止となってしまいました。 夏の風物詩はしばらく諦めるしかないかと、肩を落としたのは私だけではないはずです。 もっとも私は花火よりも、花火を眺める人々を観察する方が目的だったりします。

photography
妄想ホテル room:016 彼女の失踪 (写真・文:フクサコアヤコ)
土曜日の朝、こんがりと焼けたトーストとウインナーを、買ったばかりの小鳥の絵柄の皿に盛りつけた。記録のために写真を撮っておこうと携帯に手を伸ばして、メッセージが届いていることに気づいた。 「今日の撮影よろしくお願いします」。その日午後に撮影予定のモデルさんからだった。 2度のリスケを経ての今日の撮影である。しかし彼女を撮影するにあたって、撮影の中止やリスケは織り込み済みのことだった。 なぜなら彼女のプロフィールには、被写体をやっていることに加え、クローン病で体調が安定しないこともあると併記されていたからだ。 クローン病……調べてみると「大腸及び小腸の粘膜に慢性の炎症、または潰瘍をひきおこす疾患」とある。原因は不明、難病に指定されている。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 02 写真家への第一歩 ブルース・オズボーン(写真家)
仕事探し――アートセンター卒業後に直面したのが職探しだった。アートを専攻した学生誰もが経験する難関。一筋縄ではいかない。電話でアポを取り、大きなケースに入れた作品を持って写真家に会いに行くというのが、写真家を志す当時の学生の定番。ちょうど同じ頃に職探をしていた仲良しのDotとVivとも、彼女たちのアパートに詰めて一緒に仕事を探したものだった。電話をかける先は写真家に限らずアートディレクター、デザイナー、レコード会社、雑誌、その他なんでも可能性がありそうな相手に電話をかけまくった。電話をかける先は3人で共有。3人が5分刻みでかけるので、先方も不思議に思ったろう。当然アポの時間も同じような時間帯。アポが取れるとポートフォリオを抱えて作品を見てもらいに行ったのは懐かしい思い出で、楽しかったこともたくさんあったけれど、仕事はそんなにたやすく探せなかった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 24 もしもし言い訳もでんでん (写真・文:オカダキサラ)
2022年5月24日、アメリカ合衆国のニューヨーク市から最後の公衆電話が撤去されました。 ラジオから流れるニュースを耳にしたとき、私が思い出したのは前に勤めていた会社の先輩です。 彼は「公衆電話はいつかなくなると思うんだよね」と、公衆電話を見つけては携帯電話のカメラで記録していました。 10年前の話です。今でも撮り続けているのだろうかと、懐かしくなりました。

photography
どこにもない世界のうつゆみこ
ロードサイダーズにはおなじみ、中野区新井薬師前の写真ギャラリー(+カウンターバー)スタジオ35分でいま、うつ ゆみこ写真展『いかして ころして あたえて うばって』という奇妙な展覧会が開かれている。 うつさんは写真学校で講師を勤めたり、コマーシャルな撮影に関わったりしながら、自分の作品もつくりつづけていて、もう10数年にわたって個展、グループ展での発表、ZINEもたくさんリリースしてきた。今回の展示はそのタイトルが暗示するように生きもの(の死骸)をモチーフにした作品群。

photography
紅子の色街探訪記
ノスタルジックな遊郭や赤線の残景に惹かれるひとは多いが、8月1日に荒木町のアートスナック番狂わせで始まったばかりの写真展「紅子の色街探訪記」は、ノスタルジーとしての色街風景を並べながら、そこに仄かなノイズのようなものが含まれているようで、「色街写真家」と名乗る紅子さんのことが気になった。 「紅子の色街探訪記」は1ヶ月の会期のうち、8月1日から16日までの前半が「現代に生きる色街」、17日からの後半が「遊郭・赤線・花街の跡地」と題した前後半二部構成の写真展。紅子さんはこれが初めての写真展であり、展示にあわせてつくられた2冊の作品集も、初出版物だという。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 25 ワクワク ウェイティング タイム (写真・文:オカダキサラ)
私は1箇所にじっとしていることが苦手です。 行ってみたいお店でも、行列ができているとたいてい諦めて目的地を変更します。 そんな私ですが、人を待つことはそんなに苦ではありません。相手が来るまで散策を楽しめるからです。 見知った東京はもちろん、地方の知らない街を探検するのもとてもワクワクします。

photography
Freestyle China 即興中華 「上海」の遺影 写真家・席聞雷インタビュー (写真:席聞雷 文:吉井忍)
上海市がコロナ防衛戦の勝利を宣言したのが6月末、入国者が集中隔離される期間も以前と比べればかなり短くなったけど、気軽に行けるのはまだ少し先みたい……そんな折、都築編集長からお誘いを受け、上海市在住の写真家・席聞雷(シー・ウェンレイ)さんに取材できることになった。 席さんは長年、表門の枠を石で築いた中洋折衷型の建築「石庫門(シークーメン)」など、古い建築物や上海の昔ながらの町並みを撮り続けている。Instagram(アカウント名:Gropius Xi)でも一連の作品「Shangha!」を発表しており、海外のフォロワーも多い。 コロナ前の活気ある風景もあれば、2カ月にわたるロックダウン期間中のもの、上海人の細やかな生活の息遣いを残したまま廃墟になっている建物、瓦礫の山と背景の高層ビルが痛々しい対比になっている風景など、上海という大都市が見せる豊かな表情はいくら見ても飽きない。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 26 アカちゃんとワンチャンス (写真・文:オカダキサラ)
私がワンちゃんを怖がらず触れるようになったのはここ数年です。 幼い頃に受けた「犬」の印象があまりに悪かったのです。 友達とじゃれていたはずの野良犬がそのうちに本気になってしまい、なぜか私だけが追いかけ回されたり。従兄弟が飼っていた大型犬に吠えまくられ、鎖がちぎれんばかりの勢いで襲いかかろうとされたり…。 命の危機を覚えた出来事を経て、私は犬とは相性が悪いのかもしれないと考えるようになり、必要以上の間合いを保つよう心がけてきました。 距離を縮められたキッカケは、猫を飼い始めるようになってからです。

photography
妄想ホテル room:017 夏の始まり、ラブレター (写真・文:フクサコアヤコ)
ラブレターをもらった。 それは春の終わりのことだった。 そのころの私は定期的にやってくる「自信喪失期」に突入していて、もう写真など撮っても意味がないのだと毎日くよくよして過ごしていた。 そんな私にまるで救いの手を差し伸べるようにある日ラブレターが届いた。 それは、とある詩人から送られてきたメッセージだった。 そのラブレターには、「お忙しい中ただのラブコールですいません」という前置きの後、作品のファンであること、いつか撮られてみたいとひそかに憧れていたこと、そしてそんな気持ちだけでも伝えようと連絡してみました、と綴ってあった。 詩人ノミヤユウキ。彼女とはかつてある企画を通してコラボしたことがあった。 その企画で私は写真を、彼女は詩を担当していた。会ったことがあるのはたしか一度だけだったが一緒に作り上げたものが私たちの間には確かにあった。

photography
2022年の天野裕氏
今年になって二度、天野裕氏(あまの・ゆうじ)に会った。1月と6月、場所は東京の定宿である歌舞伎町東横インのロビー脇食堂エリア。小さなテーブルで新作の写真集を1時間ずつ、じっくり見せてもらった。 コロナ禍が始まって2年。「コロナでどう変わりましたか」というのはよく受ける質問で、僕自身は海外取材(とスナック取材)ができなくなったくらいでたいした変化も不便も感じなかった。でも「天野くん、どうしてるだろう」とは、ときどき気になっていた。天野くんはこの数年間、実は僕がいちばんすごいな、と思ってる写真家なのだ。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 03 オン・ザ・ロード ブルース・オズボーン(写真家)
アートセンターの学生だった頃から一緒に住んでいたいとこのボブと友人のビルの二人から、ヨーロッパとアジアへの旅行に誘われた。アートセンターはプロのクリエイターを養成するカレッジだけあって、いま思い出してもプロになって仕事を始めてからのほうが楽だと思うくらい、確かに毎日がハードだった。二人は、そんな宿題漬けの日々からエスケープしようという目論みのようだった。 僕は、PRM(フォノグラフレコードマガジン)の仕事がやっと軌道に乗りはじめたばかり。フリーランスの仕事も少しずつ入ってきたころで、最初はあまり乗り気ではなかったけれど、最終的にニッポンに行くという二人からの誘惑に勝てず、仕事を少し休んで世界一周の旅を選ぶことにした。 ニッポンに行ったら佳子に会える!

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 27 清掃員さん (写真・文:オカダキサラ)
私は学生時代20を超えるバイトを経験しました。 ころころとバイト先を変える私だったので、親や友人はさぞかし心配したのではないかと思います。 何より私自身が『この世には自分ができる仕事はなにひとつないのかもしれない』と怯えながら過ごしていました。 中には長く続けられた職場もあって、大手スーパーの厨房清掃もそのひとつです。 従業員は私を含め5人で全員女性。勤務時間は深夜なので昼間は別に仕事をしている方がほとんど、みんな家庭を持っていました。 私は学生だったので可愛がってもらいました。長く続けられた理由のひとつです。

photography
Freestyle China 即興中華 公園とホルモン:写真家・孫一氷 (写真:孫一氷 文:吉井忍)
コンビニに朝食を買いに行くついでに、近くの公園でラジオ体操に参加している。高齢者が圧倒的多数で、東京の片隅にある狭い公園を埋め尽くす勢い。お互いきちんと距離をとって体を動かし、「第二」が終わるとすぐ解散。静かに散り散りになっていく。しめやかな儀式のようだ。彼らに混じって公園を出る時、ふと中国の喧騒を思い出したりする。 中国の公園はいつも人が多かった。水を含ませた巨大な筆で地面に字を書く人、踊る人や走る人、昼はお手伝いさんが連れてくる子供たちで賑やかだし、夜は西瓜を食べたり機材持参で歌ったり、とにかく朝から晩まで勢いがある。読書や瞑想には向かないが、あの賑やかさも魅力ではあった。 北京在住の写真家・孫一氷(スン・イービン)さんによる作品『在公園(in the park)』には、そんな風景が地元民の目線で捉えられていて、懐かしくもあり新鮮にも思えた。

photography
妄想ホテル room:018 ハッピーエンドは終わらない (写真・文:フクサコアヤコ)
その日私は渋谷にいた。 人でごった返すハチ公広場を横切り道玄坂方面に向かう。 この日は夜から雨の予報だったが、スクランブル交差点上空の雲はギリギリのところで持ちこたえていた。 今日は外でも撮るだろうから、何とか最後まで持ってくれるといいな。 私は祈るような気持ちで暗い雲を睨むと振り切るように丸山町のラブホテル街へと足を進めた。

photography
ウェルカム・トゥ・ザ・ゾンビランド
秋葉原駅地下から出発するつくばエクスプレスで約1時間。終点のつくば駅で降り立ち駅前の公園を抜けると、茨城県つくば美術館がある。美術館と銘打ってはいるがここは県営の貸しギャラリーで、広々とした会場の半分で日本画の展覧会、もう半分で「わたし/わたしたちのウェルビーイング」というアーティスト13名によるグループ展が、9月13日から19日までの1週間、開かれていた。行った!というひと、どれくらいいるだろうか。 僕がこの展覧会を知ったのは、2021年01月06日号「サバービア・ガーデニング ――前川光平「yard」を見て」で紹介した写真家・前川光平が参加作家に加わっていて、前作「yard」では人家の奇妙な庭や玄関先を撮っていたのが今回は「案山子」がテーマということで、いっそう興味を惹かれたからだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 28 たちぐいそば (写真・文:オカダキサラ)
立ち食いそば屋が私のブームだった時期があります。 街歩きに疲れ小腹がすいたときは、決まって立ち食いそばの店を探しました。 都内の駅の近くにはたいていありましたし、店員さんとの距離感がとても心地よかったのです。 私は常連になることが少し苦手でした。 店員さんに「また来てくれたんですね」と声をかけてもらうとあたふたして、挙動不審になってしまうのです。 美容院などはその最たるもので、美容師さんが話しかけてくれるたびになにか答えなくては…と焦ってしまい冷や汗が止まらなくなります。帰るときは頭はさっぱりするのに反して、服はじっとり心はぐったりしていました。 コミュ障極まれり…

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 29 くまの子見ていたお尻 (写真・文:オカダキサラ)
アニメ・日本昔ばなしのエンディング「にんげんっていいな」が、動物視点で描かれた歌詞だと知ったのはつい最近です。 「くまの子はかくれんぼのルールを知らない。なのでお尻を隠しきれずに最初に見つけられた子どもを「1等賞」と勘違いしてしまったんだ。」 そう教えてもらって長年の疑問が解けました。 やるべきことが多くて頭がパンクしそうな私の横で、飼い猫のドモンがのんびり過ごしていると「猫っていいな」と羨ましくなります。 好きなだけ眠れて、ねだったらご飯をもらえて、キレイに毛を撫でてもらって、いるだけで人を和ませられて…実に快適そうです。

photography
portraits 見出された工藤正市 2
連続企画「都築響一の眼」として写真専門画廊KKAGで続けている連続企画の6回目「portraits 見出された工藤正市2」が10月12日からスタートする。 そもそも工藤正市の写真を知ったのが2020年の春。その年の初めから父・正市が遺したフィルムを長女の加奈子さんがInstagramにアップし始めてくれたおかげで出会えたのだった。家族にさえ隠していたという写真のクオリティにびっくりして、急いで連絡を取って取材させてもらい、2020年10月14日号「工藤正市の奇跡」で特集。そのあとKKAGで「都築響一の眼」vol.4 portraits 見出された工藤正市」として東京での初写真展を開けたのが去年(2021)6月のこと。9月にはみすず書房より『青森 190-1962 工藤正市写真集』も発売された。そして今回の2回目になる展覧会。Instagramに最初の写真がアップされてから3年にも満たない期間で、こんなふうに工藤正市の写真が広まっていく時間と場所に立ち会えたのは、ほんとうにうれしい。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 04 アフガニスタンからパキスタンへの旅 ブルース・オズボーン(写真家)
ポンコツと化して売るしかなかった愛車を処分した後の交通手段はマジックバス。運転手も乗客も個性的な人たちでそれなりに楽しい旅の仲間だったが、大きな問題はイスタンブールに到着するまでに何度故障をしたか覚えてないほどのポンコツバスだったこと。 それでもなんとかイスタンブールに到着したのは奇跡に近い。 アジアとヨーロッパにまたがる国、トルコ自治区の一つイスタンブールは、大陸の架け橋ともいわれる場所。 イスラム教徒の祈りの声や街の騒音が聞こえて、国境を越えたことを実感した。

photography
妄想ホテル room:019 人妻逃避行 世界旅行みたいなランデブー (写真・文:フクサコアヤコ)
「逃避行」という言葉には魔力があると思う。 人はいつだって逃げたい現実と向き合いながら生きている。 そんな生活に疲れ果てた時、ふと、すべてを捨ててここではないどこかへ行きたい衝動にかられたことが誰にでもあるのではないだろうか。 今回はそんな衝動に駆られた人妻の秘密の逃避行のお話。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 30 花やかな生活 (写真・文:オカダキサラ)
道を歩いているとふと金木犀の香りが…。 季節の移り変わりをこんなふうに道に咲く花で知ると気持ちが柔らかくなります。 花の形や芳しさは昆虫に見つけてもらいやすくするために進化したようですが、その魅力は人をも惹きつけます。 実は、私はまったく話さない子供でした。 同い年の子どもがどんどん言葉を覚えていくなか、親のこともろくに呼べずにいた私を両親や親戚はかなり心配しました。 親が発達障害を疑い始めた頃、出かけ先で咲き誇る花壇を私が見て「キレイねぇ…」とつぶやいたとか。それが私が初めて発した単語で、以降はどんどん話せるようになったということです。

photography
はじめての、牛腸茂雄。
写真好きのひとはとっくに知っているだろうが、渋谷PARCO8階(DOMMUNEスタジオの1階下)のギャラリー「ほぼ日曜日」で写真展「はじめての、牛腸茂雄。」が開催中だ(11月13日まで)。名前からわかるとおり、糸井重里さんが主宰するウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」が2019年から運営しているリアルスペース。今回の展覧会は「SHIBUYA PARCO ART WEEK2022」の一環で、館内のいろんな場所で展示などのイベントが行われている。 牛腸茂雄、という名前が熱心な写真ファンの外の世界でどれくらい知られているのか、僕にはよくわからない。そもそも牛腸を「ごちょう」と読めるひとがどれくらいいるだろうか。展覧会タイトルが示すように、この展覧会は「牛腸茂雄を知らなかったひとたち」にも、というかむしろ知らなかったひとたちに、予備知識なしに作品と向かい合ってもらおうという意図があるはずで、それは去年5月に同ギャラリーで開催された「はじめての森山大道。」から続く展示でもある。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 31 ふわふわのお供 (写真・文:オカダキサラ)
子どもの小さな手に繋がれた風船は、危うくてつい目で追ってしまいます。 人と人とに挟まれて割れてしまいそうになりながら、ふわふわと漂う風船。 子どもの頃はとても欲しかったアイテムですが、大人になった今では手にする機会がめっきり減りました。 というよりも風船を避けるようになりました。 風船を無料配布しているイベントもありますが、もらったとしても往来が多い中で割れないように気をつけるのは疲れますし、家には猫がいます。鋭い爪で破壊される運命を考えると、受け取る気にはなれません。

photography
妄想ホテル room:020 女体持ちのオートガイネフィリアと町田デート (写真・文:フクサコアヤコ)
新宿から快速で30分。 思っていたより遠くないのだなと思いながら、私はその日初めて町田の地に降り立った。 駅前は栄えており、その賑わいは神奈川県に間違えられる立地でありながらも確実に東京の郊外都市としての気概を感じるものだった。 さらに町田は宇宙人多発地帯でもあるらしく、行政による注意喚起のポスターなどが掲示されていた。不思議な街だなと思いながらも好感を持った私は待ち合わせのJR町田駅の改札へ向かった。 「撮影の日は女装していきますね!」という事前のメッセージ通り、待ち合わせ場所にはガーリーな服に身を包んだ彼女が立っていた。 それは私が知っていた彼女とはあまりにもかけ離れていたため、声を掛けられるまで彼女と気づけなかったほどだった。 女性なのに女装?と不思議に思っていた私だが、後に彼女がその言葉を用いた真意を知ることになる。 果たして人形のような彼女と合流した私はラブホテル街へと向かった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 32 とろける魅惑 (写真・文:オカダキサラ)
アイスクリーム。 口の中でとろける甘さが堪らないスイーツです。冷たさとそのあとに広がる甘さ。これは病みつきになります。 味のバリエーションも多く、特に地方に行くと奇抜な組み合わせに驚かされます。 アイスは好きな人も多いし冷凍して保管できる利点もあるので、自治体の商品化への判断も甘くなるのでしょうか。 地域活性化への情熱と期待と願いが込められて完成したご当地アイスは、中には食べるのを戸惑う商品もあり「無茶しやがって…」と、なんとも言えない気持ちになることもあります。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 33 微睡みが心地いいうちに (写真・文:オカダキサラ)
会社員を辞めてから2ヶ月経ちました。いちばん大きく変わったのは睡眠時間です。 5時くらいに自然に覚醒することもあれば、10時過ぎてもなかなか起き上がれないこともあったり…寝る時間は以前と変わらないのに、起きる時間はバラバラです。 めざまし時計で無理やり起こされていた時は気づきませんでしたが、体は日々変化しており必要な休息時間も一定でないらしいです。

photography
妄想ホテル room:021 「はだかは普通」ラブホテルの一室で全裸の人と友達になった話 (写真・文:フクサコアヤコ)
その日フクサコは悩んでいた。 私には年に数回、どうしようもなく写真を撮りたくなる時期がある。それはまるで発情期のように唐突にやってきて私を撮影へと突き動かす。そんな時は軽い気持ちでネットで相手を探したりする。今回も欲望のままにSNSに「軽率に撮影に誘ってください」と投稿したところ、本当に数名の方が軽率に誘ってくださった。 今回のモデルさんはその中の一人。圭子さんといって福岡で被写体活動をされている方だ。 今度東京に行く予定があるので、撮影しませんかー?とお誘いいただき、いいですねーしましょう!しましょう!とあっさり撮影が決まったのだ。 そしてここで私はある問題に突き当たった。 実はこの圭子さん、「はだかは普通」というスローガンを掲げて活動されている、裸多めのモデルさんである。いや、裸多めというか、むしろ裸が基本のナチュ裸リストさんなのである。 一方の私、エロとその界隈を取り扱う作家でありながら、基本的に全裸は撮らない作風。厳密に言うと全裸はOKだが乳首とヘアーはNGというマイルールがある。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 05 インドでの洗礼 ブルース・オズボーン(写真家)
冒険の旅を続けてきた三銃士の一人、いとこのボブは大学生活に戻るためにイランのテヘランを最後に帰国。ビルと私の二人旅となった。まるでバットマンと相棒ロビンかサイモン&ガーファンクルを連想させるような二人。アフガニスタンでは「不思議な国のアリス」のうさぎのように穴に落ちたと思うような経験を、インドでは、映画「オズの魔法使い」のドロシーがドアを開けた1シーンのような不思議な感覚の体験をした。 イラン、アフガニスタン、パキスタンと、保守的な生活習慣と地味な色になじみかけた後に訪れたインドは、まるでビートルズの「マジカル・ミステリー・ツアー」を彷彿させる感覚。新しい音、色、匂いに満ち、イスラム教徒、シーク教徒、ヒンズー教徒、さらに外国人も混ざり合う混沌とした国。最初は、そんな多様性に順応するのに戸惑ったが、明るくカラフルなものと暗く神秘的なもの、穏やかさと騒々しさ、豊かさと貧しさ、静かな感情とエモーショナルでハイテンションに変化する感情に慣れ親しんでいくにつれて、自分の中で何かが変わっていくような気がした。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 34 スルスル~看板 (写真・文:オカダキサラ)
都心部の街並みは広告で構成されているようなもので、カメラのシャッターを適当に切っても必ずどこかに看板が映り込んでいます。 一つ一つのキャッチコピーは秀逸なのに、多くの人は一顧だにしません。 宣伝効果をあげるため看板を持って声を上げている人もいますが、通行人は彼らの呼び掛けには応じず足早に去っていきます。 断るのなら一切応じないのが互いに最善の対応とはいえ、無視され続ける仕事はかなりキツそうです。

photography
TOKYO HEAT WAVE ――鈴木信彦と渋谷の20年間
2012年にロードサイダーズ・ウィークリーを始めて以来、たくさんの無名のアーティストを紹介してきたが、この11年間の出会いでもっとも印象深かった写真家のひとりが鈴木信彦。最初は創刊した年の2012年、10月17日号「センター街のロードムービー」で特集し、そのあと2017年、新宿ゴールデン街naguneにおける個展でも紹介した。 鈴木さんは2006年にオーダーによるフォトブックで部数50ほどの作品集を刊行しているが、2022年11月、初めて一般書籍としての作品集「TOKYO HEAT WAVE」を発表。刊行記念として1月9日からゴールデン街naguneと、刊行元である新宿1丁目・蒼穹舎ギャラリーの2カ所で写真展を開催する(写真好きが集まるゴールデン街のnaguneは朝鮮語で「さすらいびと、流れ者、たびびと」の意味、今年20周年を迎える)。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 35 ニュースぼつにゅうす (写真・文:オカダキサラ)
スマートフォンを使うようになって10年以上経ちました。最初はその手軽さ、便利さに感動しましたが、今となっては手が塞がるので邪魔になることも多く、スマホ機能を搭載したミラーレス一眼カメラの登場を心の底から待ち望んでいます。 私は重たい荷物を持つとすぐに肩こりや腰痛になるので、出かける際の荷物は最小限にしています。なので読書も本ではなくスマートフォン、特にニュースのチェックはほぼデジタルに移行しました。 新聞紙だと電車の移動中など周囲に配慮せねばならないことが多く、面倒なのです。

photography
妄想ホテル room:022 人との出会いは不思議 ホテルの部屋でお菓子のような甘い夜 (写真・文:フクサコアヤコ)
とある夜。ここは渋谷のラブホテル。 いつものように連載用の撮影のはずだった。 なのになぜ、私は今シャンパングラスを片手に、全身生クリームまみれで笑っているのだろう。 しかも私はいつの間にか見覚えのないTシャツ一枚という姿になっていた。下着はつけていない。 Tシャツと皮膚との間で人肌に温められた生クリームが行き場を失ってさまよっている。 そして私の目の前には同じく色とりどりの生クリームを身にまとい、私の肌に生クリーム越しに触れている女性。いったい彼女は誰なのだろう。目が合うと彼女はにっこりと笑って「キモチイイデショ?」と言った。 バスルームの赤いタイルに照明が反射して、視界がとろりと溶けた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 36 マナーの由来を学ぶ (写真・文:オカダキサラ)
「犯人はお前だ!」 と、探偵が人差し指を真っ直ぐ向けるポーズは、アニメや漫画では鉄板です。 小学生のころ友人同士でよく真似し合いました。イタズラがバレた時。持ち物を取り間違えていた時。ちょっとしたミスが露見した時。 今だ!と、一本の指を相手に向かって突きつけ、先のセリフを高らかに発します。指された方は「人に指を指したらいけないんだぞ!」と返す…ここまでがお約束な流れでした。 なぜ人に指を指すのがマナー違反なのか、と幼い頃は不思議に思っていました。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 06 インドでの洗礼/ ブルース・オズボーン(写真家)
色水を掛け合って春の訪れを祝うホーリー祭の日に、一緒に旅をしてきたビルを見送り一人旅が始まった アメリカをボブとビルと3人で出発してから早くも4カ月が経過。ボブが帰国して2人旅になりそして、カルカッタでのペイントフェスティバルの最中にビルを見送っての一人旅。放浪生活にもだいぶ慣れての気楽な旅の始まりだった。 カルカッタの喧騒をあとにネパールを目指そうと思ったが、その途中にインド北東部のアッサムやダージリンを経由することにした。ダージリンという名前の由来は、チベット語の「雷が落ちた場所」 だそう。背景にヒマラヤ山脈があり街を取り囲むように茶畑の丘が続く。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 37 ずっと太古から走っている (写真・文:オカダキサラ)
余裕を持って生きたい。 そう思って約束の時刻よりも前に現地についているように心がけてはいるのですが、何回かに一回は必ずギリギリになってしまいます。 事故や天災ならまだしも、原因は自分のウッカリによるものがほとんどなので言い訳のしようがありません。全速力で目的地に向かって走りつつ自分を罵倒します。 周りを見渡すと、大抵どこかに走っている人がいます。

photography
漁師町とタイワニーズ・キャバレー ――沈昭良写真展「續行」
台湾通いの再開に羅東を選んだのは、羅東文化工場という複合文化施設でいま、沈昭良(シェン・ジャオリャン)の写真展「續行=Continuance Journey」が開かれているから。沈昭良は台湾を代表するドキュメンタリー・フォトグラファー。ロードサイダーズでは2012年5月23日号での写真集『STAGE』の書評にはじまり、2014年5月21日号「移動祝祭車」など、彼が長年にわたって記録してきた「ステージカー」シリーズを中心に何度も紹介してきた。2021年11月17日号では連載「Freestyle China 即興中華」で、吉井忍さんによるステージカー研究者への長文インタビューも掲載している。昨年12月29日に始まった展覧会は、長さ114メートルに及ぶ中空のスカイギャラリーを使って、半分をステージカーのシリーズ「STAGE」、もう半分を羅東近くの南方澳(ナンファンアオ)漁港を撮影した「映像・南方澳」にあてて、1995年から2021年まで30年間近くに及ぶドキュメンタリーの仕事を紹介している。

photography
妄想ホテル room:023 高校教師がヌードになる。それくらい世界は自由で楽しいと知ってほしい。 (写真・文 フクサコアヤコ)
ある日一通のメッセージが届いた。 「来月東京へ行きます。また撮っていただけませんか」 地方都市で高校教師をしている女性からのメッセージだった。 彼女との撮影はこれが初めてではない。以前、学校の夏休みを利用して上京した彼女をラブホテルで撮影したことがある。その時も今回と同じように彼女はきっぱりと「ヌードでお願いします」と言った。 なぜ高校の教師がヌードになるのか? 不思議に思いつつも高校教師という言葉に甘い背徳感を覚えつつ撮影したのを覚えている。 話を聞いていくうちに彼女がなぜヌード撮影をしようと思ったのか知ることができた。 「高校教師がヌードを撮られるということ」にはAVのシチュエーションとは違う教育現場に立つ彼女なりの思いがあったのだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 38 アイラブ… (写真・文:オカダキサラ)
昭和ギリギリに生まれ、人生のほとんどを平成の中で生きてきました。 私が学生のころ、大きくなってからもぬいぐるみを持ち歩く女子は、「少女趣味だ」と認識されていた気がします。 「幼い」はもちろんですが、「女の子らしい」がついていたことに、腑に落ちない何かを感じていました。 このモヤモヤの原因が「性差」からくるものだと知ったのは、「ジェンダーバイアス」という言葉を聞くようになってからです。

photography
地底の闇、地上の光 ― 趙根在写真展
埼玉県東松山市、のどかな風景が広がる都幾川のほとりに建つ丸木美術館。正式名称を「原爆の図丸木美術館」というように、画家の丸木位里(いり)・俊(とし)夫妻が共同制作した『原爆の図』シリーズを常設展示する美術館である。1967年の開館からすでに開館56年目、いまも反戦・反原発など社会性を強く打ち出した企画展を開いている。アクセスがいい場所ではないけれど、その不便さがまた孤高の立ち位置を象徴しているようでもある。 ロードサイダーズでは2019年05月08日号「サーカス博覧会」、2020年05月20日号「砂守勝巳写真展 黙示する風景」など折に触れて紹介してきた。その丸木美術館ではいま、「趙根在写真展 地底の闇、地上の光 ― 炭鉱、朝鮮人、ハンセン病 ―」を開催中。これも丸木美術館ならではの企画展だろう。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 39 メイクアップ (写真・文:オカダキサラ)
お化粧を自発的にするようになったのは、社会人になって随分経ってからです。 すっぴんに自信があるからではありません。鏡を見る度に、コンプレックスに気付いてしまうのが苦痛だったのです。 特に、アンパンマンのような頬肉を心の底から憎んでいました。ニクだけに…。 とはいえ、お化粧に全く興味がないわけではなく、デパートのコスメブースを見るのは好きでした。 ある日いつものようにうろうろしていたところ、ビューティーアドバイザーのお姉さんに捕まってしまったのが、運の尽き。

photography
妄想ホテル room:024 タトゥー奇譚 女は海をさまよう小さな舟 (写真・文:フクサコアヤコ)
新宿ゴールデン街。その日私は難航していた仕事が少し進んだことに気をよくして、久しぶりに知り合い(と言っても毎週水曜日にカウンターに立っているという情報以外何も知らない)の店へと足を向けた。 週の中日とあってか22時を過ぎた店内に客は少なかったが、ゴールデン街においてはこれくらいが通常営業だろう。もっとも7~8人も入れば満席になる小さな店だ。仕事帰りのサラリーマンらしき人々が一人入ってきては一人出ていくといった様子をカウンターの隅でぼんやりと眺めながらグラスを傾けていた。 3杯目のグラスを受け取ったその時、一人の女が入ってきた。外は雨が降り始めたのか女は湿った空気を纏っていた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 40 レンズ越しの理想 (写真・文:オカダキサラ)
私がアニメ「セーラームーン」をテレビで初めて見たのは小学校に上がってからです。 どっぷりハマってしまった私を、両親がセーラームーン・ショーに連れて行ってくれたことがあります。 その舞台がどんな内容だったかは、もう思い出せませんが、登場したセーラー戦士たちが、アニメで描かれる姿と全く異なっていたことに、ひどくショックを受けたことは覚えています。 顔が異様に大きく、表情は全く変わらない。体もずんぐりしていて、衣装の部分はとにかく素肌の部分も不自然なシワが寄っている… そう。セーラームーンの着包みショーだったのです。 なぜ舞台とテレビで見る姿はあんなに違うのか… アニメと現実のギャップに、幼い私はひどく混乱しました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 41 ワン・ダブル (写真・文:オカダキサラ)
「わんちゃんとうまく接せられない」というコラムを以前掲載しましたが、嬉しいことに、あれからわんちゃんと触れ合える機会がたくさん増えました。 ROADSIDERS' weeklyには、書いた願望を叶えてくれる不思議な力があるのかもしれません。(ホントか?) まぁ、恐らくですが…、私の願いを察してわんちゃんが心を開いてくれた、わけではなく、そのわんちゃんと飼い主さんがいい関係を築けているからでしょう。そういう安心感があるから、初対面の私にも警戒することなく、愛嬌よく近寄ってくれるのだと思います。

photography
妄想ホテル room:025 懺悔 歌舞伎町やさぐれシスターへの告解 許されたい罪と揺れる真っ赤な嘘 (写真・文:フクサコアヤコ)
大都会東京、人々の欲望渦巻く歌舞伎町のはずれに、時折現れる懺悔バーがあるのをご存じだろうか。 そこはシスターアンネの懺悔バー。罪を背負った人々の前に気まぐれに扉を開くその店ではやさぐれシスターがあなたの告解を聞いてくれる。 懺悔したい人は懺悔をしてその罪を少しでも軽くすることもできるし、もちろんなにもせずだまって酒を飲むだけでも構わない。もちろんノンアルコールでもOKだ。 そこではただやさぐれシスターが静かに微笑んであなたの罪に優しく寄り添ってくれるのだ。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 07 ネパール ブルース・オズボーン(写真家)
ネパールの首都カトマンズは、 通称「ヒッピー トレイル」と言われていたヒッピーたちの旅の最終ポイントだ。 頭のなかで壊れたレコードのように流れていたのは、ボブ・シーガー&ザ・シルバー・ブレット・バンドの「カトマンズ」という名曲 。1975年にリリースされた「美しき旅立ち(Beautiful Loser)」の中の一曲だ。 日本にいる佳子に会うためにロサンゼルスを出発してから数ヶ月。 その頃の僕の心情にピッタリな曲だった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 42 ノーグッド・バイ (写真・文:オカダキサラ)
手のひらを相手に向けて振る仕草は、日本では「サヨナラ」や「ここだよ」という合図ですが、韓国では「めんどくさい」「あなたと関わりたくない」という意味で使われると知って驚きました。 他にも、親指を上に向けて立てて握る、いわゆる「いいね」や、人差し指と親指をくっつけて円を作る「OK」も、国によってはNGサインとのこと。 iPhoneの絵文字に登録されているので、世界共通なのかと勘違いしていました。 絵文字は元々は日本で開発されたもので、喜怒哀楽を1文字で表現できる便利さに、AppleとGoogleが注目し取り入れたようです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 43 ふっとんだ (写真・文:オカダキサラ)
落し物の多くは元の持ち主の手元に戻ることはないのでしょう。ずっと長いこと放置されている落し物もあり、その様子には飼い主を健気に待つ忠犬・ハチ公の逸話を重ねてしまいます。 中には、持ち主が困りそうな落し物もあり、その後どうやって家に持ち帰るのか少し心配になることも…。 ある日のことです。 悪天候やパッとしたない空模様が続いてましたが、やっと快晴が空に戻り、久々の絶好の洗濯日和となりました。 天気はいいもののかなり風が強く、バルコニーに並んだ洗濯物がずっとはためいていました。 住宅街を歩いていると、道路の真ん中らへんに、大きな影が不自然に落ちていました。 何の影だろう、と上を見上げてみると布団が電線に引っかかっていました。 「布団がふっとんだ!」と使い古されたダジャレが頭を過ります。

photography
妄想ホテル room:026 喪失とヌード 遺族として生きていくこと 彼女がヌードになる理由 (写真・文:フクサコアヤコ)
皆さんは親しい人を失ったことがあるだろうか。 それも突然に。続くと思っていた日常が、ある日突然ぷっつりと途切れる形で。 近しい人の喪失は大きな悲しみと同時に混乱をもたらす。自分の人生の意味を覆すほどの。 今回はそんな経験をした一人の女性の話だ。 私は初めて撮影するときに必ずする質問がある。それは「なぜヌードを撮られようと思ったのか?」という質問だ。 今回の被写体であるひかるさんの答えは想像をはるかに超えるものだった。 そこには生と死にまつわるリアルな物語があった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 44 またぐぎり (写真・文:オカダキサラ)
道路沿いに設置されている柵は視界を遮らず、けれど跨ぐとなると少し面倒という、絶妙な高さに設計されています。 きっと股下の平均値を参考にしているのでしょうが、中には高く感じない人もいるはずです。平均身長の高さは戦後から見ても右肩上がりなので、もしかすると柵はこれから徐々に高くなっていくのではないか、と私は思っています。
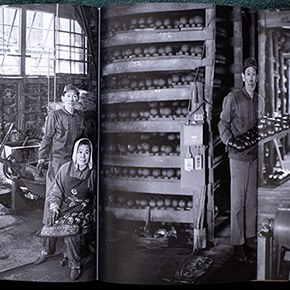
photography
山陰の記憶のとびら
ロードサイダーズ・ウィークリ−では2012年9月12日号「鳥取の店構え」で池本さんの記事を掲載して以来、写真展などの機会に何度か紹介させてもらってきた。鳥取市を訪れるたびにお会いするようになって、そのうち池本さんはロードサイダーズの記事をまとめたZINEのようなものまでつくってくれた。 その池本さんがいま入江泰吉記念 奈良市写真美術館で写真展「記憶のとびら」を開催中で、展覧会にあわせて最新作品集となる『On Display』が出版された。手元にその一冊があるが、なにかとコスト削減で世知辛い写真集が多いなか、異常なまでの手間暇と制作費もかけた力作なので、ここで紹介させていただきたい。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 45 夏予想(写真・文:オカダキサラ)
先日、久々に挨拶で握手を交わしました。 私は差し出された手に少し驚き、すぐには対応できませんでした。握手に慣れてないのもありますが、コロナ禍で人と距離を保つのが当たり前になっていて、触れていいのかどうか迷ったのです。 新型コロナウイルスの感染防止対策が解除され、東京の街も賑わいが戻ってきましたが、私はコロナ前と同じようには過ごせていません。 人との接触に気を遣ってしまいますし、電車や人が多い場所、屋内などではマスクを準備します。初対面の人とは「この人はマスクを外していい人?ダメな人?」と、距離感を探りつつ対応したり…。 マスク生活が身に染み込んでいたことを実感するこの頃です。

photography
妄想ホテル room:027 愛人という生き方 (写真・文:フクサコアヤコ)
何がきっかけだったかは覚えていないが子どものころから「愛人」という生き方にあこがれていた。 結婚というものに今一つ夢を持てなかった私は、将来誰かの愛人になって暮らすのも悪くないと自分の器量を棚に上げてぼんやりと夢想していた。 果たして大人になった私は、愛人になるほどの器量もないと身の程を知り、さらに愛人というものはどうやらそこまで楽な稼業ではなさそうだと気付き、愛人になるという夢は潰えた。けれど「愛人」という言葉の持つ甘やかな響きだけはかつての憧れとともに私の中に残っていた。 どうやら自分は愛人にはなれそうにないと気付いてしまった私であったが、忘れられない2人の愛人との出会いがあった。 いつかそのことについて書きたいと思っていたところ、ちょうどテーマにぴったりの方を撮影する機会があったので事情を話してモデルを引き受けていただいた。 前々から私が「こんないい女を愛人にしたい人生だった」と思ってやまないモデルのこのゑさんである。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 46 はい、ぽーず (写真・文:オカダキサラ)
レンズを向けられて、さっとポーズを取れる若者たちをよく見かけます。いくつか決めポーズを持っているらしく、撮られ慣れていることが分かります。撮って撮られることは、彼ら彼女らにとってはもはや日常なのでしょう。 私が小さい頃はフィルムカメラでの撮影がほとんど。写真を撮ることが今より手軽ではかったので、持ちポーズは「ピース」しかありませんでした。 家に積み重ねられたアルバムの中には、気恥しそうな笑顔に、覇気のないピースサインを添えた記念写真が残っています。

photography
Freestyle China 即興中華 山に向かって話すなよ:台湾写真家・黄煌智 (写真:黄煌智 / 文:吉井忍)
台湾の嘉義県にある阿里山。雲海と御来光、樹齢二千年を超える神木などで知られる自然豊かな国家風景区だ。台湾で原住民族に関する政策を専門に扱う行政院原住民族委員会によると、この一帯は古来から少数民族・ツォウ族の領地であり、彼らは今なお狩猟をしながら暮らしている。 写真家の黄煌智(ホワン・ホワンツー)さんは2022年から阿里山に幾度も赴き、そこで生きるツォウ族の若者たちの生活を撮り続けている。今回それを作品集『別向山説話:少年阿彬』にまとめた。タイトルにある“別向山説話(山に向かって話すなよ)”は、現地の若者たちが黄さんを戒めて口にした言葉による。

photography
川の流れのように | 写真:川(荒川晋作/関川徳之)・インタビュー:ロードサイダーズ配信チーム
神田駅前のごみごみした飲食街の片隅に店を開く「手と花(TETOKA)」。ギャラリー&カフェという業態自体が街の雰囲気から浮き立っているけれど、訪れてみれば妙に街並みになじんでもいる。「手と花」は日々の飲食営業とともに、店内の壁面を使った作品展示をつづけていて、これもまたギャラリー&カフェという語感よりもかなりアンダーグラウンドの香りが漂う、もちろん神田の酔っ払いサラリーマンともぜんぜん異質のラインナップで僕らを楽しませてくれてきた。実はロードサイダーズの配信チームとも縁が深い「手と花」。先週末から京都と金沢のスケートボーダー兼写真家が組んだプロジェクト「川」の展覧会が始まっている。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 47 無償の条件 (写真・文:オカダキサラ)
恥ずかしながら、学生時代は試食をするために、デパ地下や駅構内のお土産品売り場、物産館などをかなりの頻度で回っていました。 一口ずつ色んなものを食べられる、という魅力にドハマリしてしまったのです。頭ではもうやめようと思っていても、つい足が向いてしまうのを繰り返していました。 この悪癖に随分と悩まされましたが、社会人になるとお店を巡回する時間が取れなくなり、試食会場巡りから足が遠のくようになりました。 なにより、試食に行くたびに何かしら商品を購入していたので、お財布的にキツくなっていったのです。 「タダより高いものはない」は至言ですね…。

photography
once upon a time~もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 08 ビルマ ブルース・オズボーン(写真家)
ネパールに1か月半滞在後、飛行機でカトマンズを出発。ビルマのラングーンに到着した。当時(1977)は、ビルマ滞在の観光ビザは7日間だったから、今までに比べるとけっこう慌ただしい旅だ。 「地元で使うkyat(チャット)という通貨の為替レートが良くないから、入国前には空港の免税店でジョニーウォーカーレッドとタバコを購入するといい!」というアドバイスをほかの旅行者から聞いていたので、空港の税関でウイスキーとタバコを購入。その理由が分かったのは空港を出た直後のこと。ウィスキーとタバコを闇値で購入する人が近づいてきてすんなり交渉成立。おかげで、ビルマ滞在中の資金が捻出できた。

photography
妄想ホテル room:028 旅する写真。砂漠へと続く物語 (写真・文:フクサコアヤコ)
今回は旅する写真について書く。旅をするのは私ではない。写真である。 地球規模の災禍も収縮の兆しを見せ、人も物も再び動き出した世界。 街を歩けばそこここで見かける外国人観光客にインバウンドの戻りを感じ、SNSではちらほらと旅行の投稿を目にする日々。気づかないふりをして抑え込んでいた私の中の旅行欲がむずむずと騒ぎだすのを感じていた。 そんな中、私の写真を旅に連れていきたいという申し出があった。行先は砂漠。 この夏、どこかに行きたくてむずむずしている本人を差し置いて、私の写真だけが海を渡って砂漠へと旅に出るようである。 「ようである」と書いたのは、すでに写真は私の手を離れ、旅の準備に入っているからである。これからどうなるのかは写真が持つ自らの運命次第。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 48 夏の夢 (写真・文:オカダキサラ)
夏がやってきてしまいました。 我が家にはクーラーをつける習慣がなく、夏は窓を開けて自然風で過ごすか、扇風機をつけるかでこの季節を凌いでいます。 節約やエコのためというよりかは、クーラーを使う習慣がないのです。 身体中から吹き出す汗に不快感を覚えながらも、窓から入り込む風を頼りに、毎年暑さを耐え忍んでいます。 高齢者枠に入る家族と自分の健康を守るためにも、今年こそはクーラーを習慣化せねば…と考えてはいるものの、なぜか行動に移せず、もう7月も下旬に差し掛かろうとしています。

photography
Freestyle China 即興中華 路上の明るい白い世界:写真家・馮立(フェン・リ) | 写真:馮立、李弋迪(ギャラリー内部など一部) / 文:吉井忍
中国の写真家による二人展「閃境劇場(せんきょうげきじょう)」を鑑賞する機会をいただいた。場所は東京・新宿御苑の写真専門ギャラリー、Place M。参加アーティストは昨年本誌でも紹介した魏子涵(ギシカン)さん、そしてもう一方が成都市出身の馮立(フェン・リ)さん。魏さんは2022年に動物を写した写真展「情動の匂い」を東京で開催しており、今回の展示もその流れを汲んで動物をテーマにした構成となっていた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 49 夢の中の銃撃戦 (写真・文:オカダキサラ)
幼稚園の頃から定期的にみていた、忘れられない夢があります。 私は、理由もわからず軍人ぽいいで立ちのムキムキマッチョの外国人に命を狙われるのです。夢の中で私は彼のことをボブと名付けていました。 彼は銃やナイフだけでなく爆弾や機関銃、小型ミサイルなど、ありとあらゆる武器を使って私を殺そうと追いかけてきました。言葉を交わしたことは一度もありません。 私はたくさんの人を巻き添えにしながら、命からがら逃げまくります。友人の命と自分の命を秤にかけられることもあり、泣きながら起きた時もあります。 夢占いでは、殺されそうになって逃げる夢は、時間に追われてストレスが溜まっている状態が、これから変化することを意味しているといいます。

photography
妄想ホテル room:029 真夏のヌード・ラブホテル。被写体モデルの未来について思うこと (写真・文:フクサコアヤコ)
盛夏である。連日「酷暑」と表示されている天気予報に、酷暑って天気だったっけ?と首をかしげたくなる日々が続いている。 こんな季節はロケを避けて涼しいスタジオかラブホテルでしっぽり撮影するのが良い。 というわけで、今回のタイトルは「真夏のヌード・ラブホテル 被写体モデルの未来について思うこと」なのだが、キーワードを盛り込んだらさっぱり意味の分からないタイトルになってしまった。 まず「被写体モデル」という単語、最近よく見かけるが意味が重複していて違和感を持っていた。同じ意味じゃん!と。まあそれは今回は置いておくとして、このような謎タイトルになったのには訳がある。 今回モデルを引き受けてくださったのはRitaさん、実は前々からツイッターで拝見して素敵だなと思っていたモデルさんだ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 50 夏雲、引っ張り出す (写真・文:オカダキサラ)
「酷暑日」という言葉が予報用語として正式に採用されたのは去年のことです。 連日の天気予報を聞いていると、東京でも「酷暑日」は当たり前になる未来は近いような気がします。 ゾッとする話のはずなのに、背筋は凍るどころか暑すぎて汗がつたいます。 私の仕事は外歩きが大部分を占めるので、かなりツライ時期です。 一息つきたくても、外はどこも灼熱地獄と化しており、休める場所はありません。 寄りかかることも休むことも許さない夏の街は、外で働く人たちに厳しいです。

photography
Freestyle China 即興中華 ラブホがあぶり出す台湾 (写真:陳淑貞、黄郁修/文:吉井忍)
台湾の街を歩いているとたまに見かける「汽車旅館」の看板。米国のモーテル(motor+hotel)の直訳だが、必ずしも「自動車で旅する人向けの宿泊施設」を指すわけではなく、意味としては日本の「モーテル(つまりラブホ)」に近いことが多い。一部屋ごとにテーマが異なり、リゾート地のヴィラを模したものや回転木馬で優雅に遊べるタイプ、さらにはジュースやコーヒー、お菓子、カップラーメンなどが無料で提供されるお得なサービスも後押しし、2000年代初頭には爆発的な流行を見せたという、この台湾ラブホ。これらを一軒ずつ訪ね歩いて撮影を続けた陳淑貞(チェン・スウチェン)さんという写真家がいる。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 51 軽量ライフを夢見て (写真・文:オカダキサラ)
極力重いものを持たずに出かけたいと思っていても、実際はそうもいきません。 あれやこれやと持っていくものが増えて、どうしてもリュックや大きなカバンが必要になります。 普段カバンに詰めているアイテムを計量してみました。 1189グラム。 私の理想とする軽量ライフからは、ほど遠い数値です。 仕事の場合は道具も加わるので、もっと重くなります。

photography
妄想ホテル room:030 あの日あの時のメロウェイビー (写真・文:フクサコアヤコ)
ありがたいことに写真を撮ってくださいという依頼をよくいただく。 撮影依頼というのは面白い。 当然だがそこには写真に撮られたい誰かがいて何かしらの「写真に撮られたい理由」がある。 そしてその理由は人によって実に様々だ。 私の撮影は基本ラブホテルでのヌードもしくはそれに近しい写真で、「エロ」が前提となってくる。 そんな自分のエロい写真をラブホテルで撮られたいと思う動機とはいったいどのようなものだろうか。 これまでの経験から言わせてもらうと、その動機には2つのパターンがある。

photography
遠い日のリアリティ ――上田義彦「いつでも夢を」
どう書いたらいいだろう、と迷っているうちに時間が経ってしまった。今年7月末から8月中旬まで代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドフォーラムで開催された上田義彦展「いつでも夢を」を見て、いろんな想いに浸ったひとがたくさんいただろう。会場を訪れる機会が持てなくても、同時に発売された分厚い写真集を手に取って記憶の扉がひらく興奮を味わったひとがいたはずだ。この展覧会と写真集は上田義彦が手がけたサントリーウーロン茶の広告写真を中心に、撮影時のスナップ写真を加えて編まれたもの。それは1990年から2011年までの約20年間にわたって続けられた、広告写真家としての上田義彦の最良の仕事のひとつであるし、この時代の日本の広告史において、もっとも輝かしいシリーズでもあったろう。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 52 悪いニュースほど (写真・文:オカダキサラ)
私の好きな言葉に「なべて世は事もなし」というのがあります。 漫画のセリフで知りましたが、最近になり原典は海外の詩だと知りました。「なべて世は事もなし」、「すべて世は事もなし」両方の翻訳があり、解釈は様々のようです。 私は、悪いこともいいこともそれぞれ起きていて、総じてプラマイゼロになる、というふうに捉えています。 悪いニュースや出来事が重なって、「もういいことなど起きない!自分は不幸だ!」と、思う手前まで落ち込んだ時に思い出すようにしています。 本当に悪いことばかりなのか?と自問できる冷静さを取り戻してくれる言葉で、「そういや、いいこともあったわ」と立ち直るきっかけをくれます。

photography
電子写真集『わたしたちがいたところ』完成!
2016年にリリースしたvol.1『秘宝館』からvol.6『BED SIDE MUSIC ―めくるめくお色気レコジャケ宇宙』までPDFフォーマットで自主制作してきたROADSIDE LIBRARY。しばらくお休みしていましたが、ようやく新作ができました! 『天野裕氏写真集 わたしたちがいたところ』。ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 53 のんびりや、時代に追い立てられる (写真・文:オカダキサラ)
思った以上に自分がのんびり屋だと自覚したのは、つい最近のことです。 というのも、目の前のことが気になると、足もしくは手、または目を、つい止めてしまうのです。立ち止まる時間が数秒であっても、積み重なれば大きなタイムロスになります。 ハッとした時には時間はギリギリに迫っており、慌ててダッシュするはめに…。 急いだ呼吸の苦しさと、焦りや緊張の記憶が強すぎて、「私は常に追い立てられている」と勘違いしていたのです。 なんという自己中心的な捉え方…。

photography
妄想ホテル room:031 『私をどエロく撮ってください』 人妻からの依頼で思いがけずエロの原点に立ち戻った話 (写真・文:フクサコアヤコ)
ある日いつものようにSNSを通じて撮影依頼のメッセージが届いた。 北関東在住の人妻からだった。顔出し、乳首、ヘアもOK、撮影していただけるならば有休をとって都内へ赴きますとのこと。話が早い、もちろん喜んで快諾した。 詳細を確認しつつ、どのような撮影をご希望ですか?と聞いたところ、「どエロく撮ってほしいんです」と言う。 「どエロく…ですか?」「はい、どエロく」。こうして「人妻どエロ撮影」が決まった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 54 幸運を保つ不幸のバランス (写真・文:オカダキサラ)
今月、胃腸の精密検査を受けました。 ことあるごとに起こる腹痛の原因が何なのか、分かるかもしれない期待と、もしも病気だったら、という心配と不安を胸に施術に臨んだのですが、結果はまったくもって正常でした。 「とても綺麗な胃腸です」と医師が提示してくれた胃カメラの写真は、素人目で見ても異常が見当たりません。 胃腸痛の原因はまたもや謎に包まれてしまいましたが、問題ないに越したことはありません。 癌の心配も全くないと医師から太鼓判を押され、ひとまず安心しました。 すると急にお腹が空腹を強く訴えてきました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 55 魅惑の赤い傘 (写真・文:オカダキサラ)
街を歩いていると、同業者に遭遇することがよくあります。 彼らを見つけると、できるだけ無防備そうな雰囲気を装って、あえて撮影射程距離を横切るようにするのですが、私が写ったスナップショットをSNS上で見かけたことはありません (もしかして私が見逃しているだけかもしれませんが) 。 「撮ってもいいのよ」という上から目線とも捉えられかねない態度が、彼らの撮影意欲を削いでしまっているのでしょうか・・・・・・。 そのことを話のネタにしたこともあります。ある出版社の方から、こんなアドバイスをもらいました。

photography
妄想ホテル room:032 エロコンプレックス ~エロ業界の力士にぶつかりげいこを挑んだ話 (写真・文:フクサコアヤコ)
秋も深まってきた10月。 今年もまた金木犀の香りが漂う街角でふと、わけもわからぬ不安に立ちすくむ季節がやってきた。 毎年この季節になると、今自分の立っている場所が分からなくなるというか、自分という存在のちっぽけさに動けなくなってしまうことがある。 しかし安心してほしい、これは定期的に訪れるスランプめいたものである。いや実際にはスランプですらない。スランプとは日ごろインプットもアウトプットも精一杯がんばっている人のみに許される言葉である。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 56 理想のリュック (写真・文:オカダキサラ)
「首がヘルニアになりかけているかもしれない」 整体師さんからそういわれ、驚くよりも先に「そうか、その時がついに…」と納得してしまいました。 一眼レフカメラを首にぶら下げ続けたツケが回ってきたのです。 去年の今頃のことでした。 当時は首が痛くて仕事にも支障をきたすようになり、首から引っ掛ける以外に何か方法はないかといろいろ試しました。 結果、リュックのショルダーストラップについているDカンに引っかけるカメラストラップを付けることで落ち着きました。首にかかっていた負担を肩や背中に分散させる仕組みです。ずいぶん楽になりました。 その代わりに出かける際の必需品にリュックが加わることになりました。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 09 日本へ、そしてロサンジェルスへ ブルース・オズボーン(写真家)
ロサンジェルスのArt Center College of DesignでクラスメイトだったBillと、いとこのBobと僕の3人で旅をスタートしてから8ヵ月ぐらいたった頃、Bobは大学を続けるためにテヘランからロサンゼルスに戻り、Billはフィアンセから届いた「絶交状」に肝をつぶしてカルカッタからLAに帰ってしまった。 予想外の展開ではじめのうちは戸惑った一人旅だったが、自由で気ままな旅はそれなりに楽かった。ビルマでカメラを盗まれてしまったために、タイ南部の島々を訪れた1ヵ月間の写真記録がないのは残念だけど。 僕にとってこの旅の第一の目的は、2年前に帰国した佳子に会うためだった。ロサンゼルスからソウルまで40,000km。彼女が住む日本が刻々と近づいてくることがなによりも嬉しかった。 最終目的地の日本がすぐそこにあって、明日佳子に会える!

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 57 彼らの日常 (写真・文:オカダキサラ)
この間までアニメ版の「金田一少年の事件簿」をネトフリで見てました。 「金田一少年の事件簿」が放映されたのは26年前。平成の初期で、私がまだ10歳の時です。 作中にはなんとなく昭和の雰囲気がまだ漂っていて、スカートめくりや女湯の覗きなどのちょっとエッチなシーンも盛りだくさんで、昔見たはずなのに新鮮に感じてしまいました。 最近のアニメは、「そんなつもりなかったけど、結果的にスケベいただきました」という、いわゆるラッキースケベと言われる展開が主流。 私が幼い時によく見ていた、「主人公が自ら率先してエロを仕掛けにいくシーン」は、今では時代遅れなのでしょう。 なので主人公の金田一少年が毎話エッチなイタズラを仕掛ける様子に、ナイスガッツを感じてしまいました。

photography
妄想ホテル room:033 私に推しができた日 (写真・文:フクサコアヤコ)
その日私はとある古びたビルの前にたたずみ、上へと延びる急な階段を見上げていた。 階段の壁に貼られた写真から、踊り子たちが微笑みをたたえてこちらを見つめている。ここは大和ミュージック。 今や日本に残る数少ないストリップ劇場のひとつだ。 今日ここで私の「推し」が躍る。私はそれを見るためにここまで来たのだった。 急な階段を登り、受付で「女性一名です」と告げると自動的に女性・早割りと書かれたチケットを渡される。これで一日中めくるめく裸の芸術が楽しめる。私は大人の夢の国へのチケットを握りしめ薄暗いホールに足を踏み入れた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 58 船の上、海の中 (写真・文:オカダキサラ)
「キサラさん、たぶんフェリー旅行とかめっちゃいいと思うよ」 仲のいい写真家さんにそうアドバイスをもらいました。 海上では電波が通じないので、スマートフォンは使えなくなります。スマホという暇つぶしの機械が使えないとなると不思議なもので、あちこちで自然と宴会が始まるというのです。 知らない者同士でもお構いなしで盛り上がる宴会は閉塞的な空間も相まって、普通の飲み会では見られない奇妙な様子だといいます。 目的地に到着した後も気が合った人たちは交流が続いて楽しいよ、写真もたくさん撮れるんじゃない?と写真家さんは教えてくれました。 船上ならではの独特な空間に興味が湧いたのと同時に、スマホの中毒性について考えさせられました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 59 指に頼らなくなりたい (写真・文:オカダキサラ)
笑顔の練習を始めました。 笑顔なんて簡単にできるでしょ、と思っていましたが、とんでもない間違いでした。 笑顔の素敵なタレントさんを真似してみましたが、頑張っても口の端っこが引き上がらず、唇を弧の形に作れなかったのです。 指先で頬肉を引っ張ればいい感じに整えられますがまさに小手先のテクニッで、手を離すとすぐ元に戻ってしまいます。 自力で口角を持ち上げられるようになりたくて何度も挑戦しましたが、しまいには頬肉がジンジンと痛くなり、口角は最初の1回よりも上がらなくなりました。

photography
KARAOKENATION @ゴールデン街ナグネ
最近はすっかりインバウンド観光客の、夜のナンバーワン・フェバリットスポットと化した感のある新宿ゴールデン街。写真ファンや関係者が集まる店としても知られるnagune ナグネでは開店20周年を迎えるのを記念して、「13の光」と題した展覧会シリーズが去年7月からスタートしています。ひとり/組1ヶ月、1年間かけて13の展示が続くなか、僕も呼んでもらえて1月8日から「KARAOKENATION」を開催中。もともとは2017年11月に新宿御苑前のRED Photo Galleryで1週間だけ開いた展示をもとにした、新プリントによる展示です。 KARAOKENATIONとはもちろん「カラオケ民族」のこと! もう十数年間、スナックでカラオケに興じるひとたちを、発売されたばかりのフルサイズ・デジタル一眼レフに20ミリの超広角レンズをつけて、ぐぐっと寄って撮影させてもらったシリーズ。そういえば「近寄りすぎ!」ってずいぶん嫌がられた思い出が……涙。

photography
妄想ホテル room:034 開かれた結婚 オープンマリッジという選択 (写真・文:フクサコアヤコ)
オープンマリッジという言葉を知っているだろうか。 結婚相手の合意のもと、婚外恋愛はもちろん、夫婦以外で性的な関係を持っても良いという開かれた関係のことをいう。 性の革命の時代と呼ばれる1970年代に多く試みられ、1973年にはアメリカの社会学者の著書「オープンマリッジ」によって提唱されている。著名人ではウィル・スミス夫妻がオープンマリッジであることを公言していることなどで知られている。 このように夫婦が所有欲、独占欲、嫉妬心に妨げられず、自由に愛人を作れる、社会的、性的に独立した個人を認め合う結婚のスタイルは、結婚しても自由に恋愛を楽しみたい、一人の人に縛られたくないと思う人には理想的に思えるかもしれない。 けれど現実には、どうなのか。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 60 被写体に選ばれなくても (写真・文:オカダキサラ)
私は写真に撮られる機会があまりない星の元に生まれたようです。 たとえば学校行事。例えば会社での飲み会。例えば友達同士の集まり。例えばイベントの打ち上げなど。 絶対に写りたい!と強く願ってはいないのですが、イベントの後、写真を共有されたときに私が写っている写真がないと、それはそれで寂しく思ってしまうのです。 社会人になってから気づいたのですが、撮られる人の特徴としては、自分も撮っているというのがひとつあります。 「写真撮るよ~」と話しかければ、自然な流れで「じゃ、せっかくだから交代して一緒に写ろうよ」と撮影会が始まります。 もしくは「写真撮って~」と近くの人にカメラを預けたり、撮っているグループに「混ぜて!」と飛び込んだりする人もいます。 そうやって互いの記念写真は増えていくのでしょう。

photography
気配りの勝手椅子
2018年だから6年近く前になる、風変わりなトークのお誘いをいただいた。場所は神戸のKITTO(デザイン・クリエイティブセンター神戸)という、もと生糸検査場を改修したお洒落な施設(2017年にロバート・フランク写真展を紹介した場所でもある)。そのときは「WHY PURPLE?展~髪を紫に染めた貴婦人たちの世界~」という……謎すぎるタイトルの、ようするに街なかでよく見かける髪を紫色に染めた中高年女性たち。あれはなんで紫色なのか?という奇妙な研究発表。会場には美しく撮影された市井のパープル・マダムたちのポートレートがずらっと並んでいて、趣旨を知らないで迷い込んだらコンセプチュアルな現代美術展と間違えそうな空間になっていた。いったいそこでなにを話したのかはもう忘れてしまったけれど(なぜスナックの看板には紫が多いのか、みたいな話をしたのかも)、そんな意表を突いた展覧会を企画して僕に声をかけてくれたのが山阪佳彦さん。1961年生まれ、広告から自治体のブランディングまでを手がけるクリエイティブ・ディレクターだ。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 10 オン・ザ・ストリーツ・オブ・ロサンジェルス | ブルース・オズボーン(写真家)
町中をうろつき回って面白いものを探すのが得意だった天才Paul(前回のシリーズに登場)のアイディアが的中し、Madam WongsでTHE POLICEなどメジャーなミュージシャンがライブをするようになった頃。パンク風情の若者が足繁く通っていたのがメルローズ・アベニューだった。すでに人気があったレコード店のAron’sやビンテージの洋品店Aaardvarksの周辺にはたくさんの新しいショップが連なった。Wacko/Soap Plant、Cowboys and Poodles、Vinyl Fetish、L.A. Eyeworks、Industrial Revolution…懐かしい店が次々にオープン。店内は刺激的なファッションで満ち溢れていて、今のようにネットなどない時代だったから、情報交換をするための大切な場所だった。ブラブラ歩いていると誰か知り合いに会える通りは、ただ歩き回るだけで楽しかった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 61 首都圏(大)冒険 (写真・文:オカダキサラ)
会社員だったころ、業務中の移動手段は自転車がほとんどでした。一日の走行時間は5時間から7時間ほど。東は千葉県成田市、西は神奈川県寒川町、北は埼玉県加須市まで、都心を中心にぐるりと円を描いた範囲を定期的に巡っていました。 支給されたのは格安ママチャリ。アルミの車体はいかにも脆そうで、ちょっとした衝撃でも壊れてしまいそうでした。自宅とその周辺の移動が前提の設計で、変速機も付いておらず、とても長距離向きではなかったはずなのですが、7年ほど一緒に走ってくれました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 62 スマート旅行に憧れて (写真・文:オカダキサラ)
泊まりで地方に出張する機会が増えたのですが、いつも荷造りに苦労します。 特に冬は厚手の服が必須となるため、余計に荷物は重くなるばかり…。どうにかならないかと、いろいろ模索しているところです。 旅好きの漫画家の友達がいます。彼女のフットワークは軽く、1ヶ月に数回は地方に旅行し、そこで原稿を描いています。一回の滞在期間が1週間以上の時もあるようで、きっと大荷物で旅に臨むのだろうなと私は予想していました。 ずいぶん前のことになりますが、彼女と旅行先が一緒だったのを互いのSNSで知り、現地でお茶をすることになりました。約束の日は彼女が帰る日で、きっと大きいキャリーカーを引いてくるのだろうと私は思っていました。

photography
妄想ホテル room:035 性癖という部屋をのぞく時 (写真・文:フクサコアヤコ)
「人の性癖を見るのが好きなんですよ」 今日もラブホテルの一室。シャッター音の合間にそんな会話が漂う。 「前の撮影の時もそう言ってたね。それで今はM性感で働いてるんだよね」 レンズを除いたままで私が承ける。 今回のモデルであるフジちゃんを最初に撮ったのは昨年の春。 彼女の人生で初めてのセミヌード撮影だった。 「単純にエロが好きっていうのもあるんですけどね」 そう言って彼女は笑う。 エロへの好奇心旺盛な彼女。ラブホテルで写真を撮られるようと思ったのもそんな興味からだった。 そして今、「人のエロい部分が見たい」という欲求を満たすため、彼女はM性感で働いている。 望み通り人の様々な性癖を目にし、本当に人の性癖って多種多様なんだなと実感する日々だと言う。

photography
市川信也《仮面の告白》
先月(2月)3日から11日まで京都の下立売通智恵光院にある、民家を改装したギャラリー・ヘプタゴンで「壁をのぞむ眼差し」という写真展が開かれていた。「障害の有無を超えた表現者たちによる写真展」とサブタイトルがつけられたこの展覧会は、障害者自身や障害者に寄り添う活動を続けている表現者たち5人によるグループ展。そこで出会ったのが《仮面の告白》と題された市川信也によるモノクローム・プリントのシリーズだった。 夜店で売っているようなおもちゃの仮面をつけて、静かにカメラの前にたたずむオトナの男女たち。彼らは市川さんが医師として勤めていた精神科病院の長期入院患者たちだ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 63 喫煙所パイオニアの憂い (写真・文:オカダキサラ)
次の制作に向けて、過去の写真を見直しています。2008年から2024年までに撮った記録を行ったり来たり、小さなタイムトラベルを繰り返しているようです。 銀座の中央通りの路肩に、吸殻入れが設置されている写真を見つけて驚きました。そういえば、私が大学生の頃は、近くの店員さんたちが中央通りに集まり、タバコを吸いながら歓談していました。今となっては、かなり懐かしい光景です。 改正健康増進法が制定された2018年以降、歩道に設置されていた吸殻入れは撤去され、代わりに喫煙ブースが用意されました。 私を含めた非喫煙者にとってはいい改正でしたが、喫煙者にとっては一大事だったに違いありません。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 64 喫茶店から始まる物語 (写真・文:オカダキサラ)
先日、塩屋に23日間滞在しました。 塩屋は神戸の三宮から電車で20分ほどの所にある小さな町。山と海に囲まれた地形が特徴で、ここの風土に魅せられて移住を決める人が数多くいます。 地方から塩屋に移ってきた人たちから、引越しのキッカケを教えてもらう機会がありました。 面白かったのが、話を聞いた3人のうち2人は、喫茶店のマスターの紹介のおかげで住む家が決まったことです。 家探しも兼ねて塩屋を散策している途中、ふらりと立ち寄った喫茶店で「ここに住みたいんだよねぇ」と軽い気持ちで話したら、マスターがその場で地元の何人かに電話。みんなが集まってあれよあれよという間に、住む家の候補をすぐに見つけてくれたというのです。

photography
「人間の住んでいる島」@丸木美術館
米軍の暴挙への抵抗運動の先頭に立ち、当事者による証言として写真と文章を発表し続けたのが阿波根昌鴻(あはごんしょうこう)だった。1901年、本部町生まれの阿波根は成人後に伊江島に渡り結婚。その後キューバ、ペルーに移民したあと伊江島に帰り、一生を抵抗運動に捧げて2002年、101歳の天寿を全うしている。その阿波根昌鴻が遺した貴重な写真記録を紹介する「阿波根昌鴻 写真と抵抗、そして島の人々」が、いま埼玉県東松山市の原爆の図 丸木美術館で開催中だ。

photography
妄想ホテル room:036 裸の仮面 (写真・文:フクサコアヤコ)
2月だというのにその日は春をすっ飛ばして初夏のような陽気だった。ダッフルコートを着てきたことを激しく後悔しながら私は待ち合わせのアルタ前に立っていた。 今日は初めてのモデルさんとの撮影だ。少し前にSNS経由で連絡をくれて本日の撮影となった。 初対面なので待ち合わせの目印にと、グレーのダッフルコートを着ていますと送ってしまったため、コートを脱ぐに脱げず私の体はじっとりと汗ばんでいた。もう限界だ、コートを脱いでも手に持っていればわかるだろう、それとも脱ぎましたとメールを送りなおそうか、そう逡巡しているうちにモデルさんが私を見つけてくれ無事に合流することができた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 65 ニンゲンアピール (写真・文:オカダキサラ)
ペットショップに行くと、犬種による性格の特徴が紹介されているのを見かけます。 トイ・プードルは温厚で友好的。柴犬は忠誠心が強く、飼い主にしか懐かない。ダックスフンドは甘えん坊、などなど。 こんな説明を見聞きする度に、ペットショップでニンゲンが売られるパラレルワールドがあったとしたら、私たちはなんてアピールされるのだろうか、と考えてしまいます。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 66 モバイルふべん (写真・文:オカダキサラ)
地方に出張する機会が多くなりました。 移動時間に、景色を楽しめる余裕があるときはいいのですが、片付けなければならない仕事が溜まっていると、その時間がもったいなく思うときもあります。 空き時間を有効活用するためにノートパソコンの購入も考えましたが却下しました。重いパソコンを常に持ちながらブラブラするのは体力的にキツそうですし、なにより仕事に気を取られ、せっかく外出しても楽しめなくなりそうだからです。

photography
妄想ホテル room:037 失恋ランジェリー (写真・文:フクサコアヤコ)
春は恋の季節、と同時に別れの季節でもある。 今年もどこかで小さな恋が始まり、どこかで別の恋が終わろうとしている。 始まってしまった恋には必ず終わりがやってくるとわかっていても、その悲しみに慣れることはない。 それが突然であればなおさら。 今回の妄想ホテルはまさに終わろうとしているひとつの恋に寄り添った記録である。

photography
いまそこにある吉原のために
開催前からなにかと話題になった上野・東京藝大美術館の「大吉原展」。SNSで批判するひとたちも、とりあえず展覧会を観てから思う存分批判すればいいのにと思うが、それはともかく! 「大吉原」は遠い江戸時代の吉原に花開いた芸術に焦点を当てているわけだが、吉原という日本最大規模の遊郭は明治になっても大正・昭和になってもあいかわらず遊郭/赤線としてそこにあったわけだし、戦後も昭和33年の赤線地帯廃止後、数十軒の民謡酒場が軒を連ねた過渡期を経て、日本最大のトルコ→ソープ街となっていまも約120店が営業中。しかしその「現代の吉原」は、もちろん藝大の大吉原には入れてもらえてないし、夕刊紙や風俗情報誌以外のメディアに取り上げられることもめったにない。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 67 大人は乗れない車 (写真・文:オカダキサラ)
赤ちゃんは乗れるのに、大人は乗れない車ってなあに? こんなクイズがありました。答えはベビーカーです。 本当に大人は乗れないのでしょうか。調べてみると最大耐荷重75kgのベビーカーもあるようで、体型によっては大人でも乗れなくはないことがわかりました。 もっとも、重量的な可不可はとにかく、窮屈なシートに乗せられて誰かの手によってしか進めない状況は、言い方を変えれば「目的地もわからないまま、運ぶ人に全てを委ねる」ということ。

photography
空想ピンク映画の自撮りスター
「マキエマキの空想ピンク映画ポスター展6」が先週の6日間、渋谷のギャラリー・ルデコで開催された(4/223~28)。もう6回目になるとは・・・・・・と感慨を抱きつつ展示に向かったファンが、ロードサイダーズ諸氏にもいらっしゃったかと思う。 マキエマキを初めて紹介したのが2016年2月10日号「自撮りのおんな」。それから8年のあいだに、自撮りされたマキエさんをずいぶん見てきた。ロードサイダーズ・ウィークリーでは何度も取り上げてきたし、NHKで番組がつくられるほど世間での認知度も急上昇してきた。ちなみに2016年にはTwitterのフォロワー数が1500人くらいだったのが、現在は約5万人。インスタのフォロワー数も3.8万人である。そんなマキエさんの、ポスター展としてはコロナ禍を挟んで今回が3年ぶりになるという展示を見ての感想を、見逃したかたのための誌上展とあわせてお読みいただきたい。

photography
妄想ホテル room:038 いかに社会に溶け込みながら人からかけ離れるか (写真・文:フクサコアヤコ)
そういえば写真を始めて今年で30年になる。 専業カメラマンではないものの「昼はOL、夜はカメラマン」というスタイルでとりあえずどんな時も撮り続けた。 写真の師匠からの唯一の教え「死ぬまで撮り続けること」を心に誓い、対象が風景から人、そしてエロへと移り変わっても辞めることなく今に至っている。 初個展は写真を始めた地である京都にて。寺町三条の同時代ギャラリーに併設された小さなギャラリースペースだった。 当時の私の作品はモノクロの風景写真で、押し入れを改造して作った暗室で夜な夜な焼き上げていた。個展前などは会社から帰ると徹夜で暗室作業をし、また朝から会社へ行くという毎日だった(若かった)。

photography
21世紀の浪漫主義者
ゴールデン街を抜けて日清食品本社(かつて地下にパワーステーションがあったビル)に向かう道沿いにある新宿眼科画廊。ロードサイダーズでもずいぶん、ここで開かれた若手作家の展覧会を取り上げてきた。サブカルチャーという言葉ではくくりたくないが、日本でいちばん猥雑でエネルギッシュな歌舞伎町という街に、もっとも共振しているギャラリー(と演劇空間)であることはたしか。ここでデビューしたアーティストも、ここでしかやりたくなかったり、やれないアーティストもたくさんいるはず。 5月31日、ここでまたひとりの写真家が初個展を開く。堀江由莉(ほりえ・ゆり)、展覧会名は「浪漫(ROMAN)」。写真展というより昔懐かしい『カミオン』や『トラックボーイ』の表紙みたいなギラギラ・ド派手なビジュアルに、毛筆フォントの「浪漫」、その脇には「デコトラ、成人式、刺青、祭事、歌舞伎町、夜遊び、街並み……」と展覧会の内容を示すキーワードが並んでいて、ロードサイダーズ諸君ならこれだけで彼女のテイストが察せられるだろう。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 68 ブランド品のバッグの威力 (写真・文:オカダキサラ)
時計か靴かカバン、どれかが高級ブランド品だったら、金持ちでなくてもそれなりに見える。 そう教わったことがあります。残念ながら私は、いずれのアイテムも持ったことがないので、高級ブランドの威力を体験したことはありませんが、一理あるなと思う出来事が先日ありました。 銀座のとあるお店の中で、呼吸を荒くしてベンチでうずくまっている女性と、その女性を介抱している友人を見かけました。 あまりに辛そうな息遣いに、通りがかりの男性が心配し声をかけました。

photography
妄想ホテル room:039 はじまりのダンスを踊ろう (写真・文:フクサコアヤコ)
いつものラブホテルの受付、部屋を選ぶパネルの前で私は不思議なパワーを感じていた。 古く廃れたこのラブホテル、昨年壊れたボイラーはまだ直らないらしく「バスタブは使えませんがよろしいですか?」と毎回確認される。 そんな有様なので少し前までは平日の昼であれば部屋は選び放題だったのだが、インバウンドの波かコロナの反動かここ最近は満室が続いていた。 なのに今日は5室ほど空室を示すランプが点灯している。そしてその中に蝶をモチーフにした部屋があった。 「あ、ここ!蝶のお部屋がありますよ!」その部屋を見つけた彼女は嬉しそうに振り返った。 彼女はミラ・スワロウテイル、蝶の名前を持つバーレスクダンサー、今回のモデルである。 彼女自身が自分の名前に所縁のある部屋を引き寄せたのかもしれない。彼女の笑顔にはそう思わせる不思議なパワーがあった。 私たちは受付を済ませると蝶の舞う部屋へと向かった。

photography
死体のある風景と「火サスごっこ」
すでに完売だったのをご本人のXアカウントに連絡して送っていただいた『レトロホテルへようこそ』は、「さかもツインねね」という不思議な名前の作者による小さな写真集だが、これも女性によるラブホ・コレクション。でも、さかもツインねねさんの写真はほかのどんな昭和ラブホ写真ともちがっていて、それは画面のなかに死体・・・・・・ではないけれど、死体に擬態した本人が横たわっていて、それは彼女が長くつづける「火サスごっこ」活動のコレクションなのだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 70 リビングのかたすみで (写真・文:オカダキサラ)
あれ?と気づいたのは、つい数ヶ月前でした。 リビングに置いてあったクマのぬいぐるみが、いつの間にか消えていたのです。 全長1メートルないくらいの、少し大きめのそのぬいぐるみは、リビングの棚の上に長いこと座らされていました。 白かった毛並みは日焼けし、綿のハリもなくなって、全体的にヨレヨレした様子は、疲れたおじさんを連想させました。 もしかして古くなりすぎて捨てられてしまったのか?…

photography
国破れてしぶとい日常があった ――横浜都市発展記念館の戦後横浜写真アーカイブズ
横浜市中心部、神奈川県庁と横浜スタジアムがある横浜公園に挟まれた、歴史的建築物が並ぶエリア。昭和4(1929)年に横浜中央電話局として建てられた茶色い大きな建物がある。かつてはここでたくさんの女性電話交換手が、手作業で横浜の電話をつないでいた場所だ。2003年にこの建物内に横浜都市発展記念館と横浜ユーラシア文化館という、ふたつの博物館が誕生。あいにく去年から空調設備の更新で休館中だが今年7月20日に再開館とのこと。 閉館中ではあるが、横浜都市発展記念館の公式サイトではさまざまな収蔵品を見ることができる。

photography
Once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 11 オン・ザ・ストリーツ・オブ・ロサンジェルス part 2 ブルース・オズボーン(写真家)
その頃住んでいたのは、Western Blvd.とMelrose Ave.に近いロフト。裏庭にはバレーコートにできるスペースがあり、週末になるとみんなが集まってきて、大音響で音楽をかけながらバレーボールを。定番のサウンドトラックは、James White, Specials, Ramonesなど。Friction, Phew, Sheena and the Rocketsなどの日本のミュージシャンも人気だった。 幸いなことに、旅を終えて帰国した後も、前から働いていたPhonographic Record Magazineで働くことになったので、仕事のリサーチも兼ねてコンサート通いをしたりクラブを回って地元のバンドを聞き歩く毎日だった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 71 廊下のロッカー (写真・文:オカダキサラ)
私が通っていた高校は生徒の自主性を重んじる校風のため、自由度がかなり高く、授業の妨げにならなければ、漫画や携帯電話、ゲーム機などの持ち込みが許可されていました。 漫画が大好きな私は、友人同士で頻繁におすすめの作品の貸し借りをしていました。 私たちはそのうち漫画を家に持って帰るのが億劫になり、空いているロッカーに一時的に預けるようになりました。みんなそれぞれ持ち込むので、ロッカーはほぼパンパン。ラインナップも定期的に更新されていました。読みたい本があれば、利用メンバーにひと声かけて持ち出し、読み終わったらロッカーに戻す。そんなレンタルシステムが自然と生まれていました。

photography
妄想ホテル room:040 妄想エンドロール (写真・文:フクサコアヤコ)
歌舞伎町のはずれ、寂れたラブホテル。その一室にいる二人の女。 一人は手にカメラを持ち、一人は下着姿、どうやら何かの撮影をしているらしい。 そんなシーンからこの映画は始まる。 「今の感じいいね、もうちょっとひねってみて」カメラマンの独り言のような指示にポージングで応えるモデル。 ホテルの部屋に積み重なっていくシャッター音と衣装を脱ぎ落す音と、そして二人の呼吸。 淡々と続く撮影シーンにオープニングクレジットが重なる。 モデル:春乃ミア カメラマン:フクサコアヤコ タイトル…

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 72 証明写真の真実 (写真・文:オカダキサラ)
車の免許更新で、いちばんため息をつきたくなるのは証明写真です。 今度は自分が撮った写真を用意していこう、と決めていましたが、更新日直前になってもなかなか時間が取れず、結果、いつも通り会場で撮ってもらうことにしました。 できあがった免許証には、仏頂面なうえに半目気味で写っている私が印刷されていました。性格が悪そうな印象を与えるのに、十分な人相です。 ネタのつもりで近しい人に、「写真写り悪すぎたよー」と免許証を見せたら、「そんなことないよ」 と返されました。

photography
『公園奇譚』孫一氷写真展 (文:吉井忍)
2022年9月7日号の連載「Freestyle China 即興中華 公園とホルモン」で写真家・孫一氷を紹介してくれた吉井忍さんから連絡があり、孫一氷(ソン・イービン)がいま原宿のギャラリーで個展を開いているという。急いで行ってみたSOMSOC Galleryは原宿の表通りから入ってすぐ、2周年を迎えたばかりの新しいギャラリーとアートショップだった。運営しているのは中国人と日本人の若者たちによるユニットで、展示のテイストも、場所柄も、いわゆる現代美術のギャラリーよりもぜんぜん風通しのいい、ポップな空気感が際立っている。ちなみにSOMSOCとは宇宙を意味するCOSMOSを反転させた造語、「人間は無限に広がる大宇宙の中では、ちっぽけな存在です。そんな小さな存在でも自分の「内なる宇宙」、つまりSOMSOCを原宿という特異点から全世界へ発信できるという希望が込められています」(ツイートより:@Somsocgallery)。会期中には吉井忍さんなどが登壇するトークイベントもあるので、今回は吉井さんに展覧会紹介を寄稿していただいた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 73 別になくてもいい、私の特技 (写真・文:オカダキサラ)
私の特技のひとつに、水ものを飲む速さがあります。特技といっていいか微妙な技ですが、驚くほど多く、早く水を飲めるのです。 学校の給食でのちょっとした定番イベント、「牛乳の一気飲み」では、さぞかしいい成績を残していただろうと思う人もいるでしょうが、残念ながら、この特技が開花したのは社会人になってからです。 お酒の席で「一気飲みコール」で鍛えられたわけではありません。業務内容のほとんどが屋外でウロウロすることだったからです。

photography
妄想ホテル room:041 夏休みの自由研究 写真家うつゆみことラブホテル (写真・文:フクサコアヤコ)
7月、蝉の第一声とともに私の長い夏休みが始まった。 私は写真を撮っている一方でフリーランスのOLとしても働いているのだが、業務の繁忙期が秋冬春のため夏は比較的ヒマなのだ。フリーランスなのでここ数年は夏にも別案件を受注して通年OLとして働いていたが、少しつまらなくなってきたため今年は久しぶりに2か月夏休みをとることにした。 平日の昼から空いている映画館に行ったり、昼酒を決めてほろ酔いになってみたり、平日料金のフリータイムでラブホテルにしけこんだり、ぜいたくな時間を使って大人の夏休みを満喫するためだ。 その日も昼からビールを片手に何か面白いことはないかとSNSをさまよっていると、とある投稿が目に入った。 「気がついたら100枚位のワンピース、その他たくさんの服があり… 『服があった(仮)』というジンを制作したく、写真を撮っていただける方を募集します!! スタイルが確立している、個性のある写真を撮って下さる方だと大喜びです!! 遊び心のある方もお待ちしています!!」 写真家うつゆみこさんの投稿だった。

photography
Once upon a time ~もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 12 LAバンドとミュージックシーン ブルース・オズボーン(写真家)
Art center college of Design in Los Angelsでの最後の年、The Band, Ray Charles, Tina Turner, Rolling Stones, Frank Zappaなど、数々のレコードアルバムを撮影する超売れっ子のNorman Seeffに会いに行ったところ、友人が立ち上げたばかりの音楽雑誌社が写真家とエディターを探していると、その雑誌社の編集長を紹介してもうという幸運に恵まれた。70年代後半に、僕がメインで写真の仕事をしていたのが、この時にNorman が紹介してくれたPhonographic Record Magazine (PRM)という音楽雑誌だ。ロックミュージックに関するニュースや情報を紹介するグラビア中心のフリーペーパー。ロサンゼルスの音楽シーンに興味があった僕にとっては絶好の仕事だった。新しいレコードアルバムの情報や、クラブで新しいバンドを取材することで、たくさんのミュージシャンや制作関係者に会って写真を撮り、話を聞く機会に恵まれた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 74 どっこいしょ尊い (写真・文:オカダキサラ)
しゃがむ姿勢が好きではありません。立ち上がる時に必ず立ちくらみを起こすからです。 とはいえ、しゃがみながらの作業は制作につきもの。姿勢を元に戻すときは喝をいれるために「どっこいしょ」と掛け声をかけるのが習慣になってしまいました。 「どっこいしょ」はどこかの方言かと思っていたのですが、仏教の「六根清浄」が由来と知って驚きました。

photography
AIカメラクラブにようこそ
いまから1年ぐらい前だろうか、Instagramに不思議な画像が流れてきて、思わず見入ってしまった。それはセピアがかった、見るからに何十年も前のアメリカの風景や人物写真なのだが、なんだかモノクロームの夢というか悪夢のなかに入り込んだように、ものすごく奇妙なカメラや建築が写り込んでいる。写真だからすごくリアルだけど、よく見るとあり得ないようなディテールがあったりもする。こんな写真家、どうしていままで知らなかったんだろう!と驚いて投稿者を見ると、「The AI Camera Club」と書いてある。AIカメラクラブ? さらに探していくと、それはティモシー・アーチボルドが去年始めた風変わりで魅力的な写真シリーズなのだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 75 かくれんぼ (写真・文:オカダキサラ)
ホラー映画の何が苦手かというと、驚かされることです。後ろを振り返ったら化け物がいて、まさに襲いかかろうとしていた、というシーンは、展開をいくら予測できたとしてもびっくりします。 私は会社員時代、リフォームマンションの撮影を担当していました。中には「あれ?なんか嫌な感じがする…」と思う現場もいくつかありました。間取りや家具の配置ではなく、家の中に自分以外の何者かの気配を感じるのです。

photography
Freestyle China 即興中華 公園の性張力:孫一氷「公園奇譚」より (写真:孫一氷 / 文:吉井忍)
友人に「公園に行こう」と誘われたら、あなたはどんな場所を思い浮かべるか、何を準備するか。それが日本と中国では大きく異なる。北京在住の写真家・孫一氷(ソン・イービン)さんの個展「公園奇譚」を訪ねて、改めてそれを意識した。 孫さんはコロナ期間中、北京にある公園を訪ね歩き、そこで体を鍛える高齢者たちを撮影していた。鉄棒や雲梯、健康遊具を巧みに使いこなし、抜群の身体能力で華麗なポーズを決める高齢者たちは中国でも話題を集め、2023年には写真集『在公園』(孤独図書館)が出版された。原宿のギャラリー・SOMSOCで行われた今回の個展(8月11日終了)は、孫さんにとって日本初の個展で、これに合わせて中国版に未掲載の作品も収録した写真集『公園奇譚 SAGA IN THE PARK』(研美株式会社、2024年)を制作。

photography
妄想ホテル room:042 夏の終わり 卒業写真 (写真・文:フクサコアヤコ)
「被写体をやめることにしました。最後に写真を撮っていただけませんか」 そんなメールをもらったのは夏の始め、今年最初の蝉の声を聞くころだった。 『被写体という仮面を捨てて「ただの女」になる今こそ、フクサコさんに撮っていただきたいんです』とそのメールには綴られていた。 被写体の「始まり」と「終わり」、私はなぜかその両方に立ち会うことが多い。 被写体を始めるのにはそれぞれにその人だけの理由があって、私はその物語をなるべく記録したいと思いながら撮影に臨んでいる。そしてそれは「終わり」も同じ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 76 動いてダメなら眠ってみる (写真・文:オカダキサラ)
なんとなく本調子ではない気がする、というのが、何年も続いています。運動不足か筋力不足が原因かと思い、ウェブで筋トレやストレッチを調べてはいろいろ試してみましたが、いまいち効果を実感できていませんでした。 そんなときに、ちょっとした事件が起きました。 恥ずかしながら、先日、終電を逃してしまうまで深酒をしてしまいました。ここまで酔ったのは本当に数年ぶり。楽しい一夜から翌日は二日酔いで半日以上苦しむことになりました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 77 通りすがりの最善 (写真・文:オカダキサラ)
会社に勤めていた頃、仕事中によく道を訊かれました。住宅街をラフな格好で歩いていたので、ご近所さんだと勘違いされたのでしょう。尋ねられても大抵分からないので、Googleマップで一緒に探していました。 ただ話しかけてくる人もいました。たいていが世間話ですが、中には他人である私が聞いてもいいのだろうかと心配になるような話もありました。 7年前のことです。 現場に向かう途中でした。大通りから一本入った狭い一車線道路で、ひどく痩せたおじいさんに、「暑いですね」と声をかけられました。 季節は初夏。「暑いですね」というわりに、おじいさんはしっかり長袖を着ていました。

photography
妄想ホテル room:043 ここにいる誰かが私であること (写真・文:フクサコアヤコ)
例えば電車に乗っていて遠くの知らない街を通りかかった時、その街に住んでいるもう一人の自分の存在を感じたことはないだろうか。 駅前のだだっ広い駐車場、車窓から見える大きなマンションの窓、長閑な川沿いの土手。そこで生活している別の自分を見かけたことはないだろうか。 そしてそんな時いつも思うのだ。今ここにいる私もまた、誰かの別の自分なのだと。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 78 時代遅れはすぐにやってくる (写真・文:オカダキサラ)
漫画家ユニット・ CLAMP展開催の記念として、CLAMPの作品が漫画アプリで一時的に一部無料で購読できるようになっていました。 私が最初に見たCLAMPの作品は「魔法騎士レイアース」です。この作品は1993年から1996年に少女向け漫画雑誌『なかよし』で連載されており、当時、私はドンピシャの対象年齢でした。 「魔法騎士レイアース」は、私がCLAMPの独特の世界観にのめり込んでいったきっかけの作品です。たくさん並ぶタイトルから、この作品をいちばんに読みました。 忘れていたキャラ、シーン、セリフ。CLAMPの描く世界を、懐かしさと一緒に堪能しました。 1巻の最後の1コマを読み終わり、奥付けにあたるページをめくると、そこには読了後の満足感を吹っ飛ばすような注意書きがありました。 「現代のコンプライアンスに反するところもありますが、当時の時代背景を考慮してセリフなどはそのままにしております」

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 79 おトイレクリエイティヴ (写真・文:オカダキサラ)
トイレ待ちで並んでいたときのことです。 私の前には、おばあちゃんとそのお孫さんが待っていました。ひとつトイレが空いて、女の子はいそいそと入っていきましたが、中を見たとたんに出てきてしまいました。 「このトイレの使い方、分からないよぉ」と、女の子はおばあちゃんに訴えます。そのトイレは和式だったのです。ジェネレーションギャップに驚かされました。 洋式トイレが初めて日本に輸入されたのは1887年。場所は横浜にある外国人住居地です。今の形の和式トイレが開発されたのは1902年で、意外にも洋式トイレ導入の後です。

photography
妄想ホテル room:044 猫と承認欲求 (写真・文:フクサコアヤコ)
急に肌寒くなった。 もはや日本から秋と春という季節は消えてしまったのではないかと思うほどの急激な変化だ。 今日は30度近くあった最高気温が、明日には最低気温11度まで下がるとニュースが告げている。私は急いで押入れの奥から冬用の毛布や上着を引っ張り出した。南方の生まれ故、寒さにはめっぽう弱いのだ。 私が家で使用する毛布やシーツ、ブランケット、部屋で羽織るカーデガンなど、ぬくもりを提供してくれるグッズはすべてふわふわ、もこもこした素材でできている。暖かさよりもむしろ手触りを重視しているふしすらある。 昔はそれほど素材にこだわりはなかった。暖かければ多少ゴワゴワしていてもなんでもよかったはずだ。 いつから、なぜこんなにもふわふわな手触りにこだわるようになったのか。おそらくそれは今の私の生活に猫がいないからだ。私は失った猫のぬくもりと手触りをいつだって求め続けている。

photography
御徒町のニュー桃山時代 写真・文:紅子(色街写真家)
ロードサイダーズでもおなじみ、色街写真家・紅子さんのSNS投稿で上野御徒町の老舗ソープランド「ニュー桃山」閉店を知ったひともいるだろう。いまや絶滅危惧種となりつつある「駅前ソープランド」の典型であるニュー桃山は、文京区で営業する唯一のソープランドでもあった。その終焉に立ち会った紅子さんにお願いして、写真と文章で鎮魂の思いをつづっていただいた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 80 ロマンスとトレンドと現実と (写真・文:オカダキサラ)
最近、街の若い子たちがよく着ているコーディネートに、既視感を覚えています。私が高校生の時に流行ったスタイルだからです。流行は繰り返す、を実感しています。このままいくと、次は「エビちゃん」ルックが来るかと予想しているのですが、どうでしょうか? 少し前なら、服の傾向は雑誌名やモデル名でまとめられていました。近年ではトレンドにまとまりを感じられません。今は「○○系」とグループ分けするのも大変そうです。

photography
Freestyle China 即興中華 地下道を忘れない:許曉薇(シュウ・ショウウェイ)写真展 (写真:許曉薇 / 文:吉井忍)
写真家・許曉薇(シュウ・ショウウェイ)さんの新作個展「地下道的史内爾(地下道のスネイル)」が開かれていると聞き、台北に行ってきた。身体に植物を介入させたセルフポートレートで知られるシュウさんだが、今回はまた違った作風らしい。会期中はイベントも何度か行われ、SNSにはみんなでスープを飲んだりと何やら楽しそうな様子がアップされてはいる。だが全貌がよく分からない。閉幕2日前になんとか取材を行った。 場所は台北駅からほど近いイベントスペース「未命名(WMM)」。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 81 オカダ、山を置いて、都会に帰る (写真・文:オカダキサラ)
「オカダさん、基本的に人はみんないい人なんだよ。でも悪人でないだけで、善人ではないんだよ。俺が心の底から悪人だと思ってる奴らは、いつも笑顔だ。そのうえ笑い上戸で、ちょっとしたことでウケる。で、笑いながらとんでもないことをやらかすんだ」 誰でも彼でも、「いい人ですよ」と紹介する私に、お世話になっているフォトグラファーのYさんから鋭い指摘を受けました。本当にその通りです。

photography
妄想ホテル room:045 新しい部屋 (写真・文:フクサコアヤコ)
その日私は、東京都写真美術館で開催されている、アレック・ソスの写真展『部屋についての部屋』を訪れていた。 アレック・ソスはもともと好きな写真家だが、今回は『部屋』がテーマの写真展だ。ラブホテルの『部屋』で写真を撮っている私としてはぜひとも見ておかなくてはならないだろう、ということで愛車ミニベロに乗って颯爽と恵比寿までやってきたのだった。 思った通り写真展は素晴らしく、『部屋』についてのとらえ方もとても参考になったし、なによりこういった写真展を訪れること自体が久しぶりだったこともありその刺激はとても心地よいものだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 82 ムクドリの憂鬱 (写真・文:オカダキサラ)
友達とのお茶会の後のことです。時間は16時過ぎ。雲ひとつない天気で、冬の空は夕暮れのグラデーションで美しく染まっていました。その空に、不穏な集団の影が横ぎりました。鳥の群れが都会の真上を旋回していたのです。何十羽も揃ってグルグル空を泳ぐ鳥たちの正体は、ムクドリです。他の通行人も顔を上げて、それを眺めていました。こんな都会にもいるんだと感心している私の横で、一緒にいた友人がポツリとこぼしました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 83 星占いテロをやめてくれ (写真・文:オカダキサラ)
「今日の星座占いランキングです」という文言を見ると、占い結果が見えないように、できる限り距離を取ります。占いなんて当たるわけない、と思いながら、見て(聞いて)しまうとなんだかんだ気にしてしまうからです。これから占いを公開しますよー、とアナウンサーが事前に案内してくれるならチャンネルを変えるなり、視線を外すなり、耳を塞ぐなり対処ができるのですが、何の気なしに見上げた街の電子掲示板に、星占いランキングが表示されていた日は最悪です。自分の星座が何位であろうと、それだけで不運と呼べます。 なるべく自分の運勢に触れるコンテンツは避けていたのに、どうしても目に飛び込んで来るものがあります。厄年です。

photography
once upon a time ~もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 13 東京での展覧会が決定 ブルース・オズボーン(写真家)
1980年の春。 念願だった東京での写真展が実現することになった。 会場は日本橋の小西六ギャラリー。 初展覧会のタイトルを「LAFANTASIES|三部作」と決めて作品の制作に取り掛かった。 三部作のうち、第一部は、当時仕事をすることが多かったモデルやミュージシャンにLAのパンクシーンを盛り上げていたファッションデザイナーの衣装を着てもらって撮影したファッション系の写真。

photography
妄想ホテル room:046 始まりのラブドール、大人の赤ちゃん ひつじちゃん (写真・文:フクサコアヤコ)
新しい年がきた。希望の年だ。喜びに胸を開け、あけましておめでとうございます。 新年ということで、今年の抱負など。今年の私の抱負は「もう少しおしゃれに気を遣う」だ。昨年末の撮影で、仲良しのモデルさんだし家から近いスタジオだしとウッカリパジャマのような格好(宇宙模様)で撮影に行ったら、そのモデルさんのファンティア用の動画に出演する羽目になり、私のすっぴんパジャマ姿(宇宙模様)が全世界に配信されるという事態となった。その動画内で「来年の抱負は?」と聞かれたので特に何も思いつかなかった私は画面に映る自分の姿を見て「もうパジャマのような格好で撮影に来たりしません」と世界中にいるそのモデルさんのファンの方々に誓ったのだった。 そんなわけで、きちんと撮影用の黒の上下(私的にはおしゃれ)を着こんで臨んだ今回の撮影。 待ち合わせ場所に現れたのは全身黒づくめの私とは対照的な、全身ピンク色のひつじちゃんだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 84 脱ぎ捨てて物語 (写真・文:オカダキサラ)
私は同じパンツを2日連続で身につけるのに、ものすごく躊躇します。突然のお泊まりで「困ったな」ベスト3のうち、「パンツの替えがない」は、1位の「カメラの充電」に次ぐ2位にあたります。ちなみに3位は「歯磨き用品がない」です。 私は過去に3回、パンツの替えを忘れて遠出してしまったことがあります。着替えを用意した袋の中に、パンツがなかった時の衝撃はすさまじいものでした。

photography
いちばんつよいのはなにもかくさないこと――天野裕氏と自宅図書館
あれから8年あまり。何度も会って、何度も記事にして、2023年にはデジタル写真集『わたしたちのいたところ』もロードサイダーズから刊行した。その天野くんは長いこと鬱病に苦しんでもいて、障害者手帳も20代から所持。この数年、症状が重い状態が続いて、2024年の1年間は旅に出ずにホームグラウンドである大牟田の病院とアパートを行ったり来たりしていたという。で、そのアパートがいま「だれでも泊まれる図書館状態」になっていて、さらに来たひとのために写真を撮って紙に挟んだ一点物のポートフォリオもつくっていると聞いて興味を掻き立てられ、久しぶりに会いに行ってきた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 85 卒業適齢期 (写真・文:オカダキサラ)
「実際に写真作品を買ったことがある?」そう聞かれたのは、打ち合わせの時にポロリと出た世間話からです。日本のアート市場において、写真作品は他の作品よりも売れにくく、ギャラリーからしても扱いにくい、という話から冒頭の質問に繋がりました。 ギャラリーからではないのですが、私は一度だけ写真作品を購入したことがあります。それは夜中の中野サンロードででした。当時、私は大学1年生で、中野ブロードウェイにあるお店でアルバイトしていました。夕方から閉店までシフトを入れていたので、帰りはシャッターで閉じられた商店街を抜けて駅に向かっていました。アーケード内は明るいため、お店は開いていないのに往来は家を目指す人が行き交っていました。

photography
妄想ホテル room:047 暴れ牛の思い出 (写真・文:フクサコアヤコ)
前回のひつじちゃんに続いて今回のモデルは牛である。 丑年でもないのになぜか牛について書きたくなってしまったのは、年末年始を実家で過ごす人たちを目にし、里心が付き、ふと子どもの頃のお正月の出来事を思い出したからかもしれない。 私は子どものころ暴れ牛に遭遇したことがある。というか暴れ牛を発生させてしまったのは他ならぬ私自身であった。 その時の罪悪感、そして捕まった牛の私を見つめる哀し気な目が今でも忘れられない。 そんな思い出話を誰かに聞いてほしいなと思ったときに、ふと、今回のモデルである彼女のことを思い出したのである。 彼女の名前はにぅちゃん、白雪肌、黒毛和種の牛である。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 86 中野の家のこと (写真・文:オカダキサラ)
付喪神(つくもがみ)という神様がいます。長く愛された物には魂が宿るという、日本に昔からある信仰のひとつです。多くの日本人と同じく、私は宗教には無関心ですが、この付喪神の存在はなんとなく信じています。 私は人生の多くを実家で過ごしていますが、ほんのひととき、祖父母の家にお世話になりました。大学2年生の時です。自宅から武蔵美は2時間半かかりました。1年はなんとかなりましたが、2年生からは精神的に厳しくなってきました。そこで、自宅よりも大学に近いところに住んでいる父方の祖父母に、下宿させてくれないかと相談させてもらったのです。 祖父母の家は中野駅から徒歩3分、走れば1分30秒のところにありました。その家が建ったのは祖父と祖母が結婚した頃だといいます。曽祖父が持っていたひとつの敷地を、祖父兄弟で2つに分けたようです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 87 ガチャに願いを (写真・文:オカダキサラ)
大学生の頃、ほんの短い間、ラブホの清掃のアルバイトをしていました。 地元から少し離れたところにあるそのラブホは、住宅街に挟まれてひっそりと佇んでいました。元々は飲食店でオーナーは元料理人、支配人は板前の奥さんでした。 どういう経緯で飲食店からラブホに転身したのかは分かりませんが、背後にヤバい人たちを引き連れていても、全くおかしくなさそうな凄みのある夫婦でした。 アルバイトを始めた頃、アルバイトのメンバーは支配人の親戚筋にあたるお婆ちゃんと、フィリピン人のお姉さん、トラック運転手を辞めたばかりのギャル、そして私の4人でした。

photography
妄想ホテル room:048 ギャル電きょうことの「アツい」思い出 (写真・文:フクサコアヤコ)
先日、とある懐かしいイベントが9年ぶりに開催された。 そのイベントは『女装ニューハーフプロパガンダ』。日本最大級の女装イベントとしてマイノリティイベントでありながら時代の先端を切り開いていたイベントだ。当時出版した「アンダーグラウンドイベント東京」でも主催者のモカさんのインタビューとともに詳しく紹介している。そもそもこのプロパガンダというイベントがなければあの本は存在していない。それほど私の運命を大きく変えたイベントだった。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 88 エロ漫画と貸し借り時代 (写真・文:オカダキサラ)
漫画アプリで懐かしい漫画を見つけました。一条ゆかり氏の「天使のツラノカワ」と「プライド」です。 初めて一条ゆかり氏の作品を読んだのは、小学生高学年の頃でした。作家のセンスと力量の高さに、25年経って改めて衝撃を受けました。物語に引き込まれるままにページをめくり、あっという間に無料購読分を読み切りました。 有料分を購読しようとしたところで、小さい頃からよく漫画を貸してくれた友人から、たまたま連絡が来ました。 もしかしてまだ彼女は単行本を持っているかもしれない、と思い尋ねたところ「実家にあるよ!」と、快く貸してくれました。 長いこと漫画はiPhoneの画面で見ていたので、紙媒体との差に驚きました。大きさや見やすさ、目の疲れなさや手触りなど、数十年前までは当たり前だったはずなのに、とても懐かしく感じました。

photography
隙ある風景 2025 Lao Rider (写真・文:ケイタタ)
どうもみなさまご無沙汰してます。仕事でちょいとラオスに行ってました。ラオス最南端のアタプー県サンサイ郡というところで、少数民族のカフェづくりお手伝い、という謎のミッション。 さくっと仕事を終わらせて写真撮るぞなんて思っていたら、思いの外忙しく、移動中に撮るしかねえと、車の中から撮影してました。そしたら、なかなかいい写真が。「制限は創造の父、締切は創造の母」と言われますが。 テーマはラオスのライダーたちなんですが「EASY RIDER」より自由でイージー!Warの往年の名曲「Low Rider」からインスピレーションを受けて「Lao Rider」で。約50人のRiderを一挙にどうぞ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 89 人生の着替え時 (写真・文:オカダキサラ)
「定年後、男はダメになる。」 そういったのは、一回り以上年上の先輩でした。 先輩の父親はアウトドア派で、釣りや町内会のイベントにもよく参加していました。ところが、定年を迎えた後、家に引きこもりがちになってしまったそうです。 一日中テレビを見ている姿は、以前の父親とはまるで別人のよう。心配したご家族が、「テレビばかり見ているとボケちゃうよ」冗談交じりにと注意していましたが、それが現実になりました。退職して数年後には認知症が発症したのです。

photography
妄想ホテル room:049 祭りはまだ終わらない (写真・文:フクサコアヤコ)
2025年3月某日。 私は人生で初めての刈上げに挑戦していた。もみあげをバリカンで短く刈り上げる、いわゆるツーブロックというヘアスタイルである。 その日は気温も上がり外はすっかり春の陽気。半年続いたOLの仕事もあと2週間で終わろうとしており、私の気分は完全に浮足立っていた。 私の働き方は少し特殊で形としては個人事業主だが、業界が繁忙期となる秋から冬にかけてはOLとして会社に勤務し、逆に閑散期となる春から夏にかけてはフリーランスのカメラマンとして働いている。 時間の制限を受けるOL期と違って、カメラマン期は仕事をするのも遊びに出かけるのも自由だ。 誰とどんな撮影をしようかな、撮影を兼ねて旅行に出かけるのもいいな、などと私の胸は期待に大きく膨らんでいた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 90 青臭さはスパイスか? (写真・文:オカダキサラ)
SNSで、イギリス食をテーマにした漫画コラムを見かけました。 「イギリス食は本当に不味いのだろうか?」という疑問から、イギリス旅行を企画した作家さんが、いろいろなレストランやカフェ、バーを訪ねて噂を確かめた体験記です。 内容を一言でまとめると、「イギリス食は不味いと美味いの差が激しい」とのこと。例えばスコーンはとても美味しいけれど、謎のスープは食べられないほどえぐかった、というようにコース料理でも、舌がとろけそうなものと、とても完食できないものとが混在していて、評価をまとめきれないでいました。

photography
紅子の色街探訪記2 撮影日記
ロードサイダーズではもうおなじみの色街写真家・紅子さんが新作「紅子の色街探訪記2」をまもなくリリース、刊行記念写真展が東京吉原と大阪飛田新地で開催される。 紅子さんを初めてロードサイダーズで紹介したのが2022年のインタビュー。その時点でSNSで写真を発表しはじめてから2年も経っていなかった。そのころから数冊のZINEはつくっていたが、初の本格写真集「紅子の色街探訪記」を刊行したのが2023年11月末。出版のためのクラウドファンディングが「カメラを48歳から独学で始めた私に326名様が4,538,900円をご支援くださいました」という結果で、ほぼ無名の、写真を始めたばかりの女性にこれだけの支援が集まったことに驚いたひとが少なくなかったろう。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 91 おみやげはここ (写真・文:オカダキサラ)
母と私が「馬の佐藤さん」と呼んでいるマダムがいます。母も私も馬の佐藤さんと面識がありません。母の友人であるNさんの友人です。 馬の佐藤さんは資産家で、ハイブランドの洋服やバッグなどたくさん持っています。買い物することが彼女の目的なので、少し使うと満足し友人や知人にあげていたのです。 Nさんがもらったなかで、一番高価なのが馬の皮を使ったバッグだったので、あだ名が「馬の佐藤さん」になった、ということです。 私も例に漏れず、何回か馬の佐藤さんの恩恵に預かりました。母がNさんと会いにいく時は、どんなブランドものを持ち帰ってくれるのか期待していましたが、あるときぷっつりとお土産がなくなりました。

photography
妄想ホテル room:050 ハプバー単女というフィクション 初代えびまい (写真・文:フクサコアヤコ)
人生には2種類ある。 ハプニングバーを知る人生と、知らない人生だ。 中にはハプニングバーという言葉すら聞かずに終わる人生もある。 ハプニングバーとは何か。様々な性癖の人間が集い、交流し、突発的行為(ハプニング)を楽しむ場所だ。 人は刺激を求める生き物だ。けれど一方で、自分の人生に大きな影響を与えるようなハプニングが起こることは、誰しもが避けたいと願うものだ。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 14 日本で初めて写真展を開いた1980年の頃 ブルース・オズボーン(写真家)
写真家の井上清司さんと出会ったのは、彼がアマチュア写真家のグループを引率してアメリカを訪れていたときのことだった。 僕の作品を見た井上さんは、「東京で写真展を開けるよう手配できるかもしれませんが、興味ありますか?」と声をかけてくれた。 まるで宙に舞い上がるような気持ちで、胸が高鳴ったのを今でもはっきりと覚えている。 日本で写真展を開く――そんな夢が、突然、現実味を帯びてきたのだ。迷うことなく「YES!」と返事をした。 1980年春、日本橋にある小西六ギャラリーでの写真展開催が決定。 僕はロサンゼルスの街、人々、そしてクリエイターたちをテーマにした三部構成の展覧会を企画し、タイトルを『La Fantasies 三部作』と名づけた。

photography
天野裕氏 あなたがここにいてほしい
すでにお知らせしたとおり、いま渋谷ミヤシタパーク内のギャラリーSAIで天野裕氏個展「あなたがここにいてほしい」が開催されている。 1978 年、福岡県北九州市に生まれた天野は、30歳の頃より写真を撮り始め、2009 年には塩竈フォトフェスティバルで大賞を受賞し、写真界において鮮烈なデビューを果たします。その後、全国を軽自動車で寝泊まりをしながら旅を続け、日時と場所を SNS 上で指定し、そこへ訪れた者に1 対 1 で自作の写真集を閲覧させる「鋭漂」というスタイルを 17 年間続けます。2020 年頃からは大牟田にあるもとはラブホテルであった自宅マンションを、図書館兼ギャラリーとして、いつでも誰でも訪れることのできる場所として解放し、写真家としての活動の幅を大きく超えていきます。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 92 ロマンスをリボンで結んで (写真・文:オカダキサラ)
私は一時ボーイズラブ、略してBLにどハマりし、プロアマ問わず作品を夢中で読み漁っていました。 私にとってBLの何がそんなに良かったのかというと、物語の誰にも自分を重ねることがなかったからなんじゃないかと思っています。 主人公のどちらかが女性だと「え、同じ女性として、そんなことするかな?」と、読書中に現実が差し込んできて、物語の邪魔になっていました。 BLでは主人公たちはどちらも男性で、自分の境遇に重ねる前提条件がないからこそ、ファンタジーの世界に没入できたのです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 93 愛を求めた、ロボットと老人の話 (写真・文:オカダキサラ)
「もしも自分以外の人類が滅亡したらどうする?」 そんな話題が教室のあちこちで交わされていました。ノストラダムスの大予言が、メディアで大きく取り上げられていたからです。 「世界は滅びるかもしれない」と騒がれていた1999年。そんな馬鹿な、とみんな笑いながらも、もしかしたら…という緊張感が、ほんの少し交じってました。 「もう少しで予言の日だね」「どうなるんだろう?」「えーみんな死んじゃうんじゃない?」「やだあ!自分だけ生き残ったらどうする?」という会話が、あちこちで繰り広げられていました。

photography
妄想ホテル room:051 メイクという魔法 (写真・文:フクサコアヤコ)
その日私はいつもの待ち合わせ場所、歌舞伎町の風林会館の前にいた。 ここを待ち合わせ場所に指定するのは、行きつけのラブホに近いというのもあるけれど、それ以上にこの界隈で繰り広げられる“人間ドラマ”を眺めるのが好きだからだ。 夜になると、若手ホストたちが一斉に出勤し、また、同伴に向かう男女が入り乱れる。歌舞伎町らしい、独特の空気が何とも趣深い。 一方この日は待ち合わせが午前中だったため、いつもとは違った朝の歌舞伎町を見ることができた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 94 フィルムとバナナケーキ (写真・文:オカダキサラ)
久しぶりにフィルムカメラを使いました。最後に触れたのは、大学の授業のとき。それから、もう18年が経っていました。 当時の武蔵野美術大学の映像学科では、フィルムカメラでの写真表現は必修科目でした。 私は新しいもの好きの父の影響で、早い段階からデジタルカメラを使っていました。父の仕事の関係でPhotoshopが自宅のPCにダウンロードされてたので、父が使っていない時は自由に使ってよかったのです。大学入学時にはすっかりデジタルっ子になっていました。 初めて使う一眼レフカメラの操作は楽しかったものの、デジタル操作に慣れすぎていた私は、フィルム写真制作のコスパの悪さに、イライラするようになりました。フィルム写真って、やっぱり面倒くさいなあ。そんな気持ちがきっと作品にも表れていたのでしょう。提出した作品は酷評で、私はますますフィルム写真が苦手になったのです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 95 そこに座る覚悟について (写真・文:オカダキサラ)
先月、先々月と立て続けに脂肪溶解注射を、お尻に打ちました。 私はおしりの脂肪の多さが、昔からコンプレックスです。かっこいいお尻の大きさなら文句はないのですが、生憎、私は後ろ姿がだらしなく見えるタイプで、お尻の形が気になって試着室で購入を諦めた服が山のようにあります。 そんな悩みを見透かすように、漫画アプリで脂肪細胞をなくす医療痩身の広告が流れてきました。 えー、どうせ高いんでしょ…、と最初は思っていたのですが、そのうち何をしても変わらないこのお尻に悩まされ続けて人生を送るより、「やってやったぜ!」と満足して死ぬ方がいんじゃないかと思うようになり、受診を決意しました。

photography
妄想ホテル room:052 野球と恋 (写真・文:フクサコアヤコ)
夏になると思い出す音がある。 蒸し暑い風に乗って、部屋の中に入り込んでくる虫の声、扇風機の規則的な音。 夕飯の残り香が漂うリビングには、テレビから流れるプロ野球ナイター中継の音が重なっていた。それは、私にとって“昭和の夏”の象徴とも言える音の風景だ。 小学生の頃、そんな音が聞こえてくると宿題もそこそこに私はテレビの前に駆け寄った。 好きな球団が勝てば嬉しい、負けると悔しい。プロ野球は単なる娯楽ではなく、自分の感情を素直に託せる場所でもあった。 ヒーローのように活躍する選手を見て、自分も何かがんばれる気がしたし、ひいきの球団とともに長いシーズンを一緒に走っている感覚が心地よかった。 プロ野球には、そんなふうに人生の一部になってしまうような不思議な力がある。 今回紹介するモデル・石川陽波さんも、そんなプロ野球に魅せられた一人だ。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 96 放課後のひとつぶ (写真・文:オカダキサラ)
梅雨入りしたというのに、雨があまり降らない2025年の夏。太陽を隠す雨雲もなく、熱と湿気が長時間続く最悪な酷暑週間となっています。 そんな中、押し入れと倉庫の2カ所をメインに大掃除しました。 思い出の掃き溜めのようになっている押入れと倉庫を整理するには、相当な気合いが必要でした。 「こんなものまで!?」と驚いた思い出の品のひとつに、学生時代の成績表がありました。 捨てたと思っていたのですが、両親が取っておいてくれたのですね。 先生の丁寧な字で綴られていた私の長所と短所は、今に通じるものがあり、グサグサと心に刺さりながらも、よく見ていてくれてたんだなぁ、と感心もしました。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 97 間に合わなくていい、と思えるまで (写真・文:オカダキサラ)
私は高校生の時に、東西線を使って通学していました。東西線は長年、都内の混雑路線ランキング1位に輝いていた路線です。スーツを着たおじさんの贅肉に揉みくちゃにされ、時に骨に不穏な軋みを感じながら、命懸けで登校する毎日。そんな最悪な記憶が忘れられず、卒業後は東西線は避けるようになりました。フリーランスになってからは、ラッシュ時を避けて移動できるようになりました。かなり快適なのですが、電車が発車しそうになると、たとえ車内が人でぎゅうぎゅうになっていても、「乗らなければ…!」という衝動に駆られます。次の電車を待っても大丈夫とわかっていても止められません。

photography
妄想ホテル room:053 心に不健全な犬を飼う (写真・文:フクサコアヤコ)
子どものころ、我が家には一匹の犬がいた。 ボクサーという犬種で、ブルドックを少しスマートにしたような、いかつい見た目の犬だった。 猟犬として、獲物を追い詰め、猟師が到着するまでしっかりとくわえて確保する、そんな役割を持つ犬だそうで、狩猟好きの叔父に飼われていたが、年老いて引退した後、我が家に引き取られることになった。 私が両親と暮らし始めたのは4歳のころ。 ちょうど同じタイミングで我が家にやってきたその犬は、新しい生活になじめず戸惑う私の最高の友達となってくれた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 98 紫鏡とパンツ一丁の怪 (写真・文:オカダキサラ)
私はホラー映画が苦手で、「あまりに怖い」と評判の映画は今でも避けています。 ホラーがダメになったのは、小学5年生のときに映画館で観た「リングゼロ」がきっかけです。その前から怖いものは苦手だったのですが、友達の「ぜったい面白いから」という激推しに「そうかも」と流されてしまったのがいけなかった……。映画館の帰りには深く後悔しました。もしかして貞子を持ち帰ってきてしまったかもしれない、という恐怖が、何をしていてもぴったり背中に貼りついて離れないのです。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 15 浅草でスタートした刺激的な日本生活 ブルース・オズボーン(写真家)
引越し先の条件として、僕がどうしても譲れなかったのが、「スタジオのない生活は考えられない」ということだった。 当時の僕にとって、自分のスタジオは写真を撮るうえで不可欠な場所。 「カウボーイに馬が必要なように、写真家にはスタジオが必要だ」と、頑固に言い張った。 そんな僕のために、佳子が照明のデザインをしていた取引先だった会社の社長さんが、「会議室をスタジオとして使ってもいいよ」と申し出てくれた。しかも、同じビルの上の階に住居として使える空き部屋まであるという幸運! こうして、スタジオも住まいも無事に確保することができ、1980年7月28日、僕たちはスーツケースをそれぞれ1つづつ持って、再び日本へ—— 向かうは、浅草!!!

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 99 缶コーヒーの味と記憶 (写真・文:オカダキサラ)
先日、同年代と話していた時、最近の流行りの曲を追いかけきれていないと話題になりました。テレビCMや広告ポスター、サイネージに登場するタレントが分からないのです。 私が小学生の頃、家族やご年配がテレビに出演しているモー娘を見ても、「誰が誰だか分からない」と言っていた気持ちが、この歳になってようやくよく分かってきました。 代わりに、昔聴いていた曲はなんとなく覚えていて、今でもちょっとのフレーズだけなら口ずさめたりします。

photography
妄想ホテル room:054 欲望という名の癒し 癒しという名の欲望 (写真・文:フクサコアヤコ)
東京の夜は、いつだって欲望に満ちている。 とりわけ歌舞伎町は、その欲望がむき出しになっている街だ。 風林会館の前に立ち、行き交う人々を眺めながら、私はふと考える。 この街に集まる人々は、何を求めてここに来るのだろう。 快楽か、癒しか、それともその両方か。 ふと見上げるとホストの看板からは煽るような文句が消え、どことなく勢いを失ったように見える。 けれど、街の熱は変わらない。 人々はそれぞれ、自分だけの欲望を胸に抱えながら歩いている。 それは誰にも見せない、けれど確かに存在する、心の奥の火種のようなもの。 欲望は、いつも孤独と隣り合わせだ。 だからこそ、人は誰かに触れてほしいと願う。 触れることは、孤独を分かち合うことでもあるから。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス100 (写真・文:オカダキサラ)
今回でなんと連載100話目を迎えました。 お話をいただいた時は続けられるか不安でしたが、2週間に一度、つつがなく掲載し続けることができました。サポートいただいた都築さん、ROADSIDERS' weeklyのスタッフの皆さん、毎回添削をしてくれる母、そして読者の皆様のおかげです。ありがとうございます。 100話目を迎えるにあたりなにかできないか、都築さんと相談をしました。その日は、アシスタントの仕事で八丈島に出張する前日でした。「八丈島は、どことも違う独特な空気が流れていて面白いよ」と都築さんにいわれ、八丈島への期待がますます高まったのです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 101 推しは沈黙をほどく (写真・文:オカダキサラ)
世間ではコンプライアンスを重視する動きが強まっています。相手を思いやる気持ちは大事ですが、困ったこともいくつかあります。 会話が続かないのです。 恋人の有無を聞いてはダメ。 結婚してるか独身なのか、聞いてはダメ。 子供がいるのかいないのか、聞いてはダメ。 家族や親族のことを、聞いてはダメ。 出身地を、聞いてはダメ。 住んでいる地域を、聞いてはダメ。 ・・・・・・などなど、NGトピックが多すぎて何を話していいのか戸惑います。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 102 THE オールドニューボディー (写真・文:オカダキサラ)
最近、SNSを見る時間があまり確保できません。以前であれば移動の合間によく見ていたのですが、今はメールや予定のチェック、連絡の返信や仕事の準備で精一杯です。 15年ほど前、SNSの黎明期といえる時期に、当時30代後半の先輩が言っていた言葉を思い出しました。 「もうこの歳になれば、みんなSNSは卒業なんだよ。人の意見や投稿を受け止めるだけの時間と心の余裕がなくなるからね」

photography
妄想ホテル room:055 恥ずかしいという感情が私にとって一番苦しい (写真・文:フクサコアヤコ)
私が普段写真を撮るとき、「顔」はさほど重要ではない。 人も風景の一部だと思っているので、それが女性だろうが男性だろうが、服を着ていようが裸だろうが、ただそこに在ってくれさえすればいい、という気持ちで撮影している。 女性のヌードが多いのは、女性の方が風景に溶け込みやすい気がするという、ただの感覚的な選択にすぎない。 肝心なのは顔ではなく、佇まいだ。誰かが「そこに在る」ことで生じる空気の揺らぎ、その微細な模様を捉えることが、私の撮影の目的であり、願いでもある。 私のレンズはいつも、顔ではなく存在を見ている。そうは見えないかもしれないが。。。 ところがそんな私にも好みの顔というものがある。いやどうやらあるらしいということに今回の撮影で気が付いた。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 103 覗き窓の先にある温度 (写真・文:オカダキサラ)
オールドレンズの風合いを、デジタルレンズで表現するのは難しい、という話を聞きました。 人の心に訴えかけるような温かみのある美しさは、数値化しにくいからとのことです。 これだけAIが発達しつつある時代になっても、人の心を数や記号で正確に表現するのは、まだまだ難しいと聞いて嬉しくなりました。 この間の新聞に、AIを親友と思う人が多くいるという記事がありました。 温かな一言から始まるAIの回答は、他者のアドバイスよりも受け入れやすく、何を相談しても質問者を第一に考慮してくれるので、失敗や人に打ち明けられない悩みも、打ち明けやすいなと、私も感じています。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 104 夢見る自動追跡 (写真・文:オカダキサラ)
自動車が高速道路を自動運転で走る実証実験を始めたと知り、驚いています。 私はペーパードライバーになって5年が経ちます。運転が怖く、ハンドルを握る勇気がなかなか出ません。一方で、重たい撮影機材を電車で運ぶのもそろそろ限界で、頭を抱えています。 そんな私にとって「完全自動運転の車」は一刻も早く実現してほしい夢の乗り物です。 カメラ機材を詰め込んだバッグやキャリーカーは、いつも憂鬱の種でしかありません。

photography
追悼:「スティルライフ」とダイアン・キートン
先々週は広島太郎の訃報をお伝えしたが、10月にはもうひとり個人的に残念な死去のニュースがあって、それは10月11日に知らされたダイアン・キートンの訃報だった。79歳、肺炎だったという。映画『アニー・ホール』でアカデミー主演女優賞を受賞したのが1977年だから、あれから半世紀も経ったのかという感慨もあった。 ダイアン・キートンは女優だけでなく映画監督でもある。優れたファッション・センスでも知られていたし、公私とものパートナーだったウディ・アレンをはじめ、ウォーレン・ベイティ、アル・パチーノと、華麗な交際歴もあった(結婚歴はなし)。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 16 東京ワンダーランド ブルース・オズボーン(写真家)
「写真家にとってスタジオは、カウボーイにとっての馬のようなものだ」――そんなことを豪語していた僕にぴったりな住まい兼スタジオのスペースが見つかって、浅草での生活がスタートすると、雑誌関係者や音楽業界、広告会社の人たちが打ち合わせと称して頻繁に訪れるようになった。「浅草がソーホーに!」とまで紹介した雑誌もあったほど。 せっかくたくさんの人が来るんだからと、スタジオに来る人たちのポートレートを撮ることを思いついた。それも、ただのポートレートではなく“爆笑ポートレート”。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 105 恥じらい写真家の自撮り修行 (写真・文:オカダキサラ)
最近、カメラ雑誌「フォトコン」で自撮り企画の依頼を受けました。 スマホではなくカメラで、三脚やストロボを使って本格的なポートレートを撮ろうという主旨です。 写真家がコンテストで受賞した時のポートレートが、家族や知人がなんとなく撮った写真だと、どうにも締まりません。かといってプロに頼むのも現実的ではありません。 それなら自分のポートレートくらい自分で撮ってしまえばいいのでは?というのが企画の狙い。 そして裏テーマは「お気に入りの遺影を元気なうちに残しておこう」でした。毎年恒例の企画らしいのです。

photography
ニュー・シャッター・パラダイス 106[最終回] おめでとうの芽生え (写真・文:オカダキサラ)
年の瀬になり、1年を振り返る機会が多くなりました。 今年もさまざまな出来事がありましたが、その中で特に心に残ったニュースがふたつあります。不登校の児童生徒の数と、新卒の転職率が過去最高になったことです。 どうしてこんなにも胸に引っかかるのだろうと考えてみると、「自分の時代には許されなかったこと」だからだと気づきました。 不登校の子はろくな大人にならない、成功していないのに転職するなんて能力がない――そんな言葉を直接言われてはいませんが、“そういう空気”を感じながら育ったのは確かです。 学歴重視、不景気、就職氷河期。私の世代を取り巻いていた時代背景が、そうした価値観を作っていたのかもしれません。

photography
妄想ホテル room:056 大塚 記念湯 タイムカプセル[最終回] (写真・文:フクサコアヤコ)
人とのめぐりあわせが縁であるように、人と街にもまた、静かに結ばれる縁があるのだと思う。 私は佐世保で生まれ、京都、東京と縁を結んで今ここにいる。 佐世保は生まれ故郷だし、京都は大学時代を過ごした青春の地、そして東京は――気づけば二十年近く身を置いている街だ。 それでも時折、胸の奥にふっと風が吹き抜けるように、この街にいる自分がよそ者のように感じる瞬間がある。 どんなに駅の乗り換えがスムーズにできるようになろうと、東京中のラブホテルに詳しくなろうと、私はどこか「たまたま訪れただけの旅人」のままだ。 けれど最近になって、もしかすると私は東京に戻ってくる運命だったのかもしれないと思うようになった。 忘れていた記憶が、胸の奥で小さな音を立てて動き出した。

photography
once upon a time ~ もうひとつのカリフォルニア・ドリーミン 17[最終回] EAST MEETS WEST ブルース・オズボーン(写真家)
アメリカを出発し、ヨーロッパ各地を巡り、その先に続くアジアの国々を旅して、たどり着いた日本。 二十代後半の頃のことだったから、かれこれ半世紀近い時間が流れている。 その長い旅を振り返りながら once upon a time というブログを書くことになったのは都築響一くんと再会し、彼が主宰するメールマガジン「ROADSIDERS’ WEEKLY」で連載を始めたのがきっかけだった。 その連載も、今回で最終回を迎える。 それに伴い、Vol.17 まで続いてきた once upon a time のストーリーも、ひとまずここで一時休止することになった。 懐かしい思い出が、去来する。

photography
世界の中のインド亜大陸食紀行/日本編[最終回] タージマハルの幻影を求めて (写真・文:小林真樹 / 編集:島田真人)
「それで、タージマハルは見てきたの?」 インドに行った人たちが、帰国後にまず聞かれるのがこの質問だろう。つまりタージマハルとは、それだけインドという国を象徴するアイコンなのだ。もちろん私も初インドの際は見に行き、その壮麗さに深く感動した。 1653年にシャージャハーンによって建立されたタージマハルは宮殿ではなく、実は妃であるムムターズの墓陵である。
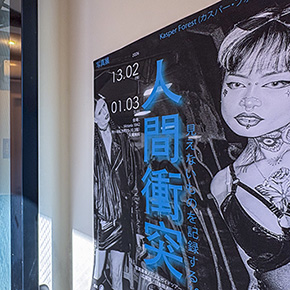
photography
見えていなかった香港の人間劇場
大日本印刷の巨大な建物群が広がる市ヶ谷の外堀に面する市谷田町あたり。交差点から新潮社を経て神楽坂上に向かう牛込中央通りに、「Victoria1842」というカフェ兼書店兼ギャラリーができているのを僕は先週まで知らなかった。 2024年にふたりの香港人がオープンさせたVictoria1842は、「香港の文化と価値を日本へ紹介していくことを使命としたプラットフォーム」。東京における香港文化の発信拠点を目指して開設されたという。

photography
雨の日でもトラックを洗車する人間たちへ
少し前にルイーズ・ミュトレル(Louise Mutrel)という若い写真家と知り合った。 パリ郊外ボビニーにある「Le Wonder」という巨大なアーティスト・コレクティブを拠点に活動を続けているルイーズは、2024年にフランス政府のアーティスト・イン・レジデンス施設である京都のヴィラ九条山に滞在。その際に知り合ったのだが、もともとは2017年に日本に1年間滞在中、築地市場で偶然デコトラに出会い、SNSで各地のデコトラ好きと関係をつないで2019年から22年にかけて日本各地で開催される集会を記録して回った。24年に来日したときにはそのプロジェクトのインタビューで僕に連絡してくれたのだった。

photography
「地の橋、人の橋」と「ネオン管の抒情」 ――イランの「普通の暮らし」に思いを馳せて
ようやく冬季オリンピックが終わって夜更かし週間終了と思いきや、いきなりアメリカとイスラエルによるイラン攻撃が勃発、またも布団の中でネット・ニュースをスクロールし続ける、眠れない夜がやってきてしまった。去年6月の爆撃でイランの核関連施設は「完全に破壊した」と自慢していたのは、いったいなんだったんだろう。世界最強の軍隊を最狂の大統領(と取り巻き)が操るという・・・キューブリックの『博士の異常な愛情』みたいな現実が訪れると、つい先月りくりゅうやアリサ・リウに感涙していた僕らのだれが想像できたろうか。
- TOP
- バックナンバー
バックナンバー検索
月別バックナンバー
- 2026年03月
- 2026年02月
- 2026年01月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年09月
- 2025年08月
- 2025年07月
- 2025年06月
- 2025年05月
- 2025年04月
- 2025年03月
- 2025年02月
- 2025年01月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年09月
- 2024年08月
- 2024年07月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年09月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2023年04月
- 2023年03月
- 2023年02月
- 2023年01月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年02月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
- 2021年05月
- 2021年04月
- 2021年03月
- 2021年02月
- 2021年01月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年09月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年02月
- 2019年01月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年07月
- 2018年06月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2018年01月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年03月
- 2017年02月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年06月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月
- 2015年06月
- 2015年05月
- 2015年04月
- 2015年03月
- 2015年02月
- 2015年01月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年09月
- 2014年08月
- 2014年07月
- 2014年06月
- 2014年05月
- 2014年04月
- 2014年03月
- 2014年02月
- 2014年01月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年09月
- 2013年08月
- 2013年07月
- 2013年06月
- 2013年05月
- 2013年04月
- 2013年03月
- 2013年02月
- 2013年01月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年09月
- 2012年08月
- 2012年07月
- 2012年06月
- 2012年05月
- 2012年04月
- 2012年03月
- 2012年02月
- 2012年01月
カテゴリ別バックナンバー
BOOKS
ROADSIDE LIBRARY
天野裕氏 写真集『わたしたちがいたところ』
(PDFフォーマット)
ロードサイダーズではおなじみの写真家・天野裕氏による初の電子書籍。というか印刷版を含めて初めて一般に販売される作品集です。
本書は、定価10万円(税込み11万円)というかなり高価な一冊です。そして『わたしたちがいたところ』は完成された書籍ではなく、開かれた電子書籍です。購入していただいたあと、いまも旅を続けながら写真を撮り続ける天野裕氏のもとに新作が貯まった時点で、それを「2024年度の追加作品集」のようなかたちで、ご指定のメールアドレスまで送らせていただきます。
旅するごとに、だれかと出会いシャッターを押すごとに、読者のみなさんと一緒に拡がりつづける時間と空間の痕跡、残香、傷痕……そんなふうに『わたしたちがいたところ』とお付き合いいただけたらと願っています。
ROADSIDE LIBRARY vol.006
BED SIDE MUSIC――めくるめくお色気レコジャケ宇宙(PDFフォーマット)
稀代のレコード・コレクターでもある山口‘Gucci’佳宏氏が長年収集してきた、「お色気たっぷりのレコードジャケットに収められた和製インストルメンタル・ミュージック」という、キワモノ中のキワモノ・コレクション。
1960年代から70年代初期にかけて各レコード会社から無数にリリースされ、いつのまにか跡形もなく消えてしまった、「夜のムードを高める」ためのインスト・レコードという音楽ジャンルがあった。アルバム、シングル盤あわせて855枚! その表ジャケットはもちろん、裏ジャケ、表裏見開き(けっこうダブルジャケット仕様が多かった)、さらには歌詞・解説カードにオマケポスターまで、とにかくあるものすべてを撮影。画像数2660カットという、印刷本ではぜったいに不可能なコンプリート・アーカイブです!
ROADSIDE LIBRARY vol.005
渋谷残酷劇場(PDFフォーマット)
プロのアーティストではなく、シロウトの手になる、だからこそ純粋な思いがこめられた血みどろの彫刻群。
これまでのロードサイド・ライブラリーと同じくPDF形式で全289ページ(833MB)。展覧会ではコラージュした壁画として展示した、もとの写真280点以上を高解像度で収録。もちろんコピープロテクトなし! そして同じく会場で常時上映中の日本、台湾、タイの動画3本も完全収録しています。DVD-R版については、最近ではもはや家にDVDスロットつきのパソコンがない!というかたもいらっしゃると思うので、パッケージ内には全内容をダウンロードできるQRコードも入れてます。
ROADSIDE LIBRARY vol.004
TOKYO STYLE(PDFフォーマット)
書籍版では掲載できなかった別カットもほとんどすべて収録してあるので、これは我が家のフィルム収納箱そのものと言ってもいい
電子書籍版『TOKYO STYLE』の最大の特徴は「拡大」にある。キーボードで、あるいは指先でズームアップしてもらえれば、机の上のカセットテープの曲目リストや、本棚に詰め込まれた本の題名もかなりの確度で読み取ることができる。他人の生活を覗き見する楽しみが『TOKYO STYLE』の本質だとすれば、電書版の「拡大」とはその密やかな楽しみを倍加させる「覗き込み」の快感なのだ――どんなに高価で精巧な印刷でも、本のかたちではけっして得ることのできない。
ROADSIDE LIBRARY vol.003
おんなのアルバム キャバレー・ベラミの踊り子たち(PDFフォーマット)
伝説のグランドキャバレー・ベラミ・・・そのステージを飾った踊り子、芸人たちの写真コレクション・アルバムがついに完成!
かつて日本一の石炭積み出し港だった北九州市若松で、華やかな夜を演出したグランドキャバレー・ベラミ。元従業員寮から発掘された営業用写真、およそ1400枚をすべて高解像度スキャンして掲載しました。データサイズ・約2ギガバイト! メガ・ボリュームのダウンロード版/USB版デジタル写真集です。
ベラミ30年間の歴史をたどる調査資料も完全掲載。さらに写真と共に発掘された当時の8ミリ映像が、動画ファイルとしてご覧いただけます。昭和のキャバレー世界をビジュアルで体感できる、これ以上の画像資料はどこにもないはず! マンボ、ジャズ、ボサノバ、サイケデリック・ロック・・・お好きな音楽をBGMに流しながら、たっぷりお楽しみください。
ROADSIDE LIBRARY vol.002
LOVE HOTEL(PDFフォーマット)
――ラブホの夢は夜ひらく
新風営法などでいま絶滅の危機に瀕しつつある、遊びごころあふれるラブホテルのインテリアを探し歩き、関東・関西エリア全28軒で撮影した73室! これは「エロの昭和スタイル」だ。もはや存在しないホテル、部屋も数多く収められた貴重なデザイン遺産資料。『秘宝館』と同じく、書籍版よりも大幅にカット数を増やし、オリジナルのフィルム版をデジタル・リマスターした高解像度データで、ディテールの拡大もお楽しみください。
円形ベッド、鏡張りの壁や天井、虹色のシャギー・カーペット・・・日本人の血と吐息を桃色に染めあげる、禁断のインテリアデザイン・エレメントのほとんどすべてが、ここにある!
ROADSIDE LIBRARY vol.001
秘宝館(PDFフォーマット)
――秘宝よ永遠に
1993年から2015年まで、20年間以上にわたって取材してきた秘宝館。北海道から九州嬉野まで11館の写真を網羅し、書籍版では未収録のカットを大幅に加えた全777ページ、オールカラーの巨大画像資料集。
すべてのカットが拡大に耐えられるよう、777ページページで全1.8ギガのメガ・サイズ電書! 通常の電子書籍よりもはるかに高解像度のデータで、気になるディテールもクローズアップ可能です。
1990年代の撮影はフィルムだったため、今回は掲載するすべてのカットをスキャンし直した「オリジナルからのデジタル・リマスター」。これより詳しい秘宝館の本は存在しません!
捨てられないTシャツ
70枚のTシャツと、70とおりの物語。
あなたにも〈捨てられないTシャツ〉ありませんか? あるある! と思い浮かんだあなたも、あるかなあと思ったあなたにも読んでほしい。読めば誰もが心に思い当たる「なんだか捨てられないTシャツ」を70枚集めました。そのTシャツと写真に持ち主のエピソードを添えた、今一番おシャレでイケてる(?)“Tシャツ・カタログ"であるとともに、Tシャツという現代の〈戦闘服〉をめぐる“ファッション・ノンフィクション"でもある最強の1冊。 70名それぞれのTシャツにまつわるエピソードは、時に爆笑あり、涙あり、ものすんごーい共感あり……読み出したら止まらない面白さです。
圏外編集者
編集に「術」なんてない。
珍スポット、独居老人、地方発ヒップホップ、路傍の現代詩、カラオケスナック……。ほかのメディアとはまったく違う視点から、「なんだかわからないけど、気になってしょうがないもの」を追い続ける都築響一が、なぜ、どうやって取材し、本を作ってきたのか。人の忠告なんて聞かず、自分の好奇心だけで道なき道を歩んできた編集者の言葉。
多数決で負ける子たちが、「オトナ」になれないオトナたちが、周回遅れのトップランナーたちが、僕に本をつくらせる。
編集を入り口に、「新しいことをしたい」すべてのひとの心を撃つ一冊。
ROADSIDE BOOKS
書評2006-2014
こころがかゆいときに読んでください
「書評2006-2014」というサブタイトルのとおり、これは僕にとって『だれも買わない本は、だれかが買わなきゃならないんだ』(2008年)に続く、2冊めの書評集。ほぼ80冊分の書評というか、リポートが収められていて、巻末にはこれまで出してきた自分の本の(編集を担当した作品集などは除く)、ごく短い解題もつけてみた。
このなかの1冊でも2冊でも、みなさんの「こころの奥のかゆみ」をスッとさせてくれたら本望である。
独居老人スタイル
あえて独居老人でいること。それは老いていくこの国で生きのびるための、きわめて有効なスタイルかもしれない。16人の魅力的な独居老人たちを取材・紹介する。
たとえば20代の読者にとって、50年後の人生は想像しにくいかもしれないけれど、あるのかないのかわからない「老後」のために、いまやりたいことを我慢するほどバカらしいことはない――「年取った若者たち」から、そういうスピリットのカケラだけでも受け取ってもらえたら、なによりうれしい。
ヒップホップの詩人たち
いちばん刺激的な音楽は路上に落ちている――。
咆哮する現代詩人の肖像。その音楽はストリートに生まれ、東京のメディアを遠く離れた場所から、先鋭的で豊かな世界を作り続けている。さあ出かけよう、日常を抜け出して、魂の叫びに耳を澄ませて――。パイオニアからアンダーグラウンド、気鋭の若手まで、ロングインタビュー&多数のリリックを収録。孤高の言葉を刻むラッパー15人のすべて。
東京右半分
2012年、東京右傾化宣言!
この都市の、クリエイティブなパワー・バランスは、いま確実に東=右半分に移動しつつある。右曲がりの東京見聞録!
576ページ、図版点数1300点、取材箇所108ヶ所!